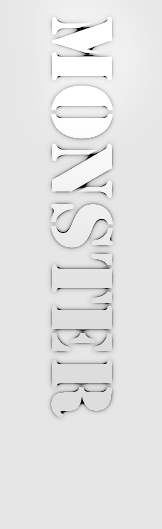MONSTER
28.噛みちぎれ!
どうやら、顔を殴られすぎたようだ。
こういうとき、痛みはなかなかやってこない。血も、実はあまり出ない。皮膚は万能だ。引かれれば伸び、打たれれば撓む。同じところを繰り返し繰り返し執拗に殴りつけられて初めて裂けるのだ。最初はまず熱が来る。火で炙られているように熱い。それを過ぎれば今みたいに、鉛のように重くなる。手足ならまだいい。折られないうちは動く。問題は首から上だ。痛みが来る来ないの前に、意識を削り取られてゆくのだ。朦朧としているうちに何をさせられるのか。それが最も恐ろしい。恐ろしくて憎い。死ぬほど憎くて、怖い。暗いところが怖い。視界が霞むとよりいっそう、なにも見えない。もう自分の四肢さえどこにあるのか覚束ない。あたり一面真っ暗だ。寒くて、臭くて、暗い。落ちてゆく。しがみつくように動く指を掻けば爪の間に何かが食い込んだ。きっと砂利だ。およそ考え付く汚いもの全てが染み付いた、あの岩の中の砂。また、あそこに転がっているのか。あの岩の中で、あの腐った連中に囲まれて。もういい、もうたくさんだ。誰に縋るのももうやめた。祈らない。願わない。叶えるんだ。考えろ。描け、導け、そして唱えろ。言葉は無意味だ。だが力でもある。
「…死にたくない…」
歯軋りで顎が歪む。バリッ、と小指の爪が剥がれあがった。血が溢れる感触がほかの指にも伝わってゆく。
「こんなところで…死にたくない…ッ、」
耳鳴りが酷い。そこに混じる大人達の怒鳴り声。男も、女もいる。遠巻きにこちらを伺う声だ。それはそのうちすぐ下卑た嘲笑に変わって、やがて、手が伸びてくる。あとはいいようにされる。したたかに殴られ、髪をむしられ、体中をいろんなものが這い回る。暗い。なにも見えない。のしかかってくる相手の顔すらわからない。ただ、笑っているのはわかる。全員笑っている。自分を見下ろして、笑っている。
「…殺してやる、」
渾身の力を込められた左手の爪が残さず剥がれ上がった。破片が床に突き立つ。剥き出しの肉片じみた指先が執拗に辺りを掻き毟る。鮮血が飛散った。
「殺してやる、殺してやる、ころしてやるころしてやるころしてやる殺してやる! お前らも、あいつらも、何もかもだ! わたしを笑うやつはみんな死ねばいい!」
怒号とともに血痰が飛ぶ。かすれた視界の先、大人の固まりがざわつきながら変わらずこちらを見下ろしている。四つんばいから立ち上がろうともがくも、片腕が使い物にならないせいか思うように動けない。やり場のない憤りが喉よ裂けよと迸る。
「いまさら何を訊くっていうのよ! わたしは知らない、あいつらが何かも、どうしてこうなったのかも、何故わたしなのかも、なにもかも、なにもかも! なにもかも全部よ! なのに、わたしを切り捨てた連中が、今更自分の都合でわたしを詰るの!? そんなの許さない、許すもんか!! 」
誰かの手が一斉に両肩へ圧し掛かった。また顎から打ち付けられる。鼻から脳へ衝撃が突き抜ける。瞼に閃光が散った。些細なことだ。
「っ、わたしは…ッ、」
この屈辱に比べれば。
「わたしは、お前らなんかにもうなにも言わない!!」
わかったのは、そこまで。
あとは、殆ど聞き取れない言葉だった。突然暴れだしたは俄かに血走った目つきで口角泡を飛ばし、決して届かないリヴァイへ飛び掛らんと必死でもがいている。その姿は狂気じみて、しかしまぎれもない少女の姿をとる。三人がかりの拘束である。飛び出したのは偶然だがこの判断が正解だった。ほぼ折れた右腕と左腕、腰から下に大の大人の体重をかけている。にも拘らず、気を抜けば滑る汗も手伝って抜けられそうになる。それほど、圧し掛かる兵士が思わず生唾を飲み込む迫力だった。
まるで、生け捕りにされた巨人だ。こちらを食い殺さんばかりにもがき、足掻き、牙を向く。違うのは目だけだ。痛いほど覚えのある目。鏡を覗けば、そこにはいつもこの目がある。暴れる少女を見つめるリヴァイの脳裏でふと、かつて地下牢で咆哮した痩せぎすの男の姿が蘇ってきた。
お前らに反吐が出る。
軍人が壁を守らない所為で多くの人が死んだ。簡素で飾りのない、だからこそまっすぐに刺さる言葉。意味がないとは、そういうことか。切れ長の目が鈍く瞬く。
「…あれは、お前の言葉だったのか」
まるでこぼれるように落ちた言葉に全員が訝った、その時だった。
「―――これは、」
三度、戸口側で静かな驚嘆が上がった。凄惨な室内を嬉々とした顔で見つめる男、その顔に載る硝子が鈍く反射している。手負いの獣さながらに意味のない大音声を上げ続けるを注意深く見下しながら、ギュルヴィ・レイが笑みもそこそこに、思いのほか軽い身のこなしで騒ぎの元へ歩み寄ってくる。辺りをついと見渡し、小首を傾げてみせる。
「騒がしいと思えば、またあなた方ですか。つくづく懲りない連中だ」
誰も、なにも答えない。先だって乗り込んできた駐屯兵士さえ、顔色を失くしたまま激しく暴れ続ける少女を食い入るように見つめている。その様に片眉を跳ねさせながら、憲兵団の男が徒に歩を進めてゆく。
「管轄外の、しかも病棟内での秘匿的かつあからさまな暴力行為。あなた方、そんなに処分されたいのですか?」
「それ以上近寄るな」
低い声が遮る。歩は止めず、ギュルヴィの笑みが深くなった。
「私に命令できる立場ですか」
「忠告だ」
「ああ、この少女がウォール教の」
リヴァイを素通りし、やや踵の高い誂えの靴音も高らかに、憲兵団の男は伏せたへ近付いていく。徐々に消耗し始めたのか、少女は未だもがきながらも、咆哮するようだった叫びを荒く息を弾ませ唸る声に変え、血走った目つきで忙しなく辺りを睨み続けている。やや手前で、その様を見下ろしつつ男が足を止めた。コツ、と踵が鳴る。
「よく生き残っていたものです。連中にとって子供が一番の"ご馳走"ですからね。血の一滴、髪のひと房でさえ残さずしゃぶり尽くす…、」
語尾は、汚らわしげに口元へ添えられた手の内に消えた。男は目元だけで笑いながら、ゆっくりと肩を竦める。
「これはこちらで引き取ります。そこの」
顎をしゃくった先は、顔色をなくした先遣の駐屯兵に向けてだ。ビクリと肩を跳ねさせる彼らを睥睨しながら、袖が余った腕を無造作に振る。
「連れて行きなさい。一先ずは駐屯の地下牢へ。手当ては必要ない。そこで我々の指示を待て」
「そいつをどうする」
淡々と問うリヴァイを振り向きもせず、優男が薄い肩を竦める。
「答える義務はありませんが」
「言えねぇようなことってか。お前ら何をコソコソやってやがる」
「口のきき方に気を付けろならず者が」
止まっていたギュルヴィの歩みが再開された。数歩先、もがくの頭を振り上げた踵が踏みつける。苦悶の絶叫に紛れて周囲がざわついた。靴裏をこすり付けるように動かしながらリヴァイを振り返り、視線を絡ませて微笑む。
「小汚いガキ一人に煩わされるこっちの身にもなって欲しいですよ。コンフューザさえ捕らえていればこんな苦労はなかったはずが、残ったのはこれだ」
これ、と言った辺りで、再度振り上がった足が少女に落ちる。彼女の代わりにその身柄を押さえつける兵士の肩が跳ねた。執拗に頭を踏みつけながら、屑が、と吐き捨てる。
「大人しく他の穀潰しどもと食われて来ればいいものをむざむざ生き残るなんて、ねぇ。始末に終えませんよ全く。…まぁ、私も良心が痛みますが残ったのなら仕方ない。こちらの希望としては知ってることを洗い浚い吐いて頂いて、その後は叛逆者の汚名を雪ぐとして王家に殉じて貰うのが妥当ですかね。年端もゆかない少女が死を以って国に尽くすならば粗方の醜聞も霧散しましょう。これで、あの不快極まりない一件も忘れられるというもの、」
「足を退けろ」
ギュルヴィが噴出した。片頬を歪に吊り上げて嘲笑する。
「お決まりの同情ですか? 美しいですね」
静まり返った一同の中で、鈍く、兵士長決まりの癖が響く。
「さっきも言ったろうが、…忠告だ」
どこに、そんな力があったか。
あまりの成り行きに僅か緩んだ拘束の隙をついてが飛び上がった。頭の上にあった脚を無事な左手で掴み、そのまま、驚愕に顔を染め抜いた男の喉笛に幼い口が喰らいついた。絶叫が迸る。目を剥いて取り乱した男が腕を振り回す。諸共に床に落ちた。首元から顔を上げたが腕を振り上げ、拳を歯形の血が滲む喉仏に叩き込む。再度悲鳴を上げた男に彼女が第二檄を繰り出す前、一閃、霞む速さで繰り出された手刀が細い頚部を捕らえた。吹き飛ぶ。少女の身体はそのまま壁に激突し、もんどりうって床に落ちた。
今度は、うめき声もない。代わりに襲われた男が甲高い声で何事かとやかましく叫んでいる。誰かがごくりと生唾を飲み込む。リヴァイが鼻を鳴らした。
「殺しちゃいねぇ。気絶しただけだろ」
「だ、大丈夫ですか!?」
「いいから先にそいつを抑えろ。起きたらまた喚くぞ」
いち早く我に返ったらしいペトラの呼びかけに平素通り返し、後はぞんざいに指示を出す。慌てて飛び出した数人がピクリともしないへ駆け寄り、やや警戒しながらうつぶせに伏した身を起こすと、細い四肢がだらりと垂れ下がった。完全に昏倒しているらしい。青褪め腫れた目蓋は閉じられ、うっすらと血に濡れている。ぶつかったときに額を切ったのか、僅かに流れる血は頬や顎先をも伝い、やがて、ひとつ、ふたつと床に落ちた。
白一色の病室に散る鮮血の跡を眺めやり、それから、リヴァイが首を巡らせた。向けられた視線の先、ギュルヴィ・レイは床に尻餅をついたまま悲鳴を上げ続けている。掛けていた眼鏡は吹き飛び、ばたつかせる足元に転がっている。いつもより劣る視界も相俟って、やや恐慌に陥っているらしい。首筋から垂れる血は僅かだが、拭っても拭っても消えない赤を見ては叫び、団服のあちこちにこすり付けている。しばらく眺めていたが、やがて、そちらに向かい進みだした。
「どうした、立てよクソ野郎」
耳慣れた靴音が高らかに響く。ついでのように眼鏡が踏み潰された。リヴァイに気づいたギュルヴィが口角泡を飛ばして叫ぶ。
「な、なにしてるおまえら、殺せ! 俺に噛み付いた! 血が、血がこ、こんなに! やっぱり人食いの気狂いなんだ、そのガキも一緒だ、はやく殺せ!!」
「何言ってやがる。連れて行くんだろ?」
間近まで歩み寄ったリヴァイの背に照明が当たり、しゃくりあげながら見上げたギュルヴィからは翳った彼の表情はよく伺えない。だが目だけが光る。それは闇の中で燈る光のように、動くたびに尾を引いて網膜に焼きつき残る。余韻は感情だ。そこに、消えぬ何かが燃えている。ひッ、とギュルヴィの喉が鳴る。
「小汚いガキに煩わされたくないんだろう。ほら連れて行けよ。都合よく寝てやがるぞ。勿論こっちは手を貸さん。お前の言うとおり管轄外だからな」
靴裏で磨り潰された硝子が鼓膜を擽る。くつ、とリヴァイの喉が鳴った。
「よく縛っとけよ。何しろ巨人どもを掻い潜って生き残ったガキだ。喩え手足を切り落としてもまた喉笛に食らいついてくる。…お前がくたばるまで、何度でもな」
「うぁぁあ、あ、ぁ、こ、こんあ、こんなことッ、よ、よくもこの俺に、俺に向かって! 軍務違反だからな、許さんからな貴様らァッ!」
振り上げた脚が霞む速さで落ちる。けたたましい音が石床を抉る。情けない悲鳴を上げてギュルヴィが頭を抱えた。
「俺は忠告した。外から生きて帰ってきたやつを舐めた結果だ」
もう聞こえていないのだろう。憲兵団員はうつぶせに背を丸めて縮こまったまま、それ以上はなにも返さなかった。唸るように短い悲鳴を繰り返し続けている。鼻を鳴らした後にさっさと視線を切り上げたリヴァイが首を巡らせた先、先立って突入してきた駐屯の兵士たちはあまりの光景に自失しているらしい。驚愕に目を剥いたまま、青褪めた顔でリヴァイ、ギュルヴィ、や室内を順繰りに見つめている。それにも鼻を鳴らし、改めて壁際の少女に焦点を合わせる。いつの間に駆け寄ったのか、調査兵団員により手際よく拘束されていくの傍に屈み込み、ペトラが首だけ振り返った。
「手当てはどうします? 頭を打ってるかも…、」
片手を油断なく少女の急所近くに副えての問いだ。薄い胸が確実に上下するのを見てから、兵士長は視線を切りあげた。
「死なれちゃかなわん。任せる」
「了解です」