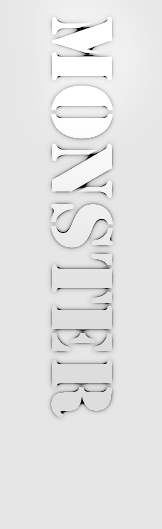MONSTER
26.思い出は何も語らない
眠り端から覚醒に至る課程はさながら呼吸に等しい。それは意識もせず、構えもせぬまま、するりと身に寄り添ってくる。
ふるえる瞼が自然に開く。途端、窓枠にはめ込まれたかのような鮮やかな青空が鋭く眼孔を貫いてきた。はしばらく、瞬きも忘れて蒼穹に見入っていた。鮮やかな、透き通るような青だ。雲ひとつない。ちちち、とあえかな鳴き声で鳥が飛ぶ。
しばらく、通るものの絶えた空を眺めていたが、やがてゆっくりと身を起こした。伸びを一つ。くぁ、とつられて欠伸もでる。短く不揃いな髪をかき回しながら、のろのろと寝台から降り、立ち上がった。見慣れたここは相変わらず代わり映えのしない兵団内の病棟である。壁内に帰還してから三日目の朝だった。
領土奪還作戦帰還後、生き残った民間兵は適当な宿舎や病棟へ押し込まれ、心身ともに手厚い看護を受けることになった。帰還を果たした人数は概ね当初の目論見通りの結果であり、その死線を越えてきたものに対する処遇はことさらに手厚い。家族のあるものは早々に退院し、身よりのないものは医師が太鼓判を押すまで療養し、あとは、それぞれあまり過酷ではない農地へ優先的に回されることになっている。の元へも既に似たような訓辞は届いている。出発はさらに三日後、東の山間部らしい。よくは見ていないため、詳しい地理はわからない。
もともと、傷らしい傷のない彼女は簡単な内診と手当てだけで好きに放置されていた。どちらかというと、精神面を慮ってくれているらしい。見慣れた看護婦の顔はひとつもないが、それに似た甘ったるい顔をした女が何人か、代わる代わる甲斐甲斐しく面倒を見てくれていた。不足はなく、むしろ快適だ。支給される食事も割合豪華なもので、思わず笑いそうになる。
戸籍の紛失も解決した。帰還兵、・ヨルムはこのまま肥沃な大地で農婦となる。そう考えると、途端胸に清涼な風が吹いたかのようになる。さて、と呟いて、彼女は寝巻きを脱ぎ、適当に用意されていた衣服へ着替えだした。木綿のワンピースは分厚く、ご丁寧に両腰にポケットまでついている結構な代物だ。飾りはなにもないが、このまま上着でも羽織れば、街に外出も可能だろう。鼻歌を歌いながら装備を確かめ、宛がわれた病室をでる。
時刻を確認すると、ちょうど今は昼時だ。病棟内が随分と忙しくなるころで、この隔離部屋は蚊帳の外になる。人気のない廊下をひたひたと進む。何度か角を曲がり、階段を上がって、静まり返る病棟一番奥、引き戸の前に立った。相変わらず人の気配はない。そっと戸を開けると、がらんどうに広い部屋が現れた。眩しい。差し込む日で白く光るようだ。調度品は少なく、寝台とチェスト、一人分の腰掛け椅子、水差しを置く滑車つきの台しかない。窓際近くにぽつんと備えられた寝台の上、カーテン越しに暖かい陽光が降り注いでいる。中央にはこんもりとした影がある。寝そべる人物は頭まで掛け布にくるまり、顔は見えない。
おはよう、とがいい、後ろ手に戸は閉められた。
「今日もいい天気。みて、雲雀が飛んでる。もうそんな季節かぁ」
いいながら、張り出し窓まで歩み寄り、閉じられていたカーテンを躊躇なく押し開く。途端、陽が更に強くなり、が眩しげに目を細めた。慣れるまで、しらじらと外を眺める。視線の先は穏やかな平野が広がり、ぽつりぽつりと線の細い木立が佇む。ちょうど、街どおりからは裏側に当たるらしい。
彼女の言葉通り、快晴はうっすらとみえる高い壁の方まで一面に広がり、めまいを覚えるような青だ。しばらく無心に眺めるに返答はない。やがて、彼女はほほえみながら振り返った。
「少し話でもする? 最後だし」
言うなり、彼女は部屋の端に所在なく置かれていた籐の椅子を引きずり、そのまま窓際へ運んでくる。よいしょ、と座り込むと、古びた椅子はわずかに軋んだ。ベッドまでは少し距離がある位置で、背もたれに沈み込みながらが小首を傾げる。
「こんな風にふたりで話すなんて久しぶりじゃない。言いたいことがあるなら聞くわよ」
返事はない。何処からとも鳴く、また鳥の声がこだまする。
「じゃあ、わたしが話そうか」
幼さの残る足をつい、と組む。
「話、そうだな…、まあ、こうしていざ話すとなると、確かになかなか話題って無いな。うーん…なにがいいかな、」
ガリガリ、と小さな指が乱暴にこめかみをかき回す。白い肌にうっすらと赤い筋が残ったあたりで、思えば、とが呟く。
「長かったわ」
組んでいた足を解き、前かがみになる。
「一年…、もっとか。あんたに付き合わされて。でもまさか、こんなことになるなんて思いもよらなかったわね。お互いに」
が立ち上がった。ついでのように、後ろ足で棟の椅子を蹴飛ばす。ガン、と乱暴に蹴られたにも拘らず、籐の椅子は軟らかく床に転がった。素材からして固い音は立ちにくい。
「そうね。話すことなんてない。わたしたち。今更よ、…"言葉は無意味だ"」
腰のポケットを探り、目当てのものを取り出した。手に馴染む金属の感触はひんやりと冷たい。小型の拳銃は撃鉄を起こすことによって安全装置が外れる。カチリ、と音が響いた。女子供の護身用に改良された、必要最低限以外の一切が省かれたオートマタイプだ。無骨なものが多い護身用銃では珍しく外観に気を配られ、美しいラインで構成されている。特にそれが気に入って手にしているわけではない。王都商会が徴収兵に向け適当に配った武器の中にこれがあり、たまたま自分が手にした、ただそれだけだ。
そう、それだけだ。だから撃った。乾いた音が室内に反響する。装填された弾は五つ。予備の弾は既に使いきっている。躊躇うことなく三発を叩き込んだ。盛り上がる人影に焦げた黒い穴が空く。硝煙が薄く上がった。火薬の臭いが鼻腔をつく、そこで初めて、衝撃が身体を貫いた。一足飛びに寝台に駆け寄り、上掛けを跳ね除ける。
口汚い罵りの言葉が幼い唇から飛び出した。現れたのは適当に巻かれたクッションだ。
そして、背後の扉が蹴り開けられた。
がらんどうだった室内が、俄かに人の気配に蹂躙されてゆく。やかましい足音と、言葉少なに飛ぶ声たち。そのどれもが手馴れている。が溜息を吐いた。
「あいつはどこ?」
空の寝台に目を落としたまま言う少女へむけ、コツ、と一歩、リヴァイが近づいた。
「そいつを寄越せ」
手を差し伸べた途端だ。パン、と乾いた破裂音が場を切り裂く。空の薬莢が硬い音を立てて床に落ちた。兆弾はない。白いシーツに空いた新たな焼け焦げの丸い穴を見据えたまま、が小さく首を傾げた。
「どこ?」
静まり返る室内に、平素と変わらない、少女じみた無垢な声音が響く。自身を取巻く複数の視線にもまるで意を返さず、片手で短銃を持て余しながら静かに佇んでいる。じり、とリヴァイの背後に控える兵士数名が呼気を合わせだした。俄かに場が張り詰める。呼吸すら憚られるような室内で、先頭に立つ兵士長が口を開く。
「会ってどうする」
がふと笑った。
「関係ないでしょ」
「大有りだ馬鹿が」
「馬鹿?」
が目を上げ、リヴァイを振り返る。
「確かにそうかも。まさか出し抜かれるなんてね」
ふふ、と微笑む少女の顔は以前となんら変わりない。線の細い華奢な四肢に小さな顔、短い黒髪がまばゆく差し込む斜光により白く縁取られている。虫も殺せなさそうな細い指が慣れた様子で檄鉄を弄びながら、ねえ、と小首をかしげてみせた。
「だけど別に、関係はないでしょ。これはわたしと、あいつの問題。そもそも何しにきたの? こんなに大勢で、あいつのお守り?」
「何が目的だ」
「無視か。ひどくない?」
軽やかな笑い声を上げながら、翻る腕がまっすぐにリヴァイを射す。握られた短銃の銃口が黒くぽっかりと穴を開けている。居並ぶ全員が低く身を沈めてまさに飛びかかろうとした途端、リヴァイが無造作に片手を挙げた。
「兵長!」
ペトラが叫ぶ。それには答えず、リヴァイが微笑むを見る。
「死んだ」
が再び首を傾げる。口元は笑んだまま瞬きをやめた彼女を見返して、掲げた腕を下ろし、リヴァイがの背後、天井に程近い採光窓に向け顎をしゃくる。
「奪還作戦が終了した日、つまり、俺らやお前が帰還したその日だ。そこの窓で首を括ってやがった」
一瞬、の瞳が泳いだ。隙なくそれを見つめながら、リヴァイが一歩を踏み出す。
「ご丁寧に遺書もあったぞ。いかにも聖職者らしいクソみてぇな内容でな、口にすんのも虫唾が走る。これがお前の望んだことか?」
平坦なリヴァイの言葉に、は微笑んだまま答えない。コツ、と軍靴が鳴る。背後に控える調査兵団一同が固唾を呑んで見守る中、ついに間合いに入った。このまま一足飛びで相手をねじ伏せるのも容易だ。本人もそのつもりだろう、一気に呼気を整える姿勢に入った。しかしその途端、銃を構えるの腕が震えた。肩を揺らし、身体を折る。そして、けたたましい哄笑がはじけた。
「あの、馬鹿! 死んだの! 今更!」
きゃはは、と甲高い笑い声を立てながら、先ほどリヴァイが指し示した採光窓を見上げる。笑いすぎて涙のにじんだ目じりを撫でながら後ずさる。収まらない爆笑に噎せ、咳き込みながら、しかし油断なくリヴァイの間合いから抜け出した。だが所詮室内、後退しきった先は分厚い壁際だ。寝台横。染みのない白壁に背を預け、空を見る。はぁ、と笑い損ねたらしい吐息が小さな口から漏れ出でた。言葉もない居並ぶ班員を顧みもせず、握り締めた銃を弄ぶ。なぁんだ、と呟いた。
「つまんな…、そう、死んだの。はぁ、ムカつくなぁまじ無駄足じゃん。自殺って…ほんっと、今更」
ため息と共に吐き出し、ち、と仕舞いに舌を打つ。銃を持つ手でガリガリと乱暴に頭を掻きながら、あらぬほうを睨んだ。まもなくして、言葉もなく立ち竦む面々へ向き直った。
「まあ、そういうことなら仕方ないし、あきらめる。騒がしくしてごめんなさい」
軽く言って頭を下げる彼女に、今度リヴァイが笑う番だった。薄く口端を吊り上げ、細めた瞳が鈍く光る。
「それで済む話か?」
「死んだんだったらどうしようもないじゃん。あ、コレ? 渡そうか? もう必要ないし」
コレ、といって掲げて見せたのは先ほどから雑に握っていた小銃である。慣れた手つきで引き金を指で回転させ、銃把側を無造作に差し出してみせる。途端、リヴァイが動いた。瞬きひとつで距離を詰め、の手から銃身を叩き落とす。カーン、と甲高い音を立てながら床で跳ねたそれは回転しながら背後へ滑った。控えていた兵団員が素早くそれを拾った。が目でその動きを追いながら、やがて笑う。
「普通に取ればいいのに」
「おいクソガキ、」
振るった拳はそのままの胸倉を掴むのに翻った。身長差から自然見下ろしながら、木綿の服をちぎらんばかりに握る。
「随分態度が違うじゃねぇか…それが手前の本性か」
「知らない大人に囲まれたら猫ぐらい被るでしょ、誰だって」
「お前が黒幕だな」
「黒幕?」
ゲホ、と咽ながら笑いを収めないが繰り返す。ゆっくりと息を吸い、唇を舐めた。
「何の話かわかんない」
ガッと米神に拳が飛んだ。手加減はされている。しかし枯れ木のような身体は掴まれた胸倉すら振りほどく勢いで地に伏した。振るった拳を解き、振りながら、転がる少女を睨みおろす。
「真面目に話せ。何が目的だ」
抑揚のない静かな声、傍目には暴力といって差し支えのない光景に居並ぶ面々が息を呑む。静まり返る室内で、しかし思いのほか気安くが半身を起こした。薄く口端を吊り上げている。
「目的といわれても、」
膝をすり合わせて立ち上がり、適当にほこりを払う。消えない笑みを浮かべつつ、が小首をかしげる。
「別に何も。会おうと思ってた奴が死んでたってだけのはなし」
「殺すつもりだったか」
「そうよ」
間髪いれずの回答にリヴァイの目が細められる。睥睨された小さな肩が上下する。
「でも死んでた。わたしがどうこうする前にね。まぁつまり、未遂ってこと。ならわたしが咎められるべきはこの騒ぎに対してだけ。で、さっき謝ったし、この話は終わりでしょ」
そう言って肩を竦め、少女はリヴァイの視線から身を翻した。緊迫する面々が身を固くするのもかまわず、気安い仕草で自分が穴を開けた寝台へ指を這わせる。くるりと軽やかに一回転し、顔を引き攣らせる全員をなめらかに見渡した。そして微笑む。いつもどおりの、可憐な少女らしい仕草で。リヴァイが鼻を鳴らした。を掴んでいた手を軽く振り、見えない埃を払うかのようだ。
「手前の理屈だけが通じると思うか? いいか、聞かれたことにだけ答えろ。場合によっちゃ相応に痛めつけてやる」
再び、少女の軽やかな笑い声が上がった。くすくすとさえずりながら、細い指で唇を撫でる。
「するの? そんなこと。ほんとに? よしたほうが賢明よ」
少女は笑いながら、額に落ちかかる短い前髪を無造作に持ち上げた。手串で整えながら、得体の知れない不気味さに沈黙を強いられる兵団一同を鼻を鳴らしながら見回す。順に顔を伺い、最後、リヴァイを見た。色の似た、しかし明らかに差異のある瞳同士が同じ視線でぶつかり合う。
「あなたたちは文字も読めないぼんくらなわけ? 領土奪還作戦から帰還すれば英雄となる、そう王命が下された。わたしは立派な帰還兵よ年齢なんて関係ない、今後に於いては肥沃な農村で兵役を免除され生産者としての安穏が約束されている。わかる? これはシーナ王都民に勝るとも劣らない特権よ。覆せるのは王だけ。ましてや軍人なんか、」
「ルカを殺したのもお前か」
遮り、やや断ずるように言い放たれた言葉に再び場に沈黙が落ちた。シンと静まり返る室内に、リヴァイの背後に控える兵士たちの顔色は優れない。目だけが先頭に佇む兵士長を見る。どうやら、初耳だったらしい。漣のように小さなささやきが断片的に交わされる。ルカ、あの金髪の、殉死した、と聞こえたあたりで、口を噤んでいたが再び唇を開く。
「あの人の怪我は巨人にやられた。わたしは関係ないわ」
「そうか」
言うなり、リヴァイが無造作に腕を振る。何かを投げつけられたらしいと見てが半歩退くが、それはキィン、と高い音を立ててはね、後退した彼女の足元まですべる。回転が止まり、見やれば、ひしゃげた金属片である。何か硬いものに押しつぶされたらしく先端の丸みを残し圧縮された部分が波打っている。よくよく見なくてもわかる、銃弾だ。
「あいつは複雑な身の上でな。どう死んでも共同墓地に埋葬することすら許されない。巨人に食われでもしない限り、死体は頭の天辺から爪先まで王都の変人どもに好きに弄くられて捨てられる。それが仇になったな。こいつが心臓に一発」
転がった銃弾の残骸を見下ろすの瞳から瞬きが絶えた。だが口元は微笑んだままだ。リヴァイが続ける。
「お前の言うとおり、帰還後の民間兵は数日中に地方へ送られる。だが、犯罪者となりゃはなしは別だ。ガキとはいえ軍人殺しの罪は重いぞ」
軍人殺し、との言葉あたりで、背後に控える調査兵団諸氏の目つきが変わった。明らかな敵意をちらつかせながら、いつの間にか僅かに俯く少女を睨む。広くもないが狭くもない個室の中、俄かに膨らんでゆく気配に目配せをしながら、リヴァイが肩を竦めた。気安い仕草だが、動きは硬い。同じ温度で冷たく光る目で、の旋毛を見下ろした。
「まぁ、なんだ。死にたくなきゃ喋れ」
抑揚のない声がそういい、ついで、腕が伸びる。もぐりこむ様にして再び少女の胸倉が掴まれた。無理やりに上を向かされたは瞳を閉じている。いつぞやと変わりない、まだ輪郭もあどけない少女の相貌。肌にはくすみひとつ、傷ひとつない。ぐ、とリヴァイの拳に力が入る。すると、伏せられていた瞳が花開くように瞬いた。青白く透き通った白目の中、リヴァイを見返す瞳だけが黒い。見覚えのある目だ、と彼が思ううち、零れ落ちそうなほど大きい目淵がゆっくりと弧を描く。
つと動いた人差し指が目の下を引く。そして、桃色の舌が群衆に向け突き出された。