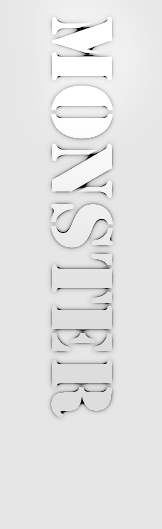MONSTER
25.友だちをみんな殺してきた、だから死に値するのさ
遠く、雷鳴が静かに室内を揺らしている。締め切った窓越しにも、黒く渦を巻く雨雲が肥大し、雷雨を孕みながら渦を巻いてゆくのがわかる。そう遠くないうちに、空を割るような豪雨が領土一帯を襲うだろう。今はまだ音だけが、呼吸すら微細に鼓膜を叩く締め切った室内を漂ってゆく。
トン、トン、と規則正しい拍子で爪先が椅子の縁を叩く。座りはせず佇んだまま、粗末な背もたれに手をかけ、まるで鼓動のように指を動かしている。視線の先は固定され、微動だにしない。気配は二つ、室内の端と端で固定されている。やがて、かすかな吐息が漏れた。
「お前、本当は話せるんじゃないのか」
明かりを消し、月明かりすら遮断した室内には相手を気取らせる光源はない。にもかかわらず、どこかしらから漏れはいる光が徐々に目を慣れさせてゆく。塗りこめるようだった闇の中、やがておおよその輪郭が浮かび上がってきた。少ない調度品の角と角を結んだ先、壁際に寄せられた寝台の上で、人影が身を起こしている。俯いているのか、猫背がちの陰影は子供のように小さい。呼吸の度に僅かな身じろぎを繰り返し、刈り取られた髪がむなしく震えている。
問いに対する返事はない。急かすつもりもなく待つ所為で、無音の隙間を遠雷がぬぐってゆく。腹の底を撫で、首の後ろを逆立てさせる低い音がいよいよ近くなったとき、突如目を焼く白い光が迸った。一瞬の閃光は人ものから色を奪う。白黒の苛烈な光彩に浮かび上がった人影と、目が合った。落ち窪んでぎょろついた眼球が半ば飛び出しかけているその中、まるで点のように稲光とは違う光がある。あの奇岩の中、儚く燃えていた松明のように、辛うじて生き抜いた知性の火だ。
「――話せないさ、」
何も、と錆びた金属が引きつるような声が落ちた。声帯に異常があるもの独特の声だ。遅れて雷音が轟く。音源は近い。落雷になる勢いの、腹の底を探られるような重低音だ。トン、とまた爪先が動いた。
「何故」
「そう言われている」
「誰に」
「わからないのか」
ク、と喉を詰まらせ肩が小さく揺れる。どうやら笑ったらしい。その嘲笑は長く続かず、場にはまた沈黙が戻る。規則正しい指の動きに合わせた硬い音が、時計の秒針代わりに響く。針が有に二週したあたりで、指の動きが変化した。ひとつ、ひときわ強く指先が打ち込まれる。
「カルノ・コンフューザはお前か?」
返事はない。今度はこちらが笑う番だった。口端が引き攣るに連れ、乾燥した唇が僅かに痛む。
「沈黙は雄弁だな。つくづくわけのわからん連中だ。お前がイカれた集団の大将なら何故気が違った振りをする」
「帰ってくれ」
語尾に被せるようにして、寝台の上の男が言った。潰れた喉で絞り出す声の調子が変わった。見る間に、丸めた背が小刻みに震えだす。頼む、と怯えた固い声が絞り出た。
「俺は違う、違う、違うんだ、頼む、帰ってくれ、違う」
「何が」
「わからないのか!?」
絶叫と同時に、再び稲光が破裂する。音はほぼ同時だった。明滅する視界の中、男が咽び泣いている。ゴォン、と余韻の木霊する室内に、堪え切れない嗚咽が漏れ出した。痩せた手が頭を掻き毟り、爪を立てて擦る。
「わからない、わからないんだみんな、みんな、あ、あん…、あんな、あんな事にな、なるなんて、俺は違う、いやだ、もう厭だ、あんな、いやだいやだいやだいやだいやだいやだい」
「おい」
一瞬で間合いを詰め、ブチブチと肉ごと髪を引き抜く手を止めさせる。乾いた手は先ほどまで触れていた木枠と変わりない感触だ。その手が、渾身の力でこちらの手を握り返してきた。間近で見る血走った目からつう、と雫が落ちる。
「どうして出した」
震えた声が責める。ぎり、と握られた腕に爪先が食い込み、厭な音を立てる。
「あれは悪魔だ。どうして出したんだ。あれは、あいつは、あそこで…、俺は死ぬ、殺される、こ、今度こそ、どうして、どうしてどうしてどうしてどうして!」
両手で掴みかかり、口角泡を飛ばす相手を白々と見返してから、ひとつ、横面を叩く。軽くいなしたつもりだったが、弱りきった体には鉄拳に近かったらしい。痩せぎすの男がもんどりうって倒れ伏す。ギィ、と軋む寝台の上、荒い呼吸と嗚咽を繰り返す男を見下ろしながら、掴まれた袖口を慎重に払う。
「騒ぐな。言いたいことがあるなら順に話せ、手短にな」
返答はない。また、閃光が室内に瞬く。ゴロロ、と唸りをあげる残響と相俟って、男の啜り泣きが物悲しくひびく。小刻みに震える身体とひれ伏した体勢が宛ら女か、幼子のようだ。常であれば失笑ものだが、今はとにかく不気味に尽きた。大の男が得体の知れないものに怯え、咽び、許しを乞うている。大袈裟な、と切って捨てるにはあまりにも惨い、それだけ正気と狂気の瀬戸際で何かと戦っているものの姿だった。
しばらく、遠雷と嗚咽だけが続く。言葉のないまま、分厚い雨雲が落ち着くのを待った。やがて、歯を食いしばって悲鳴を押し殺していた男が不規則に息を吸った。引き攣る肺に咽ながら、帰ってくれ、と歯の根の合わない声が続く。
「俺は、し、死にたくない、死にたくない厭なんだもう、やっと出れた、あ、あいつがいなくなる、いなくなるのに、も、も戻ってくる、どうして…」
「戻る?」
「どうして…、どうしてだ…、か、帰って…かえってくれ…、」
後は、鸚鵡のように帰れ、帰れと繰り返すだけになった。暫く静観していたが、落ち着く様子はない。チ、と舌を打つこちらの仕草にすら男はか細い悲鳴を上げ、必死で腕を掲げ己の身を庇った。まるで無力なその様子に深い嘲りと疲れがこみ上げてくる。ここまでか、と見切ると同時に、重い吐息が落ちた。行軍前の無理を押して出張ってみて、収穫らしい収穫はこの男が後ろ暗い組織の宗主だった、その確信だけだ。とはいえこの有様では一連の不可解な事象の真相には迫れそうもない。無駄骨か、そうごちりながら身を翻す。そのまま去りかけたが、ふと肩越しに振り返り、いまだ赤ん坊のように四肢を丸め蹲る男を見下ろした。
「おい、聞いてやしねぇだろうがな、一応忠告しておくぞ」
返事はない。歯の隙間から頭の痛くなる悲鳴だけが漏れ聞こえている。
「この作戦が終わり次第、お前は憲兵団に引き渡す。その後どうなるかは知ったこっちゃねぇが、それ相応の審議にかけられるのは避けられんだろ。どの道、運が悪けりゃお前は死ぬ。そこで怯えようが寝てようが、それは変わらんぞ」
言葉も泣くさめざめと泣き続ける男に、やり場のない怒りがこみ上げる。何を泣く、と怒鳴りたくなる胎を硬く押し込めて、ただひとつ、派手に舌を打つ。
「泣いて後悔するならいっそ死んで詫びろ。お前ら気狂いどもが玩具にした連中にな」
言い捨て、今度こそ踵を返す。ゴロロ、とまた威嚇のような雷鳴が燻る室内を、雨夜の深夜を慮り足音を殺しながら進む。その背を、泣き声交じりの男の声が追いかけてきた。
「神よ、神よ、ゆ、ゆる許し給え…、神よ、かみ、かみ、か、か、神など……、…戻ってくる。戻ってくる。言い切った、言い切ったんだ…あいつは悪魔だ、悪魔、悪魔、悪魔、生き残る、戻ってくる、みんな、」
みんな殺して、生き残る。
視界さえ遮る勢いの驟雨をもって、人類史上最大人員を投入した領土奪還作戦は終幕を迎えた。総員数二十万を越す市民のうち、無事に生還を果たしたものは百数名だけである。なお、この内には尖兵の欠損率は含まれていない。
一夜明けてから、亡骸を持ち帰られた兵士はおのおのの遺族の下へ無事に届けられた。壁外調査のたびに繰り返される多種多様な罵詈雑言の飛ぶ通過儀礼だが、この時ばかりは静かに、波風もなく終了する。本作戦への疑義はそれ即ち王政批判となる。それを、身を以って体験したものの口は重く、固い。
兵士には孤児も多い。引き取り手や身寄りのないものは纏めて荼毘に伏された後、兵団が管理する共同墓地へ葬られる決まりだ。火葬当日は薄い雲間から時折陽の差す、蒸し暑い日だった。ここしばらく降っては止みを繰り返していた雨が懸念されていたが、幸いにして一滴も洩らすことなく雲は薄れていった。未だ混乱が尾を引く市井での準備は遅々として進まず、ふと気づけば夜半である。見上げれば澄み切った空に無数の星が瞬いている下、葬送も兼ねた苛烈な火柱の前、それぞれが思い思いの別離を告げている。黒煙に混じり、人骨と肉の焼け焦げる咽る臭いが鼻をつく。何度嗅いでもなれない臭いだ。夜闇を押し上げる炎の先、舞い散る消し炭を眺めていたリヴァイの元へ、ネスがやってきた。くしゃくしゃのバンダナを手でもてあましながら、小さく頭を下げる。
「最後まで無愛想な奴でしたよ。俺に一言の断りもなくいっちまいやがって。あれだけ面倒見てやったっつーのに」
ふん、と鼻を鳴らし、またすする。リヴァイは特に答えず、ちら、と相手を見た後、再び視線を火柱へ戻した。返事がないことを特に気にした風もないネスは握ったままのバンダナを更に乱暴に丸め込む。
「あの見てくれですからね、早いとこ嫁さんでも貰えっちまえばよかったんですよ。何度か勧めはしましたが、のらくらかわしやがって。守るものでもありゃあ、ちょっとは違ったンでしょうが。あいつは常に、いつどのタイミングで死ぬべきかを考えてる奴でした。索敵に所属したのも結局はそこからきてる。事実、優秀でした」
「うまく隠してたな。お前の所にあんな輩がいるなんぞ、俺の耳には入ってこなかった」
「そりゃあ、兵長の耳に入っちまったらすぐどこぞへ取られちまうでしょう。ただでさえこっちゃあ人が足りないってのに」
「あのクソ馬鹿のお守りは多いほうがいい。奴はさぞ適任だったろう」
「でしょう? ホラ、やっぱ俺の読みは正しかったっつーことです」
低く笑い、ネスが散切りの頭を乱暴に掻く。赤く腫れた目を瞬かせながら、リヴァイの視線を追った。いまだ燃え尽きる気配のない火焔がごうごうと星を焼いている。
「これが、あいつなりに最善の結果なんでしょう。ガキ一人助けることに何の意味があるのか、俺にはわかりません。ただあいつには大儀が有った。手前の使いどころを見極めきった、軍属らしい合理的な判断の結果がこれだ。俺は、あいつのそんな考え方を変えてやりたかった。名に縛られて生きるなんてつまんねぇって、言ってやりたかったです。それが悔しくてなりません。兵長、」
リヴァイの視線が返るのを待ってから、ネスが続ける。
「あいつは最期に何かいいましたか」
火柱の赤が映え、はしばみ色の瞳が夕陽のようにじくり、と燃え盛っている。顎を引く所為か、割合彫りの深い顔に群青色の陰が溜まる。その中でも、目だけが光るようだ。覚えのあるその光を孕んだ目を見つめながら、リヴァイはしばし沈黙した。
ややあって、何も、とリヴァイが答えた。こちらを探るようなネスの目をさらに鋭い眼光が捕らえる。
「意味のある言葉じゃなかった。ましてや、お前宛ての遺言なんか聞いちゃいない」
取り付く島のない言いようできっぱりと断じ、あとは、再び同じ視線を返すだけである。だが、相手はそれで満足したらしい。目を瞬かせ、そうですか、と相好を崩した。
「それならいいんです。いや、変なことを訊いちまいました。すんません」
「いや…、」
リヴァイが返し、そのまま、お互いがお互いにあらぬほうを見やる。どこかしらから、女の咽び泣く声が響いてくる。燃え盛る熱波と焼材の焼け落ちる音とが重なり合い、まるで、いつかの落日を想起させる。ここからもうひとつ向こう側の地で、巨人に蹂躙された日も、血を溢したような黄昏だった。死に物狂いで持ち帰った仲間の死体を焼いたのも、まるで同じような火柱だ。その前も、そのまた前も、繰り返し繰り返し、今までもこれからも途切れることなく繰り返される光景がこれだ。
「ネス」
リヴァイが呼べば、いくらか老け込んだ馴染みの顔が静かにこちらを向く。
「あいつが助けたガキはどうしてる」
「ああ…、他の生き残りと一緒くたに駐屯の兵舎へ入りましたよ」
「人数は」
「見た感じ全員で百かそこらくらいでしょう。怪我人の対応にてんやわんやで、うちの医務員も何人か借り出されてるようです。まあ、あのお嬢ちゃんは殆ど怪我らしい怪我もないってんで早々に引っ込んだみたいでしたが…それが?」
「いや、いい」
ひとつ頷いて返し、リヴァイが組んでいた腕を解いた。炊き上がる火柱に僅かだけ目礼して、ネスに向け顎をしゃくった。
「確認したいことがある。動ける奴だけ二、三人連れてついて来い」