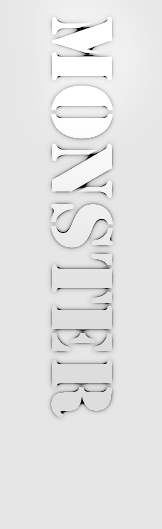MONSTER
24.雨が声を掻き消しても
ゆっくりと、団子状の人影が宙に舞う。
一瞬、重力に逆らうかのように浮いた。しかし当たり前だがそれは錯覚で、瞬きする間にまっさかさまに落ちてゆく。その先、異形の群れが一心不乱に指を伸ばしているのが見えた。
はるか下方からルカの怒号とも取れる断末魔が響き渡り、この高い時計塔を駆け上がってきた。果敢にも暗器のなにかを抜いたようだが、やがて、それも見えなくなる。一緒に落ちた男は頭から食われるのが見えた。四肢には別の巨人がそれぞれ食いついている。他も似たり寄ったりだ。
再び、厭な音を立てて塔が軋んだ。揺れも強くなってきた。思わず見上げた先、はめ込まれた文字盤の皹が大きく広がってゆく。ぱらぱらと細かなくずが頭上に落ちかかるのを払いながら再び下を覗き込むも、もうルカや他数名の姿は見えなかった。血の臭いに誘われたのか、数多の巨人が押し合いへし合い、階下へ集まってきている。すさまじい数だ。通常の脱出は万に一つも不可能だろう。見下ろす先、姿かたちに差こそあれ、むき出しの歯茎と血走った目をこちらに向け、雄たけびとも地団駄ともつかない金切り声を上げている。体の内側を擦られているような絶叫が広場内を埋め尽くしてゆく。
「きも」
凡そ場にふさわしくない声でいうなり、が片方の口端だけを吊り上げた。押し寄せる巨人の群れが円柱状の時計塔を取り囲む。きしむ床を足裏から感じながら、屈みこんだ。足元には、先ほどまでルカが身に着けていた銃具の一切がある。これは三兵団共通の装備だ。使い方は既に把握している。
先ほど奪った弾を取り出した。種類により色が違う。残る色は三色だ。もとより、今回はこれしか支給されていないのだろう。緑と紫と黄色。緑が進行方向を示す為で、紫が緊急事態、黄色が作戦遂行が不可能なときをそれぞれ示す為だという。細い指は紫をとった。
脇を絞め二の腕で鼓膜を押さえ、迷うことなく撃った。反動は思ったよりも大きいが倒れるほどでもない。痩せぎすの子供の体でも何とか踏みとどまれる。しびれた腕を下ろし、銃を投げ捨て、空を見た。煙幕は黒がかった汚い紫だ。丸みを帯びた、明らかに硝煙とは異なる類のそれが曇天をまっすぐに貫いている。
ふう、と息を吐き、がその場に座り込んだ。足場を腰掛に膝を抱え、暮れ行く街並みを改めて眺める。遠巻きに見れば、光の少ない街並みは凡そ物悲しく、侘しい。音さえなければただの黄昏時の風景だ。耳を打つ倒壊の音、立ち上る砂埃の臭い、巨人の歓声と食い散らかされる人々の悲鳴が遠く木霊する。ありとあらゆるところで、無意味な言葉が渦巻いている。
悲鳴は余計に敵を呼びよせる。やめろなどといったところで、それを聞くような相手ではない。懇願も命乞いも決して聞き入れてはくれない。それが巨人だ。言葉は無意味だ。
「だが、」
の唇が無造作に動く。意味がないと謳うこの言葉には、続きがある。ルカ・ティランには断片的に伝えていたな、と思う傍ら、いつぞや、何度も何度も耳にした言葉が甦り、口をついて出たが、間近で躍り上がる瓦礫の音にかき消された。温く吹く風の湿り気が先ほどよりも強くなっている。舐める舌のようにして、むき出しの耳たぶから首筋を風が這ってゆく。先ほどまでは人いきれで狭かったせいか感じなかったが、今は誰もいない分、少し肌寒い。伸びかけの髪が弄ばれるまま、日の沈む方角を見る、そのときだった。
ガァンッ、と派手な音があがった。身体すれすれを掠めとんだそれは後方の時計盤に激突する。胸元に手を当てながらのけぞるの前で、すさまじいワイヤの巻き返し音が轟く。血にまみれたそれが巻き切った時、現れたのは先ほど消えた男だった。
「…動くな、」
肩で息を吐きながら、搾り出すようにルカがいった。齧られたのか、頭皮の一部が剥がれ落ち、顎先まで赤く染まっている。血が入ったらしい右目をやや引きつらせながらながらも、迷いなくこちらを見下ろしている。わぁ、とが声を上げた。
「すごい、生きてるなんて。さすが調査兵団」
「黙れ」
「でも、残念。時間の問題ね。その怪我じゃ」
それ、と指差す先。ルカの右足は膝から下が欠損していた。先ほど折った方だ。狙ったのか、たまたまか、無理やりねじりきられたらしい。捻られた傷口からの出血は多くないものの、むき出しの筋と骨が覗いている。派手な色だ。脂肪の白いぶつぶつとした突起と、筋肉らしい千切れた繊維が複雑に絡み合っている。わき腹や肩口などの柔らかいところは大方食いつかれたらしく、肉が抉られはみ出す凄惨な有様だった。
やがて、耐え切れなくなったか、ルカがその場にへたり込んだ。だが目だけはしっかりとを捕らえている。血の気の失せた顔の中で欄と燃える視線だけが生き物じみている。
「…お前と俺、どの道死ぬさ。ここにいればな」
搾り出した言葉にが小首を傾げた。
「そう?」
「他の兵士を待ってるなら、生憎だが、ここにはこない。兵団の作戦ポイントから外れている。あの煙弾は確かに非常時用だが、撃ち方に特有のコツがある。それがなければ誤射と看做される。望みの迎えは、来ない」
「へえ」
「じき、ここも崩れる。俺が死ぬ前か、後で。そうなりたくないだろ、」
「だから?」
「着いて来い」
膝を突いたままルカがいった。が薄く目を細める。荒い息を繰り返しながら生唾を飲み込み、そのまま、ルカは装備を確かめだした。逡巡の後、刃を捨てる。時間が惜しいのか、複雑な留め具をはずすことなく切断し、立体機動に必要な分以外の腿のベルトも取り払う。変わりに、豚皮をなめしたそれを止血帯よろしく傷口にまきつける。片側を歯で食いしばり、ぐいと引き絞った。くぐもったうめき声が漏れる。
やがて、整ったらしい。下から掬うような目線がに戻ってきた。
「…手を貸せ」
少女は答えず、底の知れない顔で白々とルカをみる。黙る彼女に痺れを切らしたのか、血にまみれた腕を一本、突き出して寄越してきた。
「時間がないんだ。早くしてくれ」
「…わたしを助けるってこと?」
「違う。突き出すんだ」
伸ばした腕の先、開かれた五指の間から睨み合う視線が絡む。塔の振動がいっそう強くなってきた。咆哮をあげる大小の巨人が崩れかける支柱に激突する。頭上へ落ちかかる瓦礫の破片も一回り大きくなった。ルカが血まみれの唇を舐める。
「お前ら、得体の知れない連中を調べるのが、俺の任務だった。死人が出た理由は君だった。なら、君を、突き出さなきゃならない。子供でも、どういう事情があるにせよだ。だから、」
痙攣を始めた指を引き絞るように突っ張り、血まみれの男が言う。
「連れてゆく」
無言のままだったがふと、片方の口角を吊り上げた。かさついたつぼみのような唇がいびつにゆがむ。嘲笑を帯びた少女の視線が、青年から失われた脚の痕を殊更に撫でてゆく。
「…どうやって?」
ガチャリ、とルカが握るトリガーが鳴った。両手で握り締め、反応を確かめる。訓練時代からの変わらぬ装備だ。何度も整備した。血で滑ろうとも、指がもげそうでも、この感触は変わらない。アンカーは飛び出す。ワイヤは巻き上がる。ガスの噴出も侭なる。全てこのグリップで操る。そう、腕だ。腕さえ無事ならば問題ない。
「腕さえあれば、俺はまだ飛べる」
突如、時計塔の屋根が一部崩れた。下からの衝撃に耐えかねたらしい。大きさは差ほどだが重量のあるそれが二人の頭上に落ちかかると同時に、少女が青年の手を取った。
折れそうなほど小さな手が血まみれの指先に触れた途端、ルカがその手を掴んで引く。四肢の欠損を感じさせない素早い動きで彼女を負ぶさるなり、勢いよくトリガーを引き絞る。矢尻よろしく射出されるワイヤを追いかけるようなすさまじいガスの噴出でもって、崩落する時計塔を脱出する。二人が宙に投げ出されたと同じくして、十二を刻む文字盤に亀裂が走る。縦横に走りきったところで、屋根もろとも瓦解した。つなぎ目のもろい煉瓦層が滝のように、ふもとで群がる巨人の頭上へ落ちかかってゆく。
一度宙に高く舞い上がりきってから、ルカはアンカーの第二檄を繰り出した。狙うは少し下方にある建屋の屋根だ。庇に当たり派手な音が上がる。重力に従うまま二つの影は放物線を描き、やがて再び空に浮く。かつての象徴が崩壊しきる僅かの間に、この跳躍は三度を繰り返した。
広場を抜けきり、比較的富裕層が住まう住宅街へ移った。資材がふんだんな分頑強な建屋は高さも有り、巨人の手も届きにくい。ひときわ長い直線の屋根が続くあたりに差し掛かった途端、ルカの体勢が崩れた。血を失いすぎたらしい。着地もままならずに肩口から落ち、ワイヤの巻き戻しに引きずられる。とっさにを投げ捨てるようにして突き飛ばし、トリガーを突きたて衝撃を逃がす。ぎりぎり落下は免れたが、伏せたまま起き上がることが出来ない。屋根瓦に夥しい血だまりが転々と尾を引く。
「いったたた…、」
顔をしかめて呟きながら、が膝を払いつつ、立ち上がった。すりむいたらしい右手の側面を撫で摩り、依然呻きながら蹲るルカを見る。しばらく無言で眺めていたが、やがて、近寄ってゆく。硝煙が棚引く辺りを見回し、ひゅう、と掠れた口笛を吹いた。
「あっという間にこんなトコまでとは。さすが、聞きしに勝る立体起動。まるで空でも飛んでるみたい。あなたたちのご大層な紋章が翼なのもわかるわ」
ルカが咳き込んだ。血痰が飛び散る。肩で息をする彼の傍らに立ち、見下ろすの頭上で、低く、唸るような遠雷が鳴り響く。いつの間にか雨雲が肥大し、今にも零れ落ちそうなほど重い。ふと、苦しげな咳の合間に低い忍び笑いが漏れてきた。が幼い片眉を上げ、振り返る。
「なにかおかしい?」
「…饒舌だな、」
ぐぐ、と肘で上体を持ち上げ、そのまま勢いづけて半身を立て直す。こらえかねた悲鳴が食いしばる歯の隙間から漏れた。荒い息を繰り返しつつも、口端を曲げる。
「そんなに話すとは、思わなかった。舌っ足らずの、少し知恵の足りない子だと」
見下ろしながら、も微笑み返す。
「そういうのが好き?」
「まさか」
「あっそ。まあわたしも加減がわからなかったのよ。確かにあれだけ馬鹿みたいな散歩に出たけど、きちんと話すのははじめてね。あなたは無口でよかったわ」
「そうか」
「いっそこのまま永遠に黙ってほしいくらい」
色素の異なる瞳同士が錯綜する。やがて、ルカがひときわ深く息を吐いた。噛み痕だらけの腕を取り上げ、全体重をかける構えを取った。
「自分の残体力くらい、わかるさ。この騒ぎだ、兵団の連中もじき集まる。そこまで、君を連れて行くのが、俺の限界だ。精々祈るといい。なるべく早く、そうなるように」
「冷静ね」
「お互い様だ」
「そう?」
「…ふ、」
ふふ、とルカが再びくぐもった笑い声を洩らす。ほぼ、うめき声と変わらないそれを、が静かに微笑みながら見下ろしている。まるで愛でるかのような視線を見返しながら、ルカが震撼に侵され始めた指をきつく握りなおした。短い爪がそれでも刺さる。吐く息に熱が篭る。しかし身体は冷えてゆく。幼さの残る目淵に睫の影が揺れるのを恃みに、焦点を結ぶ。浮かび上がるもはや見慣れた少女の目鼻立ちに、またひとつ、ルカから笑いが落ちた。既に頭や胸から驚愕は去った。今、残るのは奇妙な納得と、充足だった。こみ上げる血に噎せながら、兵士が細く長い息を吐く。
「ずっと、君を、見ていろと。そう、正しい…、それが正しかった。俺は、見破れなかったけど、」
前後不覚の言葉に、が笑んだまま小首を傾げる。
「何の話?」
「…いや、いい」
屋根瓦を蹴りつけ、腕に反動を傾け、勢いよく立ち上がった。力む所為か、縛り上げた脚の傷口から塊のような血がボトボトと落ちる。茶けた屋根瓦が鮮血に染まるその上に、ポツリ、と重い雫が滴った。
「あーあ、降ってきた」
空を見上げ、が呟く。その小さな腕を乱暴に引き、ルカが自分の肩に担ぎ上げる。震える腕を叱咤するようにして振りかぶりトリガーを乱暴に引き絞った。
響き続ける巨人の咆哮を割くような鋭さで破裂音が鳴った。大小の影が再び宙に舞う。追いかけざまに、ポツリ、ポツリと雨が肌を打ってくる。風も強い。ごうごうと鼓膜を叩く。景色が流れるように過ぎてゆくと同じに、音は唸る風圧に支配された。されるがままルカの首に両腕を巻きつけたがふと、筋張った硬い背中に耳を押し付けた。
風音が遠ざかった。代わりに心臓の鼓動が聞こえる。早い。それに乱れている。細くなり、太くなり、刻、刻、送り出すままに血を流してゆく。巻きつけた腕にすら、雨滴とは違う滑った熱いものが這うのを感じる。確かに、じき彼自身の言うとおりになりそうだ。首筋に垂れた雫に身震いしながら地鳴りのような音響にしばし聞き入った後、が口を開く。
「やっぱり、兵士ってすごいのね。こんなにボロボロなのに、こんなに早く逃げられるなんて」
致命傷を負ってなお、残数を省みない猛烈なガスの噴射により二人の移動はかすむ早さだ。低く高く唸る風音は耳をちぎる勢いで体中をすり抜けてゆく。一心不乱にトリガーを操るルカから返事はない。ふふ、と絶えかねたかのような笑みが落ちた。が小さく唇を舐める。
「残念。本当に。もっと早く来てくれたらよかったのにね。そしたら、あの人たちも死なずに済んだかもしれない」
ブン、とひときわ高く二人が飛び上がる。落日を透かさない分厚い雨雲から落ちかかる雨は本降りの気配を見せ始めた。水気に遮られつつある風景の向こう、崩落前より備え付けられていた見張り塔付近に大勢が集まっているのがわかる。見たところ、おおむねの巨人は殲滅しきったらしい。残党を処理する兵士の動きから見て、調査兵団の拠点と見て間違いないようだ。が顔を上げ、ルカに巻きつけていた片腕を取り上げた。滴の溜まる睫を戦がせ、雨に濁る視界をぬぐう。ぬるり、と血が着いた。ぬれた手で、荒い息を繰り返すだけの肩をそっと撫でた。そのまま指を滑らせ、肩甲骨の形をなぞる。硬い骨と筋肉、皮膚と肉、脈動。音の元へ掌を押し当てた。
「もっと早く助けてくれてたら、こんなことにならなかった。きっとね。でもごめんね、」
前方の集団がこちらの異質さに気づいたようだ。俄かに騒然とする兵士が口々に何事かを叫び、刃で指し示し、飛び出し駆け寄る構えを見せる。の腕がすべり、胸元へ滑り込む。
カチリ、と檄鉄を起こした。
「わたしは祈らないわ」
巻き起こる風の中で火薬がはじける。
音はなかった。
猛烈な噴射音とともに弾丸のようにこちらへ近づく影を目で追っていたリヴァイが突如身を翻した。人にしてはいびつな影が突然力を失い、失速したからだ。待機していた班員からどよめきが沸き起こる。それもすでに背後だ。投げ出された体がそのままに高く宙に放り出され、まっさかさまに落ちてゆく。幸いにして、影はかなり高い位置を駆っていた。墜落するより早く近付くには十分だ。同時に飛び出した何人かが視界の端に映る。瞬きする間に距離をつめ、影を掴めば、異様に軽い。子供だ。見開かれた目から瞳が零れ落ちそうだ。
「お前、」
見覚えのある顔に思わずといったようにリヴァイが呟く。だが、相手が何かを言う前に彼は舌打ちひとつで体勢を変え、華奢な身を肩に担ぎながら建屋の壁を蹴りつける。逆さまになる視線の先、同じように飛び出した三名が何とか血まみれの兵士を受け止めていた。そのまま、危なげながらも石畳に着地する。その姿を追うようにしてリヴァイも地に降り立った。担いでいた身を乱暴に降ろすなり、足早に駆け寄ってゆく。班員らに両肩を支えられている兵士は間違いない、ルカだ。いびつな影の理由は欠損した右足の所為だった。俯く血まみれの体に手をかける。
「おい!」
しっかりしろ、そうかけるはずの言葉は喉元で止まった。ぐいと胸倉を掴んだ手に、あとから、あとから、滲み出す血がぬるりと滑る。俯いた端正な顔の瞳は硬く閉じられ、見る影もない金の髪ごと、鞭のように雨が滴り落ちてくる。本降りになり俄かに水煙が立ち上る。
もう自立すら難しい彼の瞼がふと僅かに痙攣した。唇がわななく。
「…兵長、」
濁りきった声音が手招くまま、リヴァイが素早くルカの唇に耳を寄せた。ひゅう、ひゅう、とかさついた吐息ばかりが漏れる。なんだ、という前に、長身の身が頽れる。咄嗟のことに両脇の隊員だけでは支えきれず、そのままリヴァイに覆いかぶさった。
「ルカ!」
背後で悲鳴じみた怒鳴り声が上がった。ネスだ。リヴァイがそう当たりをつけたと同時に、平素と変わらない、静かな声が鼓膜を叩いた。目を見開く。
「…何、」
聞き返す間は、なかった。突然重みを増した身体を抱きしめ、支える。心臓の鼓動が絶えた途端、数え切れない傷口から湧き出すようだった血の流れも止まった。張り詰めていた筋肉が弛緩し、失われた右足ごと、四肢が鉛のように覆いかぶさってくる。降りしきる雨が残るぬくもりを急速に洗い流してゆく。
ゆるく瞬きを繰り返し、言葉を飲み込み、地に横たえようとしたところで、ネスが唸り声を上げながら亡骸を引き剥がした。両肩を掴み揺さぶろうとしたが、重みに耐えかねたらしい身体がどう、と地に落ちる。だらりと垂れた手足、噛み千切られた肩口と頭に、目を射るような鮮血がこびりついている。打ちかかる雨に洗われてゆく顔と髪だけが、まるで眠るように不変だった。いつもどおりの、色や波のない顔立ちのくぼみへ、無造作に滴がたまってゆく。
班員が次々に集まってきた。飛び交う悲鳴や怒声の中、強くなる雨脚が濡らすままに乱されながら、ふと、リヴァイが首をめぐらせた。分けた前髪の先から流れるように水が垂れる。目に入り損ねたそれは頬を伝い、顎を滑って、後は、一緒くたに流れて消えてゆく。視線がさまよった。視界の中では激しく行きかう人影が右往左往とやかましい。そこに、投げ出された体勢のまま固まり、蹲り、ぬれそぼる少女がいる。瞬きをしない彼女の瞳と、やがて視線がぶつかった。交錯する瞳同士の間、その他すべてを巻き込み、圧し掛かる雨が強くなってゆく。
「どうして! 何でだルカ!」
「班長、落ち着いてください!」
ネスと、それを止めに掛かる何某かの大音声がある。背を向けたリヴァイに、それは波動のように反響する。
「何でお前が、お前がこんなことになるわけないだろうが! 巨人なんか敵じゃねぇだろ!? そうだろうが! なぁおい、おい、おい起きろコラァ!!」
最後は裏返り、意味のない叫びとなったネスの怒鳴り声が響き渡る。周りの班員が必死で静止するのも構わず、横たわる死体の胸倉を無茶苦茶に掴み、揺さぶる。なぜ、どうして。答えのない問いが一方的に繰り返されてゆく。俄かに風も吹き出し、雨滴は激しい吹き降りに変わる。頭上では低く、唸るような雷鳴が忍び寄ってきた。落雷も近いだろう。また激しい雨が降る。
あの時もそうだった。出立前夜、雷鳴と驟雨が喧しい闇夜で、あの男はどうして、と繰り返していた。