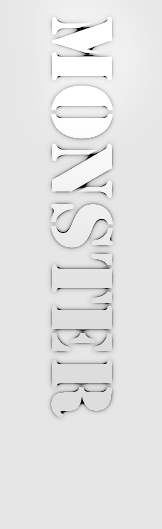MONSTER
22.あなたはゴミ、消えればいい
広場中央の時計塔。
それはかつて地区のシンボルとして親しまれ、恋人同士や家族連れのメッカだった。定時に遠く鳴り響く、低く重い鐘の音もまだ記憶に新しい。塔本体は四角く木を組み赤レンガを積んだ頑強な造りで、先端に据えられた丸時計は三時間ずつ四度の時刻表示である。薇仕掛けに連動する釣鐘は優に人の身長を超える大きさで、これは時計本体の下方、塔内部に格納されている。音を拡散させる為、鐘の四方それぞれにアーチ状の穴が空いており、その縁から外側には塔を一周する出っ張りがある。およそ二メートル程度の幅だが、人が数人乗る程度であれば問題ない。そこに、崩折れるようにして、しゃがみこむ人影がある。
地上はすでに虐殺を少し過ぎた辺りに差し掛かっている。惨劇は佳境に入ったといってもいい。瓦礫が転がる路地に食い散らかされた逃げ遅れや数名の兵士などが散乱し、その上を虚ろな瞳の巨人が何体か、諦め切れない様に右往左往する。口端に誰かの腕を引っかけたままの哀の巨人がふと上を見上げた。視線が時計塔に定まるなり、咽び泣くような声を上げながら、塔に突進する。せいぜいが二、三メートルの図体では先端まで届かず、取り縋ったあとは地団駄を踏みながら拳を壁に叩きつける。駄々をこねる彼を真似るようにして、続々と塔の周りに巨人が集まりだした。大小、表情の有る無し、どれもが異なる中、上を向く割けた口だけが一様に揃う。肉を求める歯が擦れ、不快な音が木霊する中、ひときわ高い金属音が空気を割いた。風が吹き、刃がしなり、最も脅威であろう大型を一体、まるでついでの様に仕留め、蹴りつけて更に高く舞い上がる。右腰側のワイヤが巻き上がり終えると同時に、上背のある影は塔の張り出しへ着地していた。剣柄を兼ねたトリガーを投げるように仕舞い、怒鳴る。
「何をしてる!」
張り上げた声に視線を返すものはいない。皆、一様にして縁の上から、殺戮が繰り広げられる地上をぼんやりと眺めている。だけが直立し、その外は地べたに腰を落ち着け、へたり込む。その人影を含め、総勢九名。怪我人もちらほらと見える。少女と、カルノは無傷のようだ。煤で汚れた粗末な衣服が風に煽られている。ふと、が振り返った。ルカと目が合う。ちら、と微笑んだ。
「ルカさん」
いつもどおりの、耳馴染みのいい声だ。なんら変わりない。しかし、ルカは妙な既視感を覚え口をつぐんだ。この光景に、覚えがある。がこちらに近づいてくる。
「よかった、誰が来てくれるかな、と思ってたの。知ってる人でうれしいな」
「…ここで何してる、」
「皆で逃げてたら、ここが一番安全だろうって、カルノさんが」
ね、そういい、が無言のまま俯くカルノへ水を向けた。暫く見ないうちに、細身ながら成人男性らしい上背だった男はずいぶんとやせ細っていた。返る言葉も無く、つむじを見せたまま微動だにしない。が再びルカに向き直った。
「ここで待ってたら、調査兵団の誰かが来てくれると思ってたの。軍人の誰かが来てくれたら、きっと助かる。そう信じてたのよ。よかった」
ルカが僅かに顎を引いた。前髪が瞳に落ちかかる。
「…俺には、君達を助ける権限など無い」
少女が小首を傾げた。俯く青年の覗き込むようにして、莞爾とする。
「大丈夫。そんなのあてにしてないから」
ルカが弾かれたように顔を上げた、その瞬間だった。蹲るだけだったカルノが雄たけびを上げながら飛び掛ってくる。咄嗟に反応するも、何かに脚をとられたルカの膝が崩れた。たたらを踏んだ体の上に、そのまま痩せぎすの男が覆いかぶさってくる。
「ッ、何を…離せ!」
「うるせぇッ!」
血走った目で叫び、口角泡を飛ばしながら掴みかかってくる。そのまま二人、転げまわるように乱闘を繰り広げる。だが所詮軍人対民間人である。決着はまもなくつくかに見えた。取り付くカルノをルカが往なし、立ち位置が逆になったとき、それは起きた。今の今まで微動だにしなかった男が二人、やはり奇声を上げながら、立ち上がり、揉み合う二人に飛び掛ってきた。その不意打ちになすすべなく側頭部を打たれ、束の間視界がぐらついたルカの上に三人分の体重が載り動きを封じる。後ろ手に両手を取られ、髪ごと掴まれた頭を顎から強かに打ち付けられた。堪らず呻くルカの視界を、華奢な脚が横切る。踵の低い靴が音も無く、きちんと整い揃え立つ。それはそのまま振り上げられ、無理やりに下げられたルカの頭に振り下ろされた。ガツッ、と鼻と額が縁に擦り付けられる。
「いちいち抵抗すんじゃねーよクソ軍人が、ウザいっつの」
吐き捨てるような声が飛ぶや、文字通り唾が吐き掛けられた。そして、何度も何度も硬い音が響く。そのたびに子供らしい棒のような脚が空を切った。押さえつけられている所為か、衝撃のたびにくぐもったうめき声が漏れる。張り出しの床に血が擦れつく。
「装備を取って。煙弾があるはず」
澄んだ声に促され、動いたのは、残る五人の人影だった。のろのろと立ち上がり、渾身の力で押さえつけられているルカに近づいてくる。いまだ頭がついていかないルカの前、四方八方から、幽鬼のような手が伸びてくる。身をよじるなり、関節を取られた両腕が捻られる。身体中を這う手が、軍団支給のコートのうちを探り当て、目当てのものを取り出した。不快な感触が去り、ルカが荒い息をつきながら顔を上げる。その目は彼らしからぬ混乱と驚愕に満ち満ちていた。
「…お前、」
が物言わぬ大人から雑に銃器を受け取っている。檄鉄を起こし、また下ろし、片目をつぶって筒身を確認するなどを繰り返している。やがて、満足げに頷いた。弾は片手で弄んでいる。
「ん、いけそう。わたしでも撃てるな」
言うなり、薄い笑みを浮かべたまま、やっとルカに向き直った。目が合うなり、瞳を見開いて驚く、そして再び笑った。
「何、その顔。なんて顔してるの」
可笑しくてたまらない、といったようにケラケラと声を上げて笑う。
「わたしがこんなのでびっくりした? ごめんね、せっかくかわいこちゃんでやってたのに、こんなおてんばで残念でしょ」
「…騙していたのか、」
「うん」
小首をかしげ、あっけなく同意する。瞬間、ルカの脳裏で、ここに至るまでの少女とのやり取りが物凄い速さで繰り広げられる。岩の中で出会い、壁内でのやり取り、そして、今に至るまで。肩の関節が悲鳴を上げるのも関わらず、ルカが猛然ともがきだした。
「お前、お前が、お前だったのか!? お前が全部、」
「うるさいな、そう言ってるでしょ」
がさも不快げに眉間にしわを寄せる。そして、舌打ち。その瞬間、もがいていたるルカの即頭部に誰かしらの拳が打ち付けられる。視界を星が散る。再び強かに顔面を押し付けられ、縁は汚らしく血で汚れる。脳が揺れたまま、歯を食いしばり、ルカが顎で地を押して顔を立ち上げる。僅かな視界に映るへぎらつく目を向けた。
「…どういうことだ、お前達皆、巨人から逃げてあの岩に閉じこもっていた村の連中だろう! それがどうして、何が目的でこんな、」
「ああ、あれ」
が軽く頷いた。そして両の掌を天へ向け、肩を竦めて見せる。
「嘘」
声もないルカに向かい、いつもどおりの笑みで片目をつぶってみせる。
「嘘よ嘘。ぜーーーんぶ、嘘。わたし達みんな知り合いでもなんでもないし、村人なんてひとりもいない。巨人に追いかけられたエピソードも作り話。ていうか、あれが本当なら死んでるでしょ、普通」
「な」
「逆に、」
言い募りかけたルカを遮り、が笑う。
「どうしてわたしが嘘をつかないと思ったの? 子供だから本当のことしか言わないと思った? 甲斐甲斐しく世話をしてやさしくすれば心を開いて、篭絡するだろうと思ってた?」
薄い胸に手をあて、朗々とよく通る声が響く。最後、たまりかねたような笑いがはじけた。
「ばっかじゃない、ほんと馬鹿! そんな都合のいいことあるかっつーの!!」
きゃはは、と腹を抱える甲高い爆笑が響き渡る。笑い転げる彼女以外、全員が不動である。ルカを押さえる数人の手つきに、じっとりと汗がにじんでいる。温く、ぬめるようなそれは脂汗だ。ごくり、と誰かの喉が鳴った。ひとしきり笑い終えたが目尻の涙をぬぐい、再びルカへ向き直る。
「でも、ちょっとだけ悪いとは思ってる。あなたにはね。ほんとよ? 説得力ないでしょうけど。でもそれはお互い様だし。 まあ、そこでじっとしててよ」
彼女がそう言うなり、ルカを除く全員の雰囲気が変わった。押さえつけられた軍人の肌を撫でる空気が戦場で馴染んだそれになる。自分の力ではどうすることもできない、ままならない命のやり取りをはじめるとき、どこからともなくこの感触が生まれてくる。ふと、のしかかっていた重みのひとつが消えた。相変わらずさえぎられた視界の先で、のろのろと女がのほうへ向かってゆく。いつもと変わらない、不特定多数の人間と如才なくやり取りしていたあの笑顔で、がそれを迎えた。中年の女の手を握り、背伸びして耳元に口を沿え、何事かをつぶやく。
そして、女が走り出した。の手を振りほどき、巨人のように甲高い悲鳴をあげ、地面のない先へ全速力で駆け出してゆく。
「おい!」
血の滲む顔でルカが叫ぶほうが遅かった。女の身体は舞い上がり、やがてあっという間に消えた。巨人の上げる咆哮が大きくなる。その所為か、どうか、もう女の悲鳴は聞こえない。
風が強く吹いた。ルカを、の髪を巻き上げ去ってゆく。やがて彼女が振り返った。
「さあ、位置について」
笑みのまま、が言う。
さながら何かの儀式のようだ。大の大人が必死の形相で両手を組み、全体重をかけて縁にぶら下がっている。しびれる腕に耐え切れなくなったものは組を解き、やがてずり落ち、指先だけでぶら下がることになる。こうなればもう、自力で上がることは不可能に近い。彼女はそんな輩から順に近付いていった。
「言い残すことはある?」
囁きは甘く、静かだ。ゆったりと、眠りに落ちる幼子に言い聞かすように、文字通り死の縁にしがみつく人々に降りかかる。
もう二人落ちた。そのどちらも、最後はしがみつく指を踏まれ、蹴られ、無念の叫びが尾を引くまま、消えてゆく。血と殺戮の臭いにつられ、巨人が集まってきているのだろう。先程より地鳴りと咆哮、何より塔に響く振動が強くなってきた。さすがに頑丈な作りだが、巨躯の猛攻に晒されてはそう長くは持たないだろう。しかし、少女の顔に焦りはない。薄く微笑みながら、一人、一人と別れを終えてゆく。
血の滲む涙を流しながら、白髪交じりの男が組んだ腕を自ら解いてゆく。取っ掛かりを失えば、力を込めすぎて腕はあっけなく崩れ、すぐに頭が見えなくなる。彼もまた指だけを支えに、最後の砦にしがみついていた。ルカからは、もうかすかに嗚咽する声しか聞こえない。
「やめろ…ッやめろ!!」
何度も繰り返した言葉だ。先の二人が落ちる前もあとも、彼はもがきながら腹の底からそれを繰り返していた。そのたびに、顔を殴られ顎を打ち付けられ、抵抗する力を一時奪われる。眼前にちかちかと瞬く星が消える間に、また一人、姿を消していた。先程から鼻血が止まらない所為で口に入る血に咽ながら、ルカが再度怒声を張り上げる。
「何のつもりだ!? 一体何の意味があってこんなことをするんだ、答えろ!!」
何も言わぬまま、最後の一人へ向かい、はゆっくりと歩を進めてゆく。足取りは心なしか軽やか、踵の音も響く。最後の一人は、まだ若い男である。体力もあるのか、後回しにされていたにも拘らず、未だ上半身は縁の上に有る。もがく顔に苦悶が滲み、洟も涙も流れきる、凄まじい顔だ。だが彼はまだ諦めていない、ルカにはそんな顔に見えた。何とかここを切り抜けたい、生きたい、と全身で訴えている。
その彼の前にが立つ。先程から繰り返している言葉を、再度口にしながら。
「言い残すことは?」
角度の所為か、ルカから男の表情は先に落ちた誰よりもよく見えた。彼女が問いかけた途端、あれほど必死だった男の顔から、インクが水に溶けるようにして渇望が消え、諦観が広がってゆく。先に眼が死んだ。途端、また涙が溢れ出している。尋常な量ではない。恐らく目も開けていられないほどだろう。わななく唇にもたまり、咳き込みながら吐き出している。嗚咽しながら、男が何かを言っている。ルカにも聞こえないが、も聞き辛いのだろう、無邪気に小首を傾げて再度促した。男の呼吸が荒くなる。
「何?」
「ぃ、ぁか…、か、っは、か、…ぁああ、か、み」
「か?」
「かみ、ぁ、ぁああ、か、ぁ、かみさ、…かみ、さ、ま、あああああああああああああああああああああああああああ」
そのあと、男は号泣するだけだった。泣きながら最後まで目に見えない何かにすがり続け、やがて、消えていった。
前方に人影は耐えた。ルカの荒い呼吸、それを全力で押さえつける男たちの荒い呼吸、巨人が上げる歓喜とも怒気ともつかない金切り声、響く振動が大きくなり、頭上に備え付けられた素焼きの時計盤より、細かな塵が落ちてくる。ぬるい風が強くなってきた。
「そういえば、わたしも祈ったわ」
穴倉を出たばかりの頃は到底考えられない滑らかな短髪をなびかせ、はにかむが振り返る。
「最初はお父さんとお母さん、次に知っている人全て、近所の犬、たまに見かける立派な馬。最後に、やっぱり神様だった。"どうかわたしを助けてください"って」
がルカに近づいてゆく。その距離が縮まるたび、ルカを押さえつける男たちに緊張が走るのがわかる。両手を纏めて握る男の掌に滲む汗がある。口端をかみ締めながら睨みあげるルカを見、は微笑んでいる。
「でも誰も来なかった…、それである時気づいたの。わたしは自分の中の、善いものにお願いしていたんだって」
「…なんの話だ、」
ルカの鼻先に膝を折り、少女が手を伸ばす。両手を頬に添え、持ち上げた。袖先で鼻血をそっと拭う。
「善いものは誰も助けてくれない。でもわたしの中の悪いものは、わたしをあそこから救い出してくれた。わたしは生きたい。やり直したい。全部なかったことにして、はじめから、何もかもやり直したい。だからあそこに居た全員、死んでもらわなきゃいけないの」
いっそ、優しいまでに微笑み、しかし適当に放り投げるようにルカの顔を離した。再び立ち上がる。曇天を背に、彼女の目だけが光る。この目だ、とルカが閃く。はじめから今まで、彼女はこの目だけは変わらない。言葉を飲み込んだルカに向かい、が小首を傾げた。
「あなたもね」