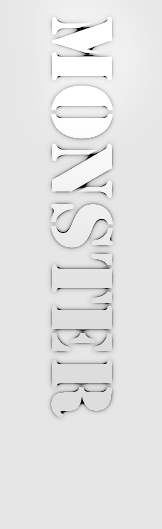MONSTER
21.弱いものたちが夕暮れさらに弱いものを叩く
深夜、また雨が降った。
夜闇に紛れて肥大した雨雲は落雷を伴う激しい雨量を齎し、夜通し火を噴く予定だった壁上固定砲が封じられてしまった。眠る巨人、目を開けたまま蹲る巨人らが揃って白亜の巨壁へへばり付いたまま雨に濡れそぼるのを見下ろし、睨み合ったまま、夜は進んだ。降れど降れど、頭上は止む気配を見せない。このままでは明け方早々に行われる作戦行動に懸念が出る、そう思われたまさにその矢先、鞭のようにひとものを叩き、暴れまわった雨滴は陽が射す直前にあっさりと静まった。まるで神のご意思だ、と得体の知れない何某かが呟いたが、周囲から特に目立った反応はなかった。
今はただ、残滓のような湿気を内包する風が侘しく吹き交っている。弱く、弱く、時折ふと強く。髪を嬲り、衣服をはためかせるそれはシンと静まり返る夜明け前の街路を駆け抜ける。立ち並ぶ家々の窓は締め切られ、戸は厳重に閉じられている。大通りから路地裏、袋小路に至るまで、そこかしこに影がある。道のある限りを埋め尽くす人々の影、影。落ちかかる薄闇で目鼻立ちさえ覚束ない。動きのない眼球には照り返しさえ点らず、皆、規則正しい瞬きを繰り返している。息することすら忘れたかのように静かな人々は、不気味に落ち着き払ったまま、そのときを待っている。
やがて、宵闇に薄く青みがかかりだした。波打つ雲の影が彫刻のように浮き彫られる。端から群青、瑠璃と流れて、そして一息に切り裂かれた。偽りの地平線上に暁が射す。曇天に阻まれ、鈍くけぶる光ながらも疑いようのない朝日である。
瞬間、怒号のような合図が飛び交い三方向の小門が一斉に跳ね上がった。突進が始まる。まず嘶きと共に騎馬が飛び出した。続けざま壁上から飛び降りる形で編制された精鋭が小門間近に群がる巨人を片端から薙ぎ倒す。間髪を入れずに、壁上固定砲がやや遠巻きを狙い火を噴いた。明けの端に動きが鈍い小物の巨人を薙ぎ、吹き飛ばす。はらわたを浚うかのような轟音だ。負けず劣らず、人と獣が叫ぶ。地響きと雄たけび、馬の嘶きも何もかもいっしょくたに、火矢のごとく放たれてゆく。
この現象が壁外東西南北で同時に起きた。砲弾、怒号、獣の嘶き、そして何より、巨人の咆哮が二重の円の内側深くまで轟く。立てこもる人々の腹と家々やその中の家具類までをも振動させる。びりびりと硝子窓が震える。地鳴りが続く。途切れない足音は遠雷のようだ。徒党を組んだ人海が潮のように、遠目には黒く波紋のように散開してゆく。王都商会がばら撒いた火器類はもちろん、道すがら無造作に打ち捨てられた鍬や丸太ですらも手に、老若男女が目を剥き、奇声を上げながら突進してゆく。事前に取り決められた隊列も何もない。ただひたすら、がむしゃらに、目の前へふいにと立ちふさがる巨大な四肢へぶつかってゆく。
まもなくして、虐殺が始まった。巨人は嬉々として突進する人波を前のめりで迎え撃った。瓦礫が散乱するのもお構いなしに、屋根が飛び、路地が割れるすさまじさで手当たり次第に喰い散らかしてゆく。悲鳴は巨大な顎の動き一つですぐに掻き消えるが、あとからあとから鳴り止むことはない。号令と怒号はほぼ金切り声に切り替わった。
明け前まで続いていた豪雨の影響で、市街地には壁上固定砲が掃討する予定だった大型巨人が目立つ。二分するはずだった隊の配置を多少変え、大半の兵卒が早々と市街地を抜けにかかった。最大出力で馬を駆り、機動力の高い精鋭だけを数班割いて路地に潜む残党を先に始末する。この流れが功を奏したらしい。四方八方から伸びる巨大な手に追走する市民兵を削られながらも、郊外の平地へ戦力的に軽微な損傷にてたどり着く。
まず、エルヴィン・スミスが陣を展開した。次々に放たれてゆく煙弾が一様に彼方を指す。音と煙幕に驚いた鳥が羽ばたく、その空が暗い。馬を駆る兵士がほぼ泥の土煙を蹴立てて走る、走る。並走する馬ですら口端からよだれを垂れ流す容赦のない速度だ。人足など、早々に振り切られる。
平野の勾配はゆるく、あがったかと思えば下がり、また上がり、下がるを繰り返す。樹齢に等しい幹を持つ木立が並ぶ道すがら、朽ちた煉瓦壁が無造作に打ち捨てられている。その影に、狙い済ましたかのように巨人が潜む。縺れる足を叱咤しながら兵団の影を必死で追っていた人々が次々に蹂躙されてゆく。駆ける兵団の背後から、追い風のように悲鳴が背を叩く。耳を塞ぎ、歯を食い縛り、馬脚は荒く街道を駆け抜けてゆく。
壁と壁の間に続く平野では巨人の絶対数自体は少ない。大部分は人類側領土に近い市街地、特に壁周辺に密集している。しかし建屋や木立しか身を隠すすべのない道のりではほぼ成すすべなく捕食されてゆく。馬もなにもない状態で、ここを越えるのは至難、そう見切りを付けた足の鈍い大衆はのろのろと背後を振り返った。ちょうど、勾配の上手に佇んでいた人員には、駆け抜けてきた市街地がよく見えた。とても自力で走りぬけたとは思えないほど、遠く、霞む家々がある。弱い風でもわかる。得体の知れない雄叫びと、生きながら食われ、死んでゆく人間の断末魔が合わさって響く。家屋の倒壊する音、もしくは、鐘の音に似ている。そう、思う背後から、また一体、二体と、巨人がやってくる。速度はない。しかし足音が重い。地響きが肌を登る。そのたびにままならない身体が揺れる。既に一年も過ぎたはずの感情や感覚がまざまざと甦る。気づけば、居並ぶ全員が泣いていた。男も女も、老いも若いもない。失禁するものもいる。立ち込める糞尿の臭い、自身で掌握できないからだの震えに圧され、誰かが一歩を踏み出した。あとはなだれるように、あとから、あとから、平野に佇むばかりだった人影が次々と、散り散りに彼方へと散開してゆく。法則はない。目的も、あてもない。凡そ、区切りなど存在しないかのような地の果てを見て泣き咽び、脚を動かし、手を振り、走り出す。雄叫びや奇声が上がった。どんどん大きくなる。一部、再び塊となった群集が突進してゆく。釉薬の厚い赤煉瓦に、焼き締めた白亜の壁が遠めにも美しい街並みは今、太い指や足がなぞる動きをするたびに、灰色の瓦礫と化してゆく最中だった。黒く、巨大な影があちこちに蠢く。その最中に、飛び出した人々が足を踏み入れて行く。
何時間かが経過した。時刻の感覚はとうに消え失せている。わかるものといえば、相変わらず姿を見せない太陽が僅かに光を寄越す位置だけである。大分、傾いてきた。溜めた雨滴を吐ききった雲は霧散せず、再び何処からか水分を集め、凝りのように濁り固まってゆく。立ち込めるようだった水烟が姿を消すにつれ、頭上の雲は重く翳った。時折、はるか遠くで遠雷が響く、様な気がする。しかしはっきりとはつかめない。それよりも、間近で繰り広げられる惨劇の音が大きいのだ。
最も巨人が密集する壁際、壁上固定砲は早朝に火を噴いたきり今は不気味に沈黙している。装弾が足りないわけではない。壁に張り付いていた巨人がトロスト区門近辺でやり過ごそうと目論んでいた市民を根こそぎ蹂躙しつくした。今は、喰い散らかされた食べ残しに小物が群がるばかりである。
比較的大型に分類されるものは早々に市外のあちこちへ散っていった。十メートルを越すものから近いものまで、我が物顔であちこちを闊歩している。名うて揃いの調査兵団、その中でも特に鏖殺に特化した精鋭たち。そのほぼ全員が市街地に残留しているとはいえ、討伐自体を禁じられたかのような編制と配置に、しかし物資だけは潤沢に設えられている。装備に不足はない。だが、手が足りない。三から五の人員で繰り返し繰り返し大型をしとめることは不可能に近い。自然、隊員達は防戦を強いられてゆく。
足掻き、叫び、絶叫する複数人をまとめて握り締めた巨人が一体、徐に立ち上がる。膝を擦り、足裏で踏みしめるたび、整然と敷き詰められた石畳が割れ、めくれ、茶けた土くれが広がってゆく。伸びをするように直立すればひときわ大きい。そこいらの建屋が玩具に見えるほどの巨躯に笑みを貼り付けて、天に向かい大口を開けてみせる。唾液と臓物にまみれた口腔へ全員を放り込むなり、すぐに租借を開始する。量が多い上暴れるせいか、うまく噛み切れないらしい。にちゃ、ぐちゃ、ごりっ、ガリッという音の合間に、くぐもった断末魔が歯の隙間から漏れてくる。頬を膨らませながら、はみ出た手足を指で押し込めつつ、一心不乱に口を動かす。柔らかい肉は前歯で裂き、固い骨や間接は犬歯で砕き、あとはまとめて奥歯で磨り潰す。吐き気を催す湿った音が割れた石畳を撫で、崩れかけた家々の壁に木霊する。
ギュンッ、とワイヤの軋む音が空を割き轟いた。遅れて屋根瓦の破裂する音。歯噛みしていた巨人の首は千切れんばかりに弾き飛ばされた。うなじを削ぐ、ではない。ほぼ斬首だ。右に逆手、左には順手に刃を構えたリヴァイが振り抜きざまにもう一体に飛び掛る。目を割いてから首筋を凪ぐ。一瞬で絶命した巨人を蹴り上げ宙に舞った身体はそのまま近場の屋根に着地した。やかましい音を立てながら巨体が地に頽れる。瞬く間にもうもうと立ち込める蒸発煙の白い隙間から、酷く静かな目が夥しい血に濡れる路地を見下ろしていた。
「兵長、飛ばしすぎです!」
遅れて追いついた女が叫ぶ。赤銅色の髪を振り乱したペトラだ。血塗られた剣を振りながら高さのある塔壁に取り付いた。彼女の半身も血に濡れている。返り血だ。その証拠に、蒸発する気体が白く立ち上っている。リヴァイが顔を巡らせ刃を振った。あらぬほうを指す。
「ペトラ、お前は荷馬車の傍にいろ」
「聞けません!」
「聞け」
「では見える限りを片付けたらそうします!」
そういい、彼女が飛び上がった。路地の二つ向こうで甲高い奇声が上がった。図体の割りに素早い四メートル級がやかましい音を立てて疾走している。それを追い、ワイヤがしなった。小柄な身があっという間に点になる。わだかまっていた蒸発煙が巻き起こった風に嬲られ、消えた。
「…勝手にしろ」
既に聞こえては居ないだろうが呟き、彼もトリガーを握りなおした。太く、傷跡に爛れた指を開き、また握る。二度繰り返したところで霞む速さで飛び上がった。高く、なるべく高く身体を跳ねさせる。重力が下へ下へと引くまでに、素早く視線を走らせる。近場には三体。そのどれもが五メートルを越す。事前伝達のあった作戦仔細どおり、街道を駆け抜ける荷馬車の護衛が任務だ。であれば、市街地の掃討も当然含まれる。物資は潤沢だ。手足の動く限り、目のつく限り、片端から始末する。頭から落ちかかりながらアンカーを投げつけた。同時にガスを噴かす。霞む視界に流れる家々が滲む。目の前にたるんだ脂肪が煤で黒ずむ汚らしい首筋が迫った。
「退け」
めり、と肉に刃がめり込む。どんな巨人が相手でもこの感触は同じだ。脂肪は軟らかいが、太い血管と筋肉を割くには流石に反動がくる。そこを抜ければ骨だ。頚椎に当たれば刃は鈍る。ぎりぎりを滑り、二刀が楕円に走る。クロスさせた腕を振り切れば、返り血が頭から降りかかる。それを避け、再び飛んだ。その繰り返しだ。
兵団のコートがいささか重い。水気を含んだ風が体中に纏わりつく。巨人の断末魔が鼓膜を痺れさせるのも不快だ。避けきれず右上腕に被った返り血が蒸発する、その白い棚引きが消えうせるほど、ガスを使い奔る。
こんな噴射は久しぶりだな、と冷えた頭の片隅で思う。壁外での戦闘は節制と計算が全てだ。後を考えずに立ち回るなど初めてに等しい。こんなこともあるのか、とむなしい思考が回る。だが戦場で考え事など愚の骨頂だ。この思考もまた、愚かと切り捨てるべきなのだろう。
また一体、進む先の目の前に立ちふさがる。まだ子供といっていい年齢の女が、頭を残して齧られている。無念と恐怖に彩られて絶命した顔は涙で濡れている。しゃがみ込み、新たな獲物を握ろうとした巨人の、まず腱を切った。そのまま倒れる。地響きを立てて転がる巨体の上に舞い、落ちながら削ぐ。
四肢をばたつかせ、これもまた絶命した。消えてゆく巨体から飛び降りる。石畳に固い靴音が響いた。血と汚物にまみれた地面のさき、転がる生首と目が合う。
「…最悪だな、」
なぁ、と口にして、しばし。腕を上へ掲げた。トリガーを引く。慣れた鋭い音が脳に響く。軽くつま先を蹴れば、巻き上がるワイヤはいとも簡単に人一人を宙に持ち上げる。建屋よりもさらに高く身体を持ち上げた。巨人は腐るほど居る。まだまだ、殺さずにはいられない。
凡そ、一方的である。
既に、黒くうねるようだった人影は消えた。鼓膜を破る勢いで響いていた絶叫も途絶え、人声は一つ、二つと鳥の鳴き声のように突然と上がるだけになる。建屋の倒壊も落ち着いたらしい。暴れる人間が逃げ、死に絶えたからだろう。破壊や衝撃に耐えかねた屋根壁が時折崩れる程度である。辺りには血の臭いよりも、道端に吐き散らかされた死体から漂う饐えた吐瀉物臭のほうが強い。酸化し、茶けた血痕の上に真新しい千切れた内臓がこすりつけられている。中途半端に喰い散らかされている所為で、租借痕がみな雑だ。どうやら腸らしいそれはずるずるととぐろを巻き、端からは糞らしいものが漏れている。その先に脊椎、肺腑、肩から上腕の部位、頭髪を一部残した皮が落ちている。これで、人一体分。石畳の割れ目を被い尽くさんばかりに、同じものがごろごろと転がっている。
多量の雨を内包する分厚い雲がどんどん低くなってきた。日没までもうすこし、その斜光を遮るせいであたりはずいぶんと淡暗い。時折唸るかのように震え、遠くない驟雨を予告するかのようだ。胎の底を撫でるかのような遠雷と、人々の上げる絶叫に混じって、銃声が木霊している。どこかで誰かが銃を使っているらしい。
無駄なことを、とルカの唇が動く。彼にして、ほとんどないことだった。唇はいつも真相とは程遠いことを呟く。言葉は無意味だ。そういったのは誰だったか、茫洋とした意識の中で様々な顔が浮かんでは消えてゆく。
軽く振った腕先から先ほど蒙った血と唾液の飛沫が飛び散った。他二人の班員と自分、計三人構成の班でなるべく素早い巨人を掃討するように、との命を請けていた。四方に散った他の少数班もおおむね同じだ。だが、その命令ももはや機能しているのかどうか、先ほどから他班員の影すら見当たらない。対巨人戦の手練と持ち上げられようとも、普段から交戦が首尾ではない班員みな、生き残るのに精一杯だ。出立までは人らしい仁義に取り付かれていた者も、難民への手出しなど早々に投げ出しほぼ防戦に回っているのだろう。
一人が霍乱し、残る二人で腱と項を狙う。取り立てて顔馴染みという相手ではなかったが、小物の掃討はどちらかというと精密作業に近い分、息は合わせやすかった。刃の消費がやや早い己にとって作業を共にする相手というのも何かと便利だ。だが、それも先ほどのまでの話である。些細な油断から内一人が負傷した。
「兵の損耗は最低限にするように、との厳命だった。離脱するべきだ」
ルカの言葉に、相手二人はなかなか頷かない。傷自体は深くなく、命に別状はない、軽く噛み付かれた程度だ。だが長引けば痛みは集中力を奪う。苦痛に顔を顰める班員に腕を貸しながら、もう一人の男、急ごしらえの班長を仰せつかった方が据わった目で顎をしゃくった。
「仲間が戦ってるんだ。見捨てるわけにはいかんだろ」
「離脱は正当な作戦遂行だ」
言葉が足りなかったらしい。矢庭、二人が口々に何事かをわめきだす。よっぽどの大きさではない限り巨人の手の届かない建屋にあがってはいるが、それも絶対ではない。両手を前に突き出しながら、素早く唇を湿らせる。
「わかった。では俺が残る」
再び相手が何かを言う前に、突き出した掌をことさら強調する。
「無論、俺一人での行動は自殺行為だ。よってこのまま六班の連中に合流する。あそこもここと同じ三名構成だった筈だ。ガスを交換してくれ」
相手のほうが残量は多い。そう見越しての台詞だった。差し出すこちらは戦闘となると心もとないが、後方支援班の元へ向かうくらいなら十分すぎる量だ。二人が示し合わせたように目配せする。まもなく、負傷した男がボンベの留め具に手を伸ばした。
「気をつけてくれ」
予備の刃を差し出しながら、もう片方の男が神妙そうに言う。頷き返し、受け取った刃を仕舞った。ボンベごと付け替え、残量を確認する。潤沢、とはいえないが、日没までの戦闘には間に合うだろう。何か言いたげにこちらを見遣る二人に向かい、きびすを返しつつ頷いた。
「後方支援に俺の位置を報告してくれ。六の連中と合流できなかった場合は俺もそちらに向かう」
「わかった」
返事を聞くか聞かないかの内に飛び上がった。女の悲鳴のような金切り音を上げながら射出したアンカーフックが崩れかけた庇を掠り白亜の壁に突き刺さる。ぐん、と引かれるまま浮き上がり、また落ちる。色彩に欠ける景色が顔の横を流れるように過ぎてゆく。進む先、目に付く巨人はいない。誰かが火を使ったのだろう、むせ返るような熱風に混じり焦げ臭い臭いが鼻先を擽る。ひときわ高く飛び上がった際、轟々と燃え上がる幾つかの建屋を視認した。黒交じりの硝煙が細く棚引き、肥大する雨雲と交じり合ってゆく。一見して、硝煙弾のようだが、合図に使う煙弾は漏れなく奇抜な色つきの為、作戦行動に支障はないだろう。
そこまで見送ったところで、また銃声が轟いた。割と近い。猟銃にありがちの間延びした音ではない。小型の小銃――拳銃程度の、乾いた端的な音だ。ともすれば軽い。威力は低いが反動も少ない。男はもちろん、小型であれば女子供でも扱える代物だ。耳朶を打つワイヤの巻き返し音と反動に揺られながら、視線は知らず周囲を走った。気づけば先ほど自分で言い切った六班が受け持つあたりまで辿り着いている。だが、巨人の姿も他班員の気配もない。目に付いた屋根に着地すれば踏み抜いた煉瓦が割れ、路地に転がり落ちていった。
佇み、首を巡らす。頬を撫でる風がゆるく髪を引いてゆく。ごう、ごう、と唸る燃滓交じりの風音に、焼け落ちる建屋の崩壊音がどこからともなく合わさってくる。見下ろせば、あちこちに団子状になった巨人の吐瀉物が撒き散らされ、敷石の崩れた路地を汚らしく汚しているのが見えた。唾液にまみれ、絶命した人々の表情はよく伺えない。距離もあるせいだ。ただこの位置からでも、血と臓物だけはやけに際立つ。人であれ家畜であれ、生きたまま解体されて飛び出した中身はすべて鮮やかだ。真紅から薄腿までのグラデーションが、整然と並ぶ石畳のそこかしこを彩っている。
辺りに目配せをして暫し、ここか、と音は出ずにまた唇が動いた。ここいらがまだ人の領地だったころ、市民に愛されていた円形広場だ。中央に高く聳え立つ時計塔をシンボルに、放射状に敷き詰められた白石に緑とベンチが効率よく配置され、早朝から夜半まで人の往来が途切れない賑やかな所だった。今はもう見る影もない。破壊されつくしたその中央で、打ち棄てられた時計塔だけがその名残を保っている。細身ながらひときわ高く、立体起動でも上るのには手間がかかる。遠目にもひび割れているとわかる文字盤に載る針は正午の少し前を刺したまま止まっているらしい。その前の僅かな出っ張りに、なにやら、蠢く影が見え隠れしている。
ルカが目を細め、影を確かめる。複数だ。ここまで逃げてきた市民兵だろう。夜を待つつもりだろうか。数が固まれば巨人に気取られやすくなる。そうなれば脱出は難しい―――そこまで考えたところで右半身が総毛だった。次いで風圧、巨大な拳が振り下ろされるところだ。音を殺して忍び寄ってきていたようだ。
たまにこういう、人間じみたやつが居る。不思議だ、と頭の片隅で思う傍ら、身体は勝手に半歩を退いて避け、腰下に体重を分配する。風が去ってから跳んだ。アンカーは下方。向かいのやや低い建屋の庇際辺りに刺さる。同時に第二檄が来る。中々に素早い拳だ。わざと握った刃に当てた。反動で身体が回る。そのままガスを噴かして伸びた腕に乗り、トリガーを操り刃を放つ。狙い通りに投擲されたそれは相手の右目を射抜いた。絶叫が上がる。肩口にアンカーを突き刺した。猛烈な巻き戻しに引かれるまま走り、駆け抜けざまに首筋を撫で切った。血しぶきが端から蒸気になり、剣先をなぞって消えてゆく。
その背を蹴り、飛び上がった。放物線を描いた身体が更に高く上がり、より鮮明に時計塔の人間を捉える。ぐんと近くなる視界、乾いた頬を熱せられた空気が叩く。
(あれは、)
ルカの目が見開かれた。虹彩が蒼穹よりも青い。
―――だ。