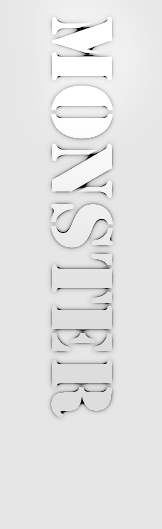MONSTER
20.その顔にピンときたら?
ぱた、ぱた、とかすかな音が石造りの廊下に響く。紙面をめくる音と、なめし革を指ではじく音だ。一度剥がれたのか、いかにも兵士らしい歪な爪の生えた人差し指が無意味にざらつく表面を叩いている。ふ、と吐息が落ちる。
「あの気障ったらしい優男のいったとおり、カルノ・コンフューザは頭のおかしい教祖だったみたいだね。でも同時に、絶大なるカリスマ性をも兼ね備えていた」
カルノ・コンフューザ。戸籍上は特に目立った賞罰のない平凡な男である。妻子、家族はなし。生まれはローゼ内北東側領土の裕福な農家の嫡男で、両親を亡くした際に相続した土地屋敷を売り払い、それを元手にどうにかして権利を得、王都へと移り住んだ。はじめは有閑夫人向けの商いなどを行っていたようだが生憎と軌道に乗ることはなく、やがて膨らんだ債務によって一時姿を消すに至る。債権者が彼の足取りを追い、地下街に降りたところまでが正規の記録である。
「ここからは憲兵団の調査結果だけど…、」
紆余曲折を経て宗教集団の総領に納まった彼は、文字通りの辣腕を振るったらしい。辛酸な経験によるものか、はたまた彼自身の天賦の才か、狭い小屋で隠れるようにして祈りを捧げていた一派に目をつけ、瞬く間に信徒を膨れ上がらせることに成功する。当然浄財と証した寄付金も多く流れていたようだが、しかし欲にかまけることなく地主や元締めへのみかじめは律儀に支払っていたらしい。土地柄、少々の問題は金銭で解決できる。各商会との関係も良好に保たれ、彼とは持ちつ持たれつ、お互いの暗部は干渉しない暗黙の了解があった。
「だけど、ある日突然姿を消した」
マリア陥落の少し前だったという。そのまま混乱を迎え有耶無耶になったものの、壁の崩壊による犠牲者というには短慮だ。
「信者の動揺は幾許か…、どうもこの前後から団体の異常性は加速したみたいだね。憲兵が踏み込んだ捜査に打って出たのもここからだ」
その後も信者達はいじらしく活動を続けていたが、総統を失った彼らはやがて秩序をも失ってゆく。横行する人買いよりも強引に一般人を拉致しだした彼らは、程なくして一斉に摘発されたという。
「公には王家に仇成す叛乱分子、として処理されたらしい。まあ、それも致し方なさそうだ。市井に人食い人種がまぎれてるなんて、精神疾患者より繊細なシーナ民が知ったら生きてけないよね」
「叛逆者はまず間違いなく極刑だ。そのあたりも都合がいい」
最後を浚ったのはリヴァイだ。窓のすぐ傍の壁にもたれ、腕を組み、外側からは気取られない角度で階下を覗いている。視線の先には、相変わらず何をするでもなし、手持ち無沙汰で口数少なくやり取りする大小の影がある。
駐屯に身柄を移されたとはいえ、環境は大きく変わらない。以前までと似たような兵舎に移された彼らは出立までの少ない日々をひどく静かに過ごしている。医務員ら曰く、の体調はほぼ快復しているらしい。手厚い看護と管理、何より本人の努力により順調に力を取り戻し、軽い運動であれば積極的にこなすべきとの診断がおりている。最初乗り気ではなさそうだった本人も、大人たちに促され再び許可された範囲での散策を再開している。既に救出された他患者の病室にも顔を出し、体調の芳しくない幾人かを見舞っている。特に、あの老人はが顔を出すと途端に大人しくなり、治療にも素直に応じるようになるという。日々必要な薬物投与すら難しいと愚痴をこぼす看護婦達に、宛ら天使か救世主のようだと持て囃されている。
先程までは伸ばした指先すら視界が怪しい豪雨だった。気まぐれな雨雲は一定の雨量を溜めるなり一気に吐き出し、また休むを繰り返し、今はちょうどその中休みに当たる。結構な水量が流れただけあって、辺りには雨後独特の臭いに満ちている。実際には濡れていないのに、何かしらに触れるたびに雫が跳ねるかのような湿気ぶりだ。
そんな中で、青年と少女は意味無く灰色の街並みを見、時折通りかかる何某かと話し、あとは、言葉少なに何かを言い交わしている。ルカの表情は一貫して無だ。だが、少女が何かを問いかけるたび煩うことなく律儀に返答している。そんな彼に慣れたのか、少女のほうも気後れしている様子は無い。随分伸びた髪を時折引っ張り、よく動く瞳でくるくるとあちこちを観察している。愛想がいいらしく、この短い期間で打ち解けたらしい人々に気安く声をかけられては、はにかみながら屈託の無い笑顔で対応している。
「可愛い子だね」
ハンジが窓の外を見もせずにいった。視線は手元にある手帳か何かに落ちている。リヴァイが鼻を鳴らした。
「ガキだぞ」
「いやだな、だからでしょ」
「俺にはわからん。煩いだけだろ」
「モテないくん典型の台詞だね」
「言ってろ」
「・ヨルム、」
ぱらぱらと紙面をめくりながらハンジが僅かだけ視線を傾けた。
「旧マリア領内バルトロイ村出身、満十三歳、か。十三にしちゃちょっと小さいね。それもあるのかなぁ、みんな猫可愛がりだ。あんな小さな子が、ねぇ」
リヴァイが顎を引く。影に呑まれ、目だけが光るようだ。
「あのガキ、その腐った宗教集団に関わりがあると思うか?」
「さて。口を割らないのはそれもあるのかもしれない。ただ、聞く限りじゃ脅えている。自ら話をすることにね」
「カルノ・コンフューザ?」
ハンジが肩を竦めた。
「同姓同名のご本人はどうしたって喋る気は無いらしい」
そう語るハンジは既に二度ほど、カルノの元を訪れている。そのどちらも尋問は不調に終わった。一度目は口を開かない彼との交渉が敢え無く時間切れとなり、二度目は相手が寝入ったまま起きない、という体たらくだ。不思議なことに、彼の体調は帰還後も好くなることなく横ばいを続けている。どころか、日に日に衰弱しつつあるといっていい。死亡した人員と同じく毒を盛られている可能性を疑ったが、事の真相は有耶無耶とはいえ死人を出した医療関係者が過剰なほど神経質になっている為、その可能性は即座に切り捨てられた。にも拘らずである。窓の外に向けたままだった視線を切り上げ、リヴァイがハンジを見る。
「二、三殴りゃいい。そんなに骨のある奴じゃなさそうだろ」
「またそう短絡的な。病棟内で怪我人出してどーすんのさ。こういうのはじわじわ行くしかないんだよ」
「時間が無い」
「まぁ、ね」
唇の端を舐めながら、歯切れ悪く肯定したハンジがようやく視線を上げた。再び戻ったリヴァイの視線と同じく、死角から階下を見下ろし細く長い溜息を吐く。
「私としても気になる。なる、が。…酷い事だと承知で言うけど、もうじき死んでしまう人たちに、これ以上心を砕いてらんない。彼女も、かわいそうだけど」
二人が揃って見遣る先で、がまた誰かに呼ばれ、振り向き、微笑んで応対している。そこいらにあふれる子供となんら変わりない。彼女には、既に今回の作戦仔細について伝達されている。どういう過程が与えられ、またこなさねばならないかということも、生きて帰れる可能性はほぼ無いということも、包み隠さず伝えられた。ひどく静かに、黙って話を聴き終えたという彼女から出た質問はひとつ。それは、岩の中にいた人間全員が参加せねばならないのか、という問いだった。事実だけを告げる兵士へ向かい頷いたきり、責めるでもなく、取り乱すでもなく、わかりましたとの一言で済ませ、今に至るという。
ハンジがゆるく米神を掻いた。
「これ以上深入りすると、忘れられなくなりそうだ」
それは辛いしね、と自嘲し、開いたままだった冊子を静かに閉じる。同じく外を見下ろすリヴァイに向かい、肩を竦めた。
「岩の調査は順調だ。どうも既出の鉱物らしいのが残念だけど。私は引き続きそちらを追うよ。リヴァイ、」
呼びかけると、素直に視線が投げ返される。
「あなたも、ほどほどに」
「…余計な世話だ」
「そ。じゃあもう行くよ」
暗に連れ立って去ろうという呼びかけだったが、相手は壁から背を浮かさず、変わらぬ姿勢のまま外を見下ろしている。束の間、様子を伺ったハンジだったが、やがて肩を竦めるなり一人踵を返して去っていった。高らかな硬い靴音がどんどん小さくなり、消える。
その間も不動を保っていた兵士長の視線の先で、ふと、ルカが何某かに呼びかけられた。彼が首を廻らした拍子に光る金の髪が鈍く目を射る。俄かに細めながら見つめていれば、呼び止めた相手と言葉を交わしたルカが頷き、ついで、に向き直った。そこでも何か、言付けている。彼女が頷くのを見やってから、最初の相手と共にどこかへ向かってゆくようだ。はその後姿をぼんやりと見送っていたが、やがて手持ち無沙汰らしくきょろきょろと辺りを見渡したのちに、その場に適当に座り込んだ。
いくら掃き清められているとはいえ、野外の地べたに頓着無く座る様子を見て、自然リヴァイの眉間に皺が寄った。こうなるともう彼の口は勝手に動く。
「おい」
やおら放たれた鋭い声にが素早く立ち上がる。そのまま、怯えた様子で声の元を探し、やがて、視線が頭上へ辿りつく。ちいさな口が、あ、と開かれた。リヴァイがぞんざいに顎をしゃくる。
「無闇矢鱈に座るな。汚れたままあちこちうろつく気か?」
「ご、ごめんなさい…」
「戻ったら着替えろ。必ずだ」
小さな頭が神妙に頷くのを見て、彼の眉間もやや元通りになる。そのまま、妙な沈黙が降りた。間が空いたものの、それを破ったのはである。
「あの、こんにちは」
今更の挨拶にリヴァイの返答は無い。どうやら、これが彼女の処世術らしいと彼が思う前で、少女のこわばっていた顔が解け、笑顔になる。
「また会えて嬉しいです。たしか、リヴァイさん。お仕事中ですか?」
やわらかい、いかにも子供らしい声だ。悲哀も怯えもない。あと数日で有無を言わさず殺しにくる相手に対して、実に暢気な物言いだ。頭の片隅でそんなことを考えながら、リヴァイが口を開く。
「あいつはどうした」
前後関係ない言葉に、丸く瞳が見開かれる。
「あいつ?」
「金髪だ」
「あ、ルカさん。えっと、呼ばれたから行って来るって」
「どこに」
「わ、わかんないです。ここに居ろって言われて…、」
「具合はいいのか」
「え」
が固まる。それきり黙るリヴァイを穴が開くほど見つめてしばし、わずかに口をあけたまま、が頷いた。
「はい、あの、いいです。とっても」
「そうか」
「はい」
「…お前、」
「はい」
呼びかけに対し、が再び神妙に頷く。くるくるとよく変わる顔だ。軍人らの表情はみなどこか固く、余所余所しい。調査兵団は規模と成り立ちからして結束が固く、普段はあまり上下の差無い気安いやり取りがあるが、それでも皆、所属から日が経つにつれ顔筋が鈍くなってゆく。それも処世のひとつだ。まともではとても耐えられない。人間性に必要な喜怒哀楽のどれも失わず、巨人と相対するなどは絵空事だ。
「岩の中で何があった」
その瞬間、少女の顔に奔った一瞬の感情を見て、リヴァイが薄く目を細める。その彼の前で彼女は目を見開き、固まり、やがて、俯く。ここまではハンジやルカの話どおりだ。リヴァイが組んだままだった腕を解く。
「あの臭ぇ男に遠慮してるなら気にするな。それでも言えないならそれでいい。ただし、理由を話せ。そこまで頑なになる理由をだ」
顔の見えなくなった少女の両手がさまよった。やがて胸の前でそれぞれが出会い、固く結ばれる。三度、無言の呼吸を繰り返した辺りで、がひときわ強く息を吸った。そして力なく首を振る。
「とても、…とても、言えないです。ごめんなさい」
リヴァイが窓枠に手をかけた。
「理由は」
が腕を解いた。弛緩した指先が、だらりと体の脇に垂れる。そのまま、彼女は顔を上げた。瞳同士が交錯する。
「もう、思い出したくもない」
ザァア、と凪いでいた風が吹きはじめた。湿気は変わらず、生ぬるく湿った感触が首筋から頬を流れてゆく。交錯する瞳同士は一見よく似た色をしているが、違う。問いかける兵士長の虹彩は青みが掛かった黒灰色なのに対し、少女の瞳には一切の色がない。白目は青いほど透き通り、この距離でもわかるほど境界がくっきりと浮かび上がっている。二重の筋に、細くささくれたような睫が風に嬲られている。双方押し黙ったきり、ただ視線が交わされる。
最初、この子供の正気を疑っていた。だが、違う。そうリヴァイが思い至った頃だった。
「あら、ちゃん」
気安い声が少女にかけられる。はじかれたように振り返った先、中年の女がにこやかに微笑み佇んでいる。看護婦らしい。俯いた小柄な人影を車椅子に乗せ、カラカラという音と共に近づいてくる。
「なにしてるの? あのいつも一緒にいるお兄さんは…あら、」
そこで、ようやくこちらに気づいたらしい。口元に手を添えつつ、瞳が油断無く光る。軍人に対する市井の反応は大体こうだ。口を開く気も無いリヴァイに気を使ったか、がこんにちは、と努めて明るく挨拶する。
「ルカさんは、今ちょっと用事でいないんです。でもすぐ戻ってきます」
女がほっとしたように頷いた。
「そう。なるべく一人になっちゃダメよ。怖い人がいるかもしれないからね」
「はい、気をつけます」
「でもちょうど良かった。雨が止んだみたいだから、気分転換に出てきたのよ。ねぇ、おじいさん。ほらちゃんですよ」
そういって呼びかけたのは、日よけ代わりに薄い紗をかけられた車椅子に載る人物だった。女の手が布をどける。がわぁ、と歓声を上げた。
「おじいちゃん、外に出て平気なの?」
そう声をかけるのは果たせるかなあの奇声を上げる老人である。帰還前後にあったひと悶着が嘘のように、猫背気味に大人しく座っている。元からそうだったのか、改めて見るからかは不明だが、リヴァイの目には彼こそ子供のように小さく映った。枯れ木のような手足はいよいよしわがれて浅黒く、とても手厚い看護を受けているようには見えない。の呼びかけにも不動と見えたが、痩せこけて飛び出した眼球だけがぎょろり、と動いた。少女を視界に入れ、そこから動かなくなる。その顔を覗き込み、が小さく微笑んだ。
「今日はちょっと元気そう」
傍からそうは見えないのだが、何かしらいつもと違う変化があるらしい。看護婦もにこにこと頷いている。
「最近は少し落ち着いてきてね、今日も大人しくしててくれたわ。ホント、ちゃんのおかげね」
「そんな、そんなことないです」
「だけどねぇ。こんなこと言っちゃダメだけど、本当、今後が心配で。まあ、あなたの退院はすごくいいことよ。でもねぇ、今後が心配で…」
片手を頬に当て、看護婦がため息混じりにそう吐き出す。がちら、とリヴァイを振り返った。どうやらただの退院と銘打っているのか、例の作戦参加に関する詳細は伝えられていないらしい。ここは駐屯兵団の管轄下にある医療棟だ。三兵団中最も多くの兵士を擁する分規模も大きく、市井との結びつきも強い。王命という免罪符があるとはいえ一度死に呈で連れ帰った人員を再度死戦場に投げ込むなど、耳障りの悪い事は封じてしまいたいのだろう。恐らくルカも心得ている。そう思いながら薄く肩を竦めてやると、少女の方も察したらしい。なにも言わず、再び視線をしきりに残念がる看護婦へ戻した。やや困り顔に笑みを混ぜ、小首を傾げる。
「また、遊びに来てもいいですか?」
「もちろん、大歓迎よ。近くに来たらいつでも寄って頂戴」
「うれしい」
はしゃぐ少女の顔からみるみると暗澹としたものが消えてゆく。もうこちらを見もしない。先程とは打って変わった和やかな表情で、そのままは看護婦と頻りに何かを言い交わしはじめた。しばらく聞いていたがなんてことはない、女特有の中身のない会話である。果ても落ちもない茶番に飽いたリヴァイが無言のまま溜息をつき、そのまま踵を返そうとした。が、直前で思い直す。あの看護婦の言うとおり、何かと物騒な今時分では不逞の輩がうろついているとも限らない。少なくともルカが戻るまでは傍にいるように、と伝えるべきかどうか、考えながらまたを見る。
彼女は、あの老人の傍らに頓着無く膝を着くところだった。粗末な寝巻きが途端に湿った土くれで汚れてゆく。思わず舌を打ちかけたところで、よく通る声が流れるようにして耳に入ってきた。
「おじいちゃん。心配しないでね。わたし、絶対戻ってくるから。何があっても、絶対。絶対に」
ね、と微笑み、痩せて骨ばった手を握ってやる。聞いていないと思われた老人の瞳がまた動き、じ、とを見つめた。膝を着いた少女を見下ろす形で見詰め合っていたが、不意に、老人の頬を伝うものがある。
「まあ、」
看護婦の驚嘆が背を押したか、あとからあとから、あふれ出して止まらない。濁った目に水晶のごとく盛り上がり、滝のように落ちてゆく。しゃくりあげるでも、奇声を上げるでもなく、ただ静かに老人は泣いていた。も驚いたように目を見開いていたが、すぐに笑顔を取り戻すなり腰を上げ、老人の頭をぎゅっと抱え込む。
「泣かないで。約束するからね。わたしは戻ってくる」
あとは、似たような台詞を繰り返し、ゆっくりと老人の背を撫でてやる。これが天使と呼ばれる所以か、まさに慈愛に満ち満ちた、いたいけな仕草である。その口から出る言葉がたとえ根拠の無い無いでまかせだとしても、人の胸を打ち、涙させるには十分なのだろう。老人は声も無く泣き続けている。
リヴァイが見つめていると、もらい泣きしかけている看護婦の後ろでふと閃光が散った。何かと思えば、相変わらず派手ではないが目を引く金の髪である。足早にこちらに近づきつつも異変を悟ったらしい。表情を変えないままさっと周囲に目を走らせる。リヴァイにも気づいたようだ。目礼する青年を不動のまま睨み、あしらう。ルカがに声をかけるのを見届けてから、リヴァイはやっと踵を返した。胸の内に渦巻くものを頭の中で片付けながら、歩を進める。落ちかかる陽が廊下を夜のように暗くしている。また、雨になる。