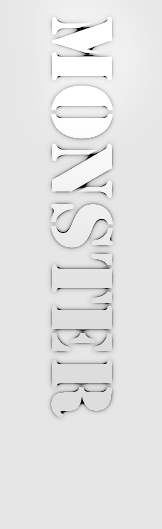MONSTER
19.火を見るより
「あっという間だった」
いやに肉付きのいい手だ。間接には脂肪によるたっぷりとした皺が載り、その癖間接は黒ずんで汚い。色はつやつやとした小麦色で、よく日に焼けている。赤ん坊の手だ、となんとは何し考えたあたりで、ふと、その手がむずがった。五指が巨大な芋虫のように蠢く。途端、まるで紙くずのように、焼き絞めた煉瓦造りの風車が握りつぶされる。喧しい音を立てて崩れ落ちてゆくその隙間から、巨大な目が現れた。大きい。睫毛一本一本の生え際すらわかる。だが一つしかない。
ギョロリ、と動いた。
「本当に、なにもかも、一瞬で、…よく覚えていないんです。ごめんなさい」
伏目がちに謝罪を口にする少女の横顔に、けぶる斜光が這ってゆく。雲が出てきたのか、降り注ぐ光は穏やかな明滅を繰り返し、低く、高くなる。やがて語られた内容は凡そ鵜呑みには出来ない、しかし生々しい、なすすべなく蹂躙された南部民の声だった。そう感想を述べながら、居並ぶ面々を控えめに見返し、ルカは僅かに唇を舐める。
「両親や村人とともに逃げたものの、道すがら他の巨人の強襲に遭い、這う這うの体であの森まで走りきったそうです。両親はその際におそらく死亡、ただ遺体は見ていないと。生き残った村人達につられ、我々に発見される今日までを篭城で過ごし、岩に関してはあまり関知していないながら、その奇異な見た目からして大人がこぞって何かしらを行っていた、ということはおぼろげに把握しているようです。とはいえ、奇岩に関してのめぼしい情報は得られませんでした。彼女の年齢からして致し方ないことかとは思いますが」
「年齢、」
口を挟んだのはミケだ。律儀に目礼を返してから、ルカが小さく首を縦に振った。
「徴兵にあたり必要な問いかと思い、予め質しておきました。彼女はローゼ陥落時点で十二、日付を確認したうえで、先日満十三になったと」
「じゃあ、条件からは外れるね?」
ハンジの言葉へは、静かに首が振り返された。
「彼らの身柄は先日駐屯へ委ねられました。その上で、トロスト区区長から命が出たそうです。戸籍の確認できない人間は年齢不詳と看做し、出撃せよと。…少女の戸籍は紛失され、確認できないとのことです」
誰も、何も言わなかった。おもむろに、リヴァイが備え付けの茶器を取り上げた。白磁の、曲線も滑らかな注ぎ口を見つめ、止まる。中身はすっかり冷め切って、湯気も水滴もない。やがてゆっくりと手首を傾けて、先ほどまで使っていた器へ傾けて注ぎ込んだ。流れる液体は出がらしの色だ。なみなみと満ちる濁りの強い水面を見ながら、黙って口に運ぶ。ずず、と行儀の悪い音が室内に響いた。
「…カルノ・コンフューザ」
程なくして、またミケが唐突に口を開いた。視線を漂わせていたハンジが瞬きし、ん? と首を傾げる。当の彼は顎をなで、エルヴィンを見つめていた。
「確か、そんな名だった」
「それはもう一人の男性の名だよ、彼はまあ、他の人々と同じ扱いになるでしょうね」
「商会はあれきり沈黙している。こちらからの要請にも言葉を濁すばかりだ」
ミケの言いたいことを察したのかどうか、ハンジの後をエルヴィンが浚った。とはいえ、微妙に的は得ていないらしい。言い募るでもなく、納得した風でもない様子で、ミケがじ、とエルヴィンを見る。さすがの団長も緑青の瞳を瞬かせ、よどみない声がすらすらと落ちる。
「軍律を曲げるほどの人物ではなかったらしい。徴兵される可能性も書き添えたが、目立って大きなリアクションはなかったな。どちらかといえば、このまま有耶無耶にしたいという印象だ。駐屯での身元照会も芳しくないようだし、なにより身柄の責任があちらに移ってしまった以上、ここまでだろう。王都商会が何を考えているのかなど、我々にはいくら考えても蚊帳の外だな」
そう、エルヴィンが語り終えたかどうか、そのときだった。コンコン、と開け放たれた扉を叩く音があがる。
全員がそちらを見遣れば、腕だけを廊下方から突き出した中途半端な姿勢で佇む姿があった。
「失礼、戸が開いていたものですから、どうお声をかけてよいやらと」
はにかんだように見える笑みを貼り付けた男が、取り上げた腕で頬をかきながらそういった。人好きする優男の風情は相変わらず、厚めの眼鏡で視線をはぐらかしている。
「何の用だ」
視線も寄越さずリヴァイが言う。それには答えず、現れたギュルヴィ・レイはまず一礼し、入室を乞う。エルヴィンが無言で頷くのを見遣るなり、特に気負いするでもなく諸氏の前を横切った。調査兵団団長へ、折口に厳重な封蝋が施された茶封筒を差し出し、薄く微笑む。
「ナイル団長のお使いです」
エルヴィンが頷いた。
「そうか、ありがとう」
「いえ」
では、と端的に礼を返し、そのまま踵を返した。長い髪が動きをなぞるかのように舞う。去り際に、ふとルカに目を留めた。身長差のある相手をしげしげと見つめ、そういえば、と誰彼なしに言う。
「懐かしい名が聞こえましたね、カルノ・コンフューザとは」
「え?」
呟いたのはモブリットだ。はた、と口元を押さえ罰が悪そうに下を向く。そちらを振り返り、全員を眺めてから、芝居がかった仕草でレイがおや、と首を傾げた。
「ご存じないのですが?」
片眉を上げて問い返したものの、やにわ唇を吊り上げる。
「まあ、中央以外の人間には馴染みないかもしれませんね。数年前に少し問題になった宗教集団の宗主の名ですよ」
「宗教集団?」
「ええ」
頬に落ちかかる髪をかきあげ、ギュルヴィがうっそりと相槌を打つ。笑みを浮かべたまま、鸚鵡返しを寄越したハンジにちら、と視線を投げた。
「今はもう解体に追い込まれましたが、我々憲兵団員は聞き慣れた名です。昨今力をつけてきている壁の信奉者・ウォール教、でしたか。彼らの前身のようなもので、活動内容から危険分子と看做され瓦解を余儀なくされました」
「どんな内容?」
「聞かないほうがよいかと思いますが」
今度はハンジが笑む番だった。両手を広げ、肩をすくめる。
「まあ、そういわずにさ、気になるじゃない。といっても、大体予想はつくけどね! エログロとかそっち系かな!?」
ち、と舌打ちが飛ぶ。
「おいクソ眼鏡、慎め」
「ごっめーん」
このやり取りにギュルヴィが噴出した。芝居がかった仕草だが、笑いを刺激されたのは確からしい、クック、と拳で唇を押さえ、何度か頷いてみせる。
「まぁ、あなた方なら平気でしょうね。仰るとおり、度を過ぎた猟奇的な活動が異端と看做されたのです。信奉内容は至って単純ですが、その手順が常軌を逸していた」
そこまでいうなり、ギュルヴィが肩を竦めた。
「壁を"女神"として崇め、そこに縋る様に噛り付く巨人を使途と目し、人類は捧げられるべき贄として尊ぶ。これがまあ、基本理念だったそうですが、件の男…カルノ・コンフューザが宗主となってから、ここに曲解が加わった。"信徒は須く使途となるべし"、とね」
「えーと、つまり、巨人になれ、ってこと?」
「ええ。その行動を寸分たがわず真似るように、と説いたようです。…ここまでいえばお分かりですね?」
黙りこくる調査兵団一同を見渡して、ギュルヴィが小さく首を縦に動かした。見えぬ誰かを睥睨するように虚空の一点に薄い笑みをむける。
「最初は信徒から"供物"を選定していたようですが、やがて一般人にも手を出すようになりまして。それもはじめは地下街の人間が一人二人消える程度でしたが、究極はローゼやマリアの閑村にも失踪者が続出した。とはいえ、開拓民に脱走者はつき物ですからね、露呈するまでにいささか時間がかかってしまい、我々が把握したころには結構な人数に上ってしまいました。潜伏先を割り出して踏み込んだとき、それはもう凄惨な現場だったそうですよ」
おぞましい連中です、と平坦な言葉が滑らかに告げる。ややあってから、フム、とハンジが顎に手を当てた。
「で、瓦解した連中はその後どうなったのかな? 聞いた限り、更生なんて期待できそうになさそうだけど」
「おっしゃるとおり、捕縛された面々はすべて極刑です。ただ、件のカルノ・コンフューザ。彼は検挙前に姿を消してしまい、以前行方知れずのままです。よって残党がどこかに潜伏している、という噂もあるにはあるのです。事実、失踪者はここ数年横ばいを続けていますからね。しかし地方の行方不明者数は事件事故両方とも以外にも数が多い。どこまで信憑性があるかも不明ですし」
「では我々が連れ帰った男がその行方不明の教祖だと?」
静かに問うエルヴィンに、ギュルヴィは微笑みながら首を振った。
「報告書は拝見しました。カルノ・コンフューザは五十そこそこの壮年の男です。その男とやらは少し若すぎますね。人相書きの面影もないようですし、同姓同名の他人でしょう」
不吉な名ですが、と尾を引く笑みで告げ、一同を見渡した。なんともいえない雰囲気が充満するのに満足したのか、再び腰を折り、暇を告げる。滑らかに室内から退出する際で、再び不動のまま虚空を見るルカを振り返り、先ほどよりも朗らかに微笑んだ。
「王政に仇なすなど、この壁内では畜生にも劣る愚行です。ねえ、そうは思いませんか?」
視線すら返さないルカを気にした風もなく、憲兵団の男はそのまま去っていった。
「今日も雨、雨、雨」
澄んだ声が薄曇りの元に響く。子供らしい、特に意味のない抑揚で口ずさむ言葉に反し、澱む空はまだ雫を吐き出していない。ただ、ここ数日代わり映えのない灰褐色に、時折薄く白いもやがやや早めに通り過ぎてゆく。即興の歌どおり、そう遠くないうちに振り出すだろう。
「降る前に帰ろう」
いつもどおりの平坦な声が呼びかける。聞いているのかいないのか、道端にしゃがみこんだ少女は鼻歌を歌い続けている。
「ルカさんは、お仕事しなくていいんですか?」
背を向けたまま、少女がいう。問われた兵士はややあってから、頷いた。
「訓練はある」
「それは、いつしてるんですか?」
「まあ、色々。夜が多い」
「わたしのせい?」
少女が首を逸らし、佇む青年と目を合わせた。緩く首が振り返され、細い金の髪が光る。
「違う」
「でも、」
細い首が元に戻った。剥き出しの項に、頚椎の影が浮き彫りになっている。
「他の人のところには行かないでしょ?」
拾い上げたらしい小石を振り上げ、振り下ろす。なにか、虫でも潰しているらしい。ザク、ザク、と砂利を掻き混ぜる音が響く。青年がまた首を振った。
「いや、本当に。元々壁外調査以外で何かをすることもないし」
「じゃあずっと訓練?」
「そうなる」
「厭じゃない?」
「考えたこともないな」
少女が再び首をめぐらせた。猫のような眼で青年を見る。
「どうして?」
心底不思議らしい。手に持った小石を振り上げたまま、中途半端な姿勢のまま固まった。問われた青年も、ややあって首を傾げる。
「どう、とは」
「わたし、家畜の世話が厭だったことがあった。いつもは可愛いけど、時々噛むし、暴れるし。ルカさんはないの?」
青年も、固まったらしい。首をかしげた姿勢のまま視線が宙を舞う。そのまま、黙りきった二人の間を水気に引かれた羽虫が行きかう。ひいては押すような風に煽られる髪を適当に掻き上げて、青年はさあ、と口にした。
「厭か。そうだな、どうだろう。もし軍を辞めろといわれたら考えるのかもしれないけど」
「辞められないの?」
「そういう決まりだ」
「なぜ?」
「恩赦の条件が隷属だった。家の係累は概ね斬首されたが成人以下はこれで首の皮一枚繋がったんだ。まあ、運がいい」
意味が伝わらなかったのか、少女の眉間に薄く皺が寄る。持ち上げた手に握る石を両手で弄んでいる。
「いいの?」
「いいさ。刑死なんてくだらない」
少女がふと息を吐き、石を適当に放り投げる。
「そっか」