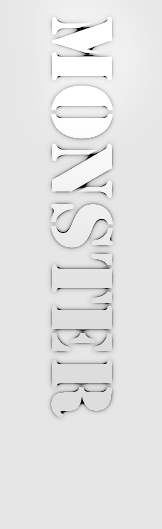MONSTER
16.ただのしかばねのようだ
硝子づたいに、水滴が滑り落ちてゆく。あとからあとから、糸を引くように軌跡を作っては消えてゆく。吐く息と気温差の所為か、ほんのりと曇る窓越しの外は暗い。時刻は夕暮れ時だが、午過ぎから本格的に肥大した雨雲が完全に陽光を隠してしまった。調査兵団医療棟二階から見渡せる景色は侘びしく、にわかに立ち上りだした水烟に白くけぶり、おぼつかない。雨雲の分厚さを裏切る細い雨は一本一本の軌跡がわかるほどゆっくりと落ちてゆく。園生に染み入る水音に耳を傾けながら、は緩く目を閉じている。
整えられた清潔な寝台の上は固い。弾機の死んだマットレスに上身だけを起こし、足と掌は重い布団の中に包まったままだ。水気が勝る空気の中で触れる木綿の表皮は少し粘り気を感じる。そこへはひたひたと、冷気が忍び寄ってくる。室内に明かりはない。同部屋の女性患者は皆横になり、寝入っているのか、思考に耽っているのか、わずかな吐息が辺りを掠めて漂ってゆく。瞼までもが視界を覆えば、あたりはすっかりと一面の闇である。一片の隙もない。特に意味もなく持て余していたその視界に、ふと、鈍く柔い光がぼう、と射してくる。蜜色のとろりとした流れに誘われるまま、は瞼を押しあげた。視界の先、僅かに押し開けられた戸の先に誰かが佇んでいる。
「誰?」
問うと、戸が遠慮がちに、しかしいっそう開かれる。廊下方には僅かな灯が焚かれている。その洋燈から漏れる光が眼を射たのだ。逆光と淡暗い室内の所為か、静かに入室する人物をすぐには判別できない。わずかに躊躇いがちに、しかし明らかに、その人物は前進してくる。まっすぐとが腰掛ける寝台の傍らで立ち止まった。かける言葉を探すようにして口ごもる長身の人陰を見上げ、あ、とが目を見開いた。
「お兄さん、あの時の…、」
「…やあ」
そういって、青年は再び口ごもる。見下ろす所為か、金の髪が僅かに目にかかるのを適当にかきあげながら、傍らに置かれたままの椅子を指さした。
「座っても?」
が頷いて返すと、青年は黙ったまま静かに粗末な椅子を引いた。腰掛けたとたん、きしむ木の音が室内に反響する。僅かに不快感を呼びながら尾を引く残響が捉えられなくなるまで黙ってから、青年が再び口を開いた。
「ルカ・ティランという。調査兵団内ネス班所属の索敵と斥候を務めてる」
どうやら、自己紹介らしい。唐突に語り出された単語の反芻すら許されず、君は、とルカが口を次ぐ。
「、だったか」
ややあって、戸惑いながらもが頷いた。
「はい」
「そうか、…その、」
「…?」
小首を傾げる貧相な少女を見つめることしばし、表情のない男が何度か口元をさすった挙げ句、動きにくそうな唇を湿らせた。
「…話をしないか」
俺と、と漏れ出るような声音が雨音を割いて静かに響く。にわかに、雨が強くなったらしい。石壁をたたき、窓を揺らす水音が室内に満ちてゆく。
「話、」
鸚鵡返しの声音にはあからさまな戸惑いが含まれている。しと、しと、とかすかな雨音が忍び寄る中、少女の黒い瞳が意味なく宙を二度ほどさまよった。不可解な言葉を吐いたまま押し黙った青年は、次の言葉を探しながらゆっくりと唇を開く。なかなか声は出なかった。
「色々、考えたんだが、結局君が一番話せるんじゃないかと思って」
「わたしが…?」
「何故あんなところに入っていたのか」
彷徨うままだったの視線が止まった。上目遣いにじ、とルカを見つめ、息を詰めている。
「あれは何なのか、あの男は誰なのか、君は、誰なのか。話せることから話してほしい。医務員の許可はさっきとった。時間は区切られたけど。体調が回復するまでとは思ったけど、そうこうするうちに先日何人か死んでしまった。これ以上待つことに意味があるとは俺は思えない」
言い切り、再び押し黙ったルカが見つめるままのを見て返す。こくり、と小さくどちらかの喉が鳴る。
無言が続いた。やがて、再びルカが口を開く。
「とはいっても、いきなり何から言えばいいかわからないとは思う。俺も、何を訊けばいいかすらわからない。子供と話すのもそう得意じゃないし…、」
途切れてゆく語尾が尾を引いて、再び沈黙が満ちていく中、雨音ばかりがこだましてゆく。ふと、ルカが視線を窓の方へ変えた。薄暗い光の中で金の髪が揺れる。
「だから、しばらく、何か適当な話をしよう。君が訊きたいことを訊いてほしい」
が顔を上げた。驚きと怪訝、僅かな警戒がない交ぜになった複雑な表情で首を傾げ、目を合わせない相手の横顔を見上げる。
「…訊きたい事?」
「そう。あるだろう? なんでもいい。俺が知る限りで何でも答える。君が知りたいだけ聞き尽くしたら、今度は俺が訊きたいことにも答えてくれ。それならいいだろう?」
小さな唇が僅かに開閉し、やがて、再び閉じられた。窄められた子供らしい花唇が頑ななまま、の視線が刹那、宙をさまよった。その先には、ルカが眼をやる暗い窓がある。雷こそ鳴らないが憂鬱さ漂う灰色の空、細い雨を同じように見つめ、少女が細く息を吸った。
「雨、好きですか」
ルカが僅かに視線を戻した。を見てから、また同じ窓へ戻る。
「嫌いじゃない」
「なんでですか?」
「…俺が君くらいの頃は、身体を洗うのも、飲み水も、雨だった」
ルカが僅かに笑った。
「だから多分、なかったら死んでいた。でも寝床も濡らされるから好きにはなれなかった。こんな風に分厚い雲は特に、見かけと違って一気に降らずに長引くんだ。晴れるまでが億劫だったな」
「軍人さんなのに、貧乏だったんですか」
窓の先を見つめるままだったルカの顔が、再びに向き直った。少女は頑なにこちらを向こうとはしない。
「昔、各兵団への志願率が極端に低下した時期があった」
頬骨の目立つ小さな頭を眺めながら背凭れに重きを預け、投げ出していた指先を何とはなしに組み合わせる。
「君は多分、生まれているかいないかくらいだ。ちょうど壁内に伝染病が蔓延して、子供や年寄りが大勢死んだ。軍人も例外じゃなくて、普段寄り集まってる駐屯の連中なんかひとたまりもなかった。警邏の連中が軒並やられたから、治安が一気に悪化して犯罪者が増えた。この反比例を逆手に取った政策が施行されて、俺は軍人になったんだ」
「病気で、犯罪者が増えて、軍人になったの?」
「そう。死ぬか従軍か選べといわれて、まぁ、仕方なく。だから君が知る軍人とは扱いが違うんだ」
「…難しいね」
「悪い。つまり恩赦、いや、徴兵といえばいいのかな。…これも難しいか。まぁ、要するに、俺は碌な人間じゃないってこと」
思わず、というように吐息が漏れた。それはそのまま、いかにも少女らしいクスクスと喩えられる微かな笑いへ転化されてゆく。不安定な首筋に乗る小さな頭蓋が揺れ、少女の顔は正面へ戻ってきた。やや血の気の薄い顔ながら、声どおりに笑顔を湛え、はにかみながらルカを見る。
「本当に、何でも答えてくれるなんて、ちょっとおもしろいね」
「面白い?」
繋がらない単語にルカが首を傾げる番だ。表情の変わらない男に向け、少女はだって、と小さな唇をほんの少し苦めに吊り上げる。
「わたしの知ってる軍人さんはみんな声が大きくて顔が怖くて、口がきけない人ばかり。それがいい事でも悪いことでも、何かを言うと必ず怒るの。それが、お話しようなんてはじめて言われたから、びっくりした」
「そう」
「わたしだけじゃない、みんなが喋っても同じだから。だから、お兄さんは不思議で、おもしろいなって」
はそこで言葉をきり、分厚い掛け布団に押し込められたままの足を少し動かした。もぞり、と木綿の皺へ溜まる影が形を変えてうごめいてゆく。色味は灰が掛かった青、水屑交じりの下水と同じ色だ。その筋を目で追った後に、ルカが再びを覗き込む。
「君の言うみんなっていうのは、彼女たちのこと?」
固い掌が翻る先は、蹲り寝転んで息をするばかりの婦人たちである。息を潜めてはいるが、会話によって成されるあからさまな訪問者の気配は拭いきれない。にも拘らず、反応を示すものはやはり皆無だ。ルカがここへくる道中、二、三と話を聞いた看護婦によれば日がな一日その調子だという。まるで生きた心地を感じさせない呈に、心配よりも不気味さが混じる声音だった。反芻するルカの前、がやおら、頷く。
「…そうです」
「知り合いなのか」
「みんな同じ、あそこの、あの村で暮らしてた」
「風車のある?」
こっくり、と小さな頭が上下する。明確な肯定を受け、青年は矢庭に投げ出したままだった背を起こす。
「村人だったのか。全員?」
「はい、大体は」
「大体?」
「知らないひともいます」
少女の答えは子供らしく断片的で、一つの質問に返る情報量は僅かだ。青年はチラ、と壁の時計に目配せをした後、僅かに開いた唇のうち、舌先で糸切り歯を舐める。
「たとえば、あの彼女は知っている人?」
適当に指差した先には頭までを掛布で被い、息を殺して横臥する影がある。眠ってはいないようなのは気配でわかる。やや肉厚のその山にむけ、がのろのろと視線を動かした。こくり、とまた頭が上下する。
「エメラルダおばさん。エメラルダ・テェーロ。お裁縫が得意で、畑のほかにお針子さんもしてた」
「なるほど、知人だ。じゃあ、君のいう知らない人っていうのはどれ?」
「ここにはいない」
「いない?」
「…死んじゃった」
このあいだ、と靡いた声に押されるようにして、少女の顔が下に向く。小さなつむじを見つめ、暫し言葉を止めたルカだったが、じゃあ、と再び口を開いた。
「君の知っている人と、知らない人、みんな一緒くたになってあんなところにいた理由は?」
思いのほか、ぽんぽんと澱みなく返されていた返事が止まった。俯いたままの少女は震えるでもなく、泣き出すでもなく、かといって急ぎよくもなく、ただ停止したように見受けられる。ゴゥン、と雨音を割き、遠く雲が鳴った。腹の底に汚泥が残るような重低音は、これから聊かも回復しない空模様を容易に想像させる響きだ。粒の雨が硝子窓を叩き、跳ね、飛散ってゆく。
「カルノさんは?」
思いもよらない唐突な言葉に、暫しルカの言葉も止まった。雨の音だけが変わりなく室内に木霊する。
やがて、ルカが一つ息を吸った。
「変わりない。同じように安静にしてる」
「わたしがどうしてるかとか、知ってるんでしょうか」
「…さあ、そこまでは」
そもそも口を利かなくなった、とは胸のうちに収め、歯切れ悪くルカが答える。再び無言が降りた後、がゆるく首を振った。
「勝手に喋るなって、言われました」
首を振るたび、短い髪が僅かに揺れる。光の乏しい室内で、艶を失った髪はひとものの影より暗い。蠢くそれを見つめながら、ルカがおちかかる前髪をあしらう。
「殴られるのを心配しているなら問題ない。君には近づけないようにしてある」
「…言うなっていわれてるの」
「他に何か問題があるのか?」
そのまま、少女の言葉は止まった。ルカが見つめる前で、微動だにしない少女の視線は同じく一点を見埋めている。横たわる足の丘陵に出来上がった上掛けの皺だ。刻まれた一本一本に意味などない。ただ、そこを見つめたまま動かない。このまま、重ねられる言葉に意味はないと判断したルカが、じっと少女の動きを待った。吹き降りに変わったらしい雨が撫でる様に窓を叩いてゆく。
「"言葉は無意味だ"」
さあ、さあ、と水が流れる音の合間。沸き立つような声だ。前後の唐突な言葉にルカが答えあぐねている内に、が瞳を上げた。色味のない虹彩に何か、胸をざわつかせる光を載せ、僅かに微笑んでいる。
「カルノさんの口癖。こういってよく叱られたの」
「…どういう意味?」
「多分、そのまま」
ルカが再び口を開くより、閉めた戸を叩く音の方が早かった。振り向いたルカの視線の先、一拍をおいてから、先ほど閉じた扉が御静かに押し開かれた。
「…申し訳ありません、」
お時間です、と現れた能面のような顔の女が言う。衣服からして、看護婦らしい。先ほど一通りを確認した相手ではない。生気のない唇を真一文字に結び、ことさらに戸を開いて退室を促している。
ここまでか、とルカが腰を浮かした。立ち上がりざま、を伺うと、彼女はまた瞳を落とし、特にこちらの挙動を伺うでもない。
「また来る」
返事はない。
「話しづらくても、話して欲しい。君が語ることで変わることもある。あの男のことは心配しなくていい。本当に。…じゃあ、また」
平坦な挨拶にも何も返るものはなく、そのまま、ルカはに背を向けた。清潔な床は軍靴が一歩踏み出されるたび、コツ、コツと硬い音を立てて軋む。先に外へ出た看護婦が押し開ける扉を潜りかけたとき、一度、ルカが背後を振り返った。
少女は見送るでもなし、雨に濡れる窓を眺めていた。吹きつける雫がまるで洗うように何度も硝子を伝ってゆく。それを追いもせず、逸らしもせず、虚ろな瞳がただ窓に向いている。兵士はそこで視線を切り上げ、後ろ手で静かに扉を閉めた。