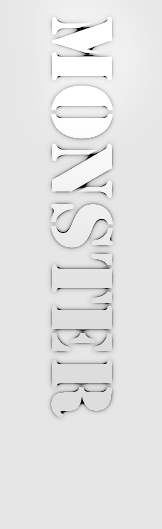MONSTER
13.天使は生き返らない
「どういうことだ」
発せられたリヴァイの声は明らかな怒気を孕んでいる。指が重厚な樫の机をコツコツと間断なく叩き、その苛立ちを物語っていた。その彼の傍らには同じく樫の椅子に腰掛けたエルヴィン、壁際にはハンジ、モブリット、ミケ、そして少し離れたところにルカが控える。全員の視線は前、調査兵団団長の執務室に召集された医療棟の面々に向けられていた。真ん中に軍医、左右に数名の看護婦が立ち並び、皆一様に青褪めた顔で項垂れている。暫く、返答はなかった。やがて、ごくり、と軍医の喉がなる。
「も、申し訳ありません、」
「妙だな。俺は今お前に謝れといったか?」
ぐ、と壮年の男が詰まる。再び喉の奥で何事か呟いたようだが、それは音にならずにそのまま空気として漏れ、霧散した。それからまた沈黙が続き、ややあってエルヴィンが口を開く。
「とにかく状況を、なるべく仔細に説明して欲しい。何故病棟で管理されているはずの者が突然同時に何人も死に至るんだ?」
「…はい」
弱りきった顔で、責任者らしいその男が固く頷いた。エルヴィンの言葉どおり、その訃報はまさに突然だった。依然会話もままならぬとはいえ、あの大岩から救出された面々は少なくとも身体に関しては時に従い順調に回復していた筈だった。そこへ、救出された二十三名のうち十一名が亡くなったとの知らせが届いたのだ。どうやら医療棟にとってもこの出来事は予想外だったらしく、その死は中一日伏せられてから調査兵団へと齎された。それがまた、リヴァイの怒りを買う一員でもある。見かねたハンジが肘でつついて睨みつけるのを止めるように促すが、それを煩げにあしらった彼は壁へ乱暴に背を預ける。腕を組み、下から切りつけるような視線はそらさず軍医を捕らえている。
すっかり怯えきった男は、一度咳払いをしてから深く呼吸した。色の無い舌が小さく唇を舐める。
「亡くなったのは、運び込まれた方々のうち特に衰弱が激しかった者ばかりです。彼らは固形物を一切受け付けず、流動食を日に一日、胃に流し込むのが精一杯なほどでした。夜までは、特に何もなかったのです。ですが、早番のものが明朝確認に回った時には、その、全員…」
「死んでいた」
「…はい、」
「検死の結果は?」
「断定はできていませんが、どの患者も激しく嘔吐した形跡がありました。…摂食物に原因があるのではないかと」
「それを管理していたのは」
「女性の何人かで持ち回りです。量はあまり多くないので、一日交代で」
「当日、その食事を作っていたのはどなたかな?」
エルヴィンの視線が、男の後ろに控える何名かの看護婦をぐるりとなぞった。それはまるで生き物のように這い、なぞった順に俯いた看護婦の肩が跳ねてゆく。暫く、返事は返らなかった。まさかいないのかな、とハンジが首を傾げた辺りで、その、と男の唇が重く動く。
「メアリ、というものです。若いながら熱心な娘でした」
「そいつは何処にいる」
リヴァイの問いに、再び男の喉が鳴った。
「…死にました」
再び、室内には静寂が宿る。男が一度、深呼吸をした。鼻と口から同時にか細い息を長く吐き出して、自殺です、という。
「患者が亡くなった翌日でした。医療棟の屋上から、身を投げて。これも検死をしましたから間違いありません。…で、ですが、我々には信じられないのです。あの子は新婚で、子供もまだ小さいのに、死ぬ理由がない! 我々は断じてこの件で彼女を糾弾したりしていないのです。確かに事情は聞きました。だが、彼女がそんなことをする理由がないでしょう! 理由など、こっちが聞きたいくらいだ!」
最後は口角泡を飛ばし、場も忘れて軍医の男が叫んだ。取り乱す男の肩を傍に居た看護婦がたまらず抑える。他の面々よりやや年嵩らしいその看護婦が男の後を引き継ぐように顔を上げた。はっきりと青褪めている。
「…隠し立てしていたわけではないのです。ただ、メアリの死に我々も混乱しておりまして、ご報告が遅れてしまいました。その点については謝罪致します。ただ、きっとあなた方はメアリがあの方々に毒を盛ったとでもお思いになるのでしょうが、誓ってそんなことはありえません。何か、計り知れない間違いがあったのだとしても、それは故意ではなく過失でしょう」
ふぅ、とハンジが思わずといったような吐息を漏らした。ガリガリと乱暴に頭を掻く。
「その過失がまずいって言ってるんだけどな」
この言に室内はまた沈黙が降りる。普段は窘める筈のモブリットも口を噤み、何処とも知れぬ先を見る視線は固定されたまま動かない。他の面々も同様である。やがて、エルヴィンが顎に手を当てふむ、と呟いた。なぞられ動いていた視線は俯く医療棟の面々からはずれ、宙を向く。
「ここまではわかった。では話を変えよう。残った人々はどうしているのだろうか」
「…他の患者が亡くなったことは知っていると思います。ですが、大きな混乱はありません。…と申しますか、現時点で彼ら自体に変わりがありません。何をいうでもなく大人しく従い、衣食住すらこちらの指示通りという有様です。ただ、時折酷く何かに怯えております」
「うん、出てきてからと一緒だね」
ハンジが頷いた。それに倣うようにしながら、では、とエルヴィンが続ける。
「三名ほど、毛色の変わった者が居ただろう。彼らは?」
「カルノ、という男性患者もやはり大きく変わりはありません。他の患者が死んだと聞かされたときは、いつ、との問いがあったようですが、それしき目立った言動は見受けられず、依然静かにしています。老人も相変わらずです。時折奇声を上げるだけで言語らしい言語はなく、意思の疎通はままなりません。ちゃんは…」
ちゃん、とエルヴィンが失笑した。それを享けてやっと、滔々と語っていた看護婦が己の失言に気づいたらしい。失礼致しました、と縮こまって謝罪する。手を振って遮りながら続きを促す兵団団長を恐る恐ると伺いながら、看護婦は再び口を開く。
「…あの少女は、酷く落ち込んでいます。メアリに随分と懐いていましたから」
「うん? 知り合いか何かだったのかな?」
「いえ、初対面だったらしいですが、メアリが最初から熱心に看護していたのです。素直な子ですから、すぐに心を開いてくれましたし、その分、ショックも大きいのでしょう」
メアリというその看護婦の死を聞かされて以来、はそれまで日課になっていたリハビリを兼ねた病棟内の散歩もやめてしまったらしい。今はあてがわれた病室で、ほかの女性患者とともにふさぎ込むだけだという。付き添う人間がいなくなった為、それも当然かもしれない。そこまで聞いたハンジがん、と顔を上げた。
「…あ、じゃあ、彼女がメアリか」
「知っているのか?」
エルヴィンの問いにはモブリットが答える。
「少し前に、あの少女が看護婦とともに班長の元へ挨拶に訪れたのです。おそらくその女性が死亡した看護婦でしょう」
「…そうだと思います。メアリは、本当に、熱心な子で…、」
そこで、今度は年嵩の看護婦が声を詰まらせてうつむいた。婦長、とほかの面々から沈痛な声がかけられる。嗚咽する彼女に対して、チ、と控えめながら明確な舌打ちが飛んだ。怒りが収まる気配のない兵士長様を振り返らずに、では、と団長が続ける。
「先ほど自殺で間違いないと断定したが、なにかそれにまつわるものや、手がかりなどは全くなかったのかな。たとえば遺書や、以前から周囲にそれらしい何かを漏らしていたとか」
明確な返答はせぬまま、軍医の男がのそりと首を振った。
「何もありません。少なくとも、我々の誰一人として、彼女が死に至る理由を思いつかない。…わからないのです、なにも。本当になにも。今確かなことは、間違いなく彼女は自らの意思であそこから落ちた。他殺や事故も疑いました。ただその痕跡がない。あるのはただ、丁寧に揃えられた彼女の靴と、自死特有の損壊がある遺体だけでした。…以上から判断して、我々はメアリが過失による患者の死亡に自責の念を感じ、自ら命を絶ったと断定しました」
男が言い切り、そしてうなだれた。エルヴィンは暫し草臥れ果てたその男のつむじあたりを眺めていたが、やがて二度、三度と頷いた。
「よくわかった。そちらも混乱しているときにわざわざすまなかったね。患者はさておき、そのメアリとやらの遺体の引き取りは済んだのかな?」
「…本日午後、家族が引き取りに訪れる手筈になっています」
「ではそれまでに、一応こちらも確認しておこうか。構わないね?」
「我々の検死に納得されないということですか」
そこで初めて、軍医の男の目に光が宿るようだった。じくりと燃えるまなざしを受け、兵団団長はにわかに微笑む。
「そう聞こえたのなら申し訳ない。ただ、我々は何でも自分の目で確かめたい偏屈の集まりなんだ。ただの性分と思って、聞き入れてほしい」
言外に肯定を受けた男は歯噛みしながらも黙り込む。しばらく微笑んだ後、エルヴィンは医療棟の各班員へ労いを施し、退出を促した。