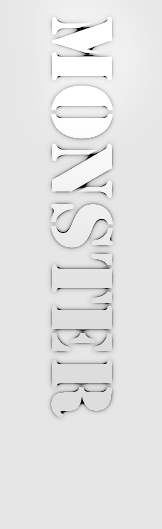MONSTER
12.フレンドリーファイア
紆余曲折あったが、兵団に連れられ帰還した人々は無事に心身へ手厚い看護を享ける事となった。男女と衰弱の度合いによって部屋を分けられ、そこから更に皮膚病の有無、意思のレベルなどを測られる。不潔な身なりは早々に洗われ、手のつけようのない頭髪は男女の差無く刈り落とされた。もはや囚人といって差し支えない見目の彼らは依然消耗激しく、話を聞けるような状況ではない。
精神の破綻というものは一朝一夕でどうにもできず、加え、無理を押せば身体の故障より厄介な代物である。なにか話を聞きたいのであれば、ひとまずは自力歩行や明確な意思疎通を行える程度にまで回復させるのが先だという結論が派遣された医師たちにより下され、あの岩や、彼らへの追及はやはり後回しにされることになった。
抵抗らしい抵抗も無く唯々諾々と従う多くに反して、あの奇声を上げる老人の抵抗が殊の外強かった。洗浄をはじめ治療までをも嫌がり、一体枯れ木のような身体の何処にそんな力があるのか、大の男二人がかりで押さえねばならぬほど、四肢を振り回して我武者羅に暴れまわる。やむなく鎮静剤を打ち一通りの処置が施されたが、相部屋は難しいだろうという判断からひとり個室に移された。その途端、静かになる。どうやら、見慣れぬ者に対して異様に怯えているらしかった。
それとは逆に、神経衰弱など片腹痛いかに見えたカルノは医療棟へ入れられるなり突然一切の口を噤んだ。開けば飛び出す悪口雑言だった唇を真一文字に引き結び、何も語らず、医師の穏やかな質問には首を縦か横に振るだけで答えるようになる。何を今更、とあきれ返る兵団の面々が揶揄するにも全く意に介さず、ただ落ち窪んだ目がぎょろりと動き、無言の一瞥をくれるだけで終わる。壁外にたどり着き、兵団の監視の目が多少とはいえ薄れた状況での不気味な身の変わりように、少なからず彼と接触した面々はなんともいえぬ胸中を持て余していた。
「なんかありますよね、絶対」
モブリットが不満顔を隠さずそういった。水を向けられているハンジはどこか上の空でんー、と生返事を返す。視線の先は、あの採取し持ち帰った岩のかけらである。光に透かしながら、矯めつ眇めつと眺めている。
「あれだけ減らず口ばっかり叩いていた人間がそうそう変わりますか? 聞かれたくないことがあるからに決まってます。商会関係者なんてどうせ嘘っぱちですよ。適当なこと言って、助かりたい一身だったんでしょ。それが後ろめたくてあんな無口な人間を演じてるんでしょう。男の風上にも置けない輩ですよホントに…聞いてます?」
「聞いてるよー続けてー」
「…いや、いいです」
なんでさ、とハンジが視線を返さないまま言った。モブリットが大仰に溜息をつき、机の上に置かれた岩のかけらを手に取る。小さいながら、確かにあの岩のかけらと思わせる、妙な黒光りをする感触である。生身で触るとやはり墨のように指先が汚れる。そのくせ、力を込めても砕けたりはしない。どんなに小さなかけらでもだ。文字を書くようにして何かにこすり付ければ儚く消えてゆくのに、押さえつける力にだけは頑として抵抗する。これもつくづく得体の知れないものだ。
「技術班の連中に渡しはしないんですか?」
尋ねるモブリットへ、やっとハンジの視線が寄越される。外していた眼鏡を掛けなおし、んん、と歯切れの悪い返事である。
「どーしよっかなぁ、って感じだねぇ。ちょっと自分で出来るところまで調べきりたい感じはするし」
「餅は餅屋、ですよ。なんだかんだで彼らは優秀ですし、とっととお渡ししたほうが」
「ま、そうだよね。この一週間、色々やったけどさーっぱりわかんないしね」
その言葉どおり、帰還から早一週間が過ぎていた。班長としてのこまごました業務を片付けたあとは、ハンジは研究と称して自室に篭りきり、それからずっとこの岩屑と格闘していた。強酸につけてみたり、煮たり焼いたり叩いたりと数々の拷問を加えたが、どれ一つとしてこちらに応えてくれるような反応はない。それは自身の知識不足の所為も否めないことはハンジ自身も痛感していることだが、そこで折れるような神経などは生憎持ち合わせていなかった。しかし、効率を考えることは間々ある。ここまでやって一つとして成果が上がらないのであれば、手段を変えねばならないということだろう。ハンジが肩を竦め、指先で摘み上げていた欠片をそっと置きなおした。
「癪だけど話は通してみるよ。彼らは厭とはいわないだろうしね。で、なんだっけ、君の話って」
「え、ホントに聞いてなかったんですか?」
「いやだなぁ、聞いてたよ。でもちょっと忘れちゃったからもう一回お願い」
ち、と補佐の舌打ちである。ですから、と彼が再び口火を切ったとき、ふいに締め切ったドアから軽いノックの音が響いた。
「はい、誰?」
「失礼します、医療棟の者です」
若い女性の声でそう返事があった。小首を傾げつつ入出を許可すると、控えめに戸が開き、いかにも看護婦らしい穏やかな顔の女性が現れる。面識のない相手にどなた? とハンジが尋ねる前に、ほら、と女性がなにやら後方に呼びかけた。そして先程より押し開かれた戸から、おずおずと華奢な身体が滑り出てくる。
「あ!」
「ちゃん、」
班員二人に名を呼ばれた少女は、恥ずかしそうに小さく笑った。傍らの付き添いである婦人の裾を握りながら、こんにちは、と少女らしい澄んだ声が響く。
「この子がどうしてもご挨拶がしたいというものですから。助けていただいたお礼が言いたいと」
「わがままを言って、連れてきていただきました。あの、本当に、助けてくれてありがとうございました」
ひょっこりと小さな頭が上下する。皮膚病を広げない為の措置としてその髪は刈り上げられ、地肌が見えるほどの五分刈りになっている。見るからに貧相なその様子に兵士二人は思わず口をつぐんだが、やがてハンジがの前で膝を突き、いがぐりのような頭をわしわし、とこね回した。
「いいんだよぉ、お礼なんて! 元気になったみたいでよかった。もう出歩いて平気なんだね?」
「はい。あんまり動き回ると叱られるので、こうして看護婦さんと一緒に、毎日ちょっとだけ」
「ちゃん、がんばってるもんね。積極的に動いてくれるので、萎えた足が戻るのも早いんですよ。今はたまに私たちを手伝ってくれたりもしますし」
「へえ、そりゃすごいや。包帯巻いたりとか?」
ハンジの台詞にが恥ずかしそうに笑って首を振った。はにかみ、そのまま口を噤む彼女を見かねてか、看護婦がやんわりとその頭を撫でる。
「配膳、とかですね。一緒に運ばれてきた方々はまだ怯えが抜けきれないので…、ちゃんなら平気な方も多いんですよ」
「そっか、大役だ」
がんばって!とハンジが親指を立てる。モブリットも屈み、小さな頭を撫で激励する。微笑んでそれを受け入れながら、あの、とが小首を傾げた。
「あの、あのひとはいないのですか」
「あのひと?」
誰だろ? と小首を傾げるハンジが脳裏にエルヴィンを思い浮かべると同時に、が言いにくそうに付け足してくる。
「黒い髪の、ちょっと、少しだけ…怖そうな顔の、」
「ああ、リヴァイ? 彼はねぇ、基本的に殆ど外にいるからねぇ。なに? 彼に用事?」
「いえ、その、お礼を言いたかったんです。よくしてくれたから」
「え、あいつが?」
うそぉ、とハンジが大仰に仰天する様にくすくすと笑っただったが、それが喉を刺激したのか、やおら咳込み始める。それまで穏やかに微笑んでいた付き添いの看護婦が一転、険しい顔で喉を抑えるを覗き込んだ。
「ここまでにしましょう。まだ万全じゃないんだから」
「…はい、」
素直に頷いたが大きく深呼吸をして、再び顔を上げた。咳込んだせいで涙の滲む瞳を細め、ハンジを見ながらうすく微笑む。
「会えないのは残念だったけど…、あのひとにも、伝えてもらえると嬉しいです。毛布をありがとうって」
「うん、わかった。必ず伝えるよ。体が空けば君に会うようにもいっておくからね」
素直に聞くかはわからないけれど、とは胸の内に呟いて、嬉しそうに頷いたの頭を再びかき混ぜる。そのまま二三と言葉を交わして、少女は看護婦とともに病棟へ戻っていった。その背が見えなくなるまで揃って手を振り見送り、やがて、ふう、とどちらともなく息を吐いた。
「元気になってよかったですね」
モブリットの台詞に、ハンジが大きく頷いて返す。
「うん、ホントに。やっぱあれくらいの女の子はかわいいなぁ。でもちょっとかわいそうだよね、あんなふうな頭にされちゃって」
「回復が早い分、髪が伸びるのも早いですよ。その間は帽子でも被っていればいいでしょうし」
「なら、退院祝いには帽子がいいね」
気が早いですよ、という補佐の苦笑を貰い、ハンジがそっか、とつられて笑う。先ほどまでの会話はそこで断ち切られ、彼らはそのまま、調査兵団らしいこまごました班内の話に切り替えられる。カルノのことも、のことも、それきり話題には上がらなかった。
岩から救出された人員のうち十余名が死亡したとの一報が齎されたのは、それからまもなくのことだった。