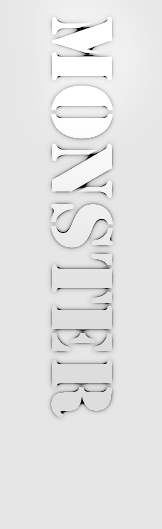MONSTER
8.真に名を持たない
立ち上がった団長に倣い、リヴァイやハンジも椅子を引いた。朽ちかける家屋からそぞろに退出する。金錆が目立つ古いドアを押しあけ、外にでると、見張りに立っていた班員が黙礼して居住まいを正してくる。先頭をエルヴィン、ハンジ、リヴァイと続き、補佐の三名が退出したときだった。暗がりに佇んでいたらしい誰かが、あの、と声をかけてくる。
「班長」
応じたのはルカだった。その言葉通り、やや身を屈めながら姿を現したのは、索敵班兵士を束ねるネスである。ルカにはおう、と気安く返事を返し、そのまま、聊か緊張した面もちで立ち止まる面々に向き直った。頭に巻いた布を乱暴に外し、敬礼する。
「突然申し訳ありません。その、こいつが団長に呼ばれたって聞いたもんで。もしやなんかやらかしましたか?」
こいつ、と言いながら長身のルカの頭を掴み、無理矢理に下に押し下げる。特に抵抗もなく素直に腰を曲げるルカの背を乱暴にこづき、小首を傾げる面々に焦った班長が唇を舐める。
「すんません、なんかやらかしたんだったら俺の責任です。こいつ、礼儀がなってないでしょう。常々言ってんですがなかなか直らなくって。元々ちょっと感情が出にくいところがあるんですが、悪気はないんですよ。失礼があったんなら謝ります」
おら、とルカの頭を再度地面に向かい押し込む。そのまま、彼も深く腰を折り、すいません、と叫ぶように言う。エルヴィンはちら、と左右の面々をみるが、ハンジは小首を傾げ、リヴァイは興味のなさそうな顔であらぬ方を見遣るだけだ。エルヴィンが笑い、ネス班長の肩を気安く叩いた。
「いや、特に何かあったわけではないんだ。どころか、彼はお手柄だよ。索敵班らしい俊敏な行動と判断で民間人の救出に尽力したんだ」
「え、」
詳細は知らなかったらしいネスが瞠目し、掴んだままのルカの頭を今度は持ち上げた。上背のあるルカの顔を見上げながら、そうなのか、と問うが、当の本人は無表情のまま、特に何を言うでもない。色のない目がちら、とエルヴィンを見る。無言の訴えを汲んだかのように、団長は再び小さく笑った。
「私からも礼を言うが、よくよく労ってあげてくれ。ご苦労だった」
「は」
ルカが短く返事をし、小さく頭を下げた。それに倣い、ネスも慌てて腰を折り、暇を告げて去ってゆく。おら、とまた乱暴にルカを追い立てるが、歩幅の違いからか、そう経たないうちにネスがルカを追う形になる。何事かを口喧しくがなり立てながら去ってゆく索敵班員を見るとはなしに眺めていた一行は、リヴァイが再び歩を進めたことにより現実を取り戻した。兵士長様はそのまま、無感動に広場の篝火を目指す。
「知らなかったなぁ、索敵班にあんなに優秀なコがいたなんて」
ハンジがあとに続きながら、誰に言うでもなしに暢気な声を上げる。確かに、と頷くのは律儀なその補佐だ。
「判断も早いし躊躇もない。手付きも鮮やかで無駄がなかったですね。まあ、それでこそ斥候というべきなんでしょうが」
「彼はネス班長の秘蔵っ子だよ」
エルヴィンが朗らかにそういった。秘蔵っ子、と思わず繰り返すペトラへ穏やかに微笑む。
「あのとおり優秀だが、少し性格に難があるらしくてね。訓練兵時代の適正試験で不可を出されかけたところを、ネス班長の熱烈な勧誘で索敵班兵士になったんだ。彼を採るのを疑心暗鬼だった連中はさぞ歯噛みしただろうね。蓋を開けてみれば、斥候班の損耗率は大幅に減少したわけだ」
「へぇ」
誰とはなしに、感嘆の吐息が漏れる。実際にその手腕を目の当たりにしたハンジとモブリットは一入だった。なるほど、と頷きあっていたが、やがてハンジが小さく小首を傾げる。
「でも、性格に難あり? そんな感じしなかったけどなぁ。まぁ確かに無表情なコだなぁとは思ったけど」
「そうですね。どなたかと違って突飛な言動をされたりはしませんでしたし」
「でしょお。うーん、ネス班長が厳しいのかなぁ? まぁ彼、礼儀に煩いところがあるしね」
聞いているのかいないのか、モブリットの皮肉をあっさりと流したハンジが己の言葉に頷いて、話は終わるかに見えた。それまで黙っていたリヴァイが徐に鼻を鳴らす。
「適正試験な。あのわけのわからんクソみてえな問答を繰り返すやつだろ」
「一応、精神科医の指導の下に作成された心身の適正を測るものなんだがね。そういえば、お前は途中で投げ出したな」
「あんなモンに長々付き合ってられるか」
「えー、そんなのでも通るのに、ルカは駄目だったてこと? なーんか眉唾くさいねぇ」
「そういうこった」
は、とリヴァイが吐き捨てるように行ったと同時に、一行は灯りの強い拠点中央へ到着した。
調査兵団の夜明けは、月が沈み、太陽が昇るちょうど中間に始まる。見張りの兵だけではなく、仮眠をとっていた全員が示し合わせたようにきびきびと動き出し、手早く荷造りをして出立準備を整える。帰還の際も大まかな陣形は崩さず、中央に指揮系統を置き、菱形に展開して渡り鳥のようにすばやく、正確に壁内を目指してゆく。いつもなら行きと違い帰りは兵站の物資がない分身軽なのが常だったが、今回はそうも行かない。食料や物資などより遥かに慎重に運ばねばならない相応の人員を載せた荷馬車は、中央に陣取る団長とともに手厚い護りを享けて進むことになった。護衛には、そのエルヴィンの声が掛かったルカが当てられる。初列、索敵班兵士を裂くことに対してその班長であるネスがかなり渋ったが、周囲に説き伏せられて最後はしぶしぶと頷いた。ルカの肩に乱暴に腕を回し、何事かをきつめの相貌で囁く。対する彼が相変わらずの無表情で頷くのを見てから、列に戻ってゆく。よほどの執心ぶりか、と周囲は失笑したが、当の本人は何も言うではなく示された位置についた。
天候は生憎と芳しくない。早朝にも拘らず、泥濘んだ風が全身に纏わりつくように緩く吹いている。指先は冷えるのに、体は粘つく汗がじわじわと噴出してくる。荷馬車に詰められた人々は、相変わらず声一つ上げずに大人しいものだった。岩内で遭遇した当初とはまるで真逆である。あまりの静かさによもや死んでいるのではないか、と危惧されたが、瞬きを繰り返す瞳と僅かに上下する胸を見る限り、どうやらそうではないらしい。
昨夜夜半、見張りと世話を任された兵士たちが残り少ない食料をどうにか工面して彼らに分配しようとしたが、誰一人として受け取ろうともしなかった。顔も上げず、返事もしない。も静かに首を振った。おなかが空いていない、と小さな声があったが、あの環境下で空腹でないはずがない。最年少の彼女を慮って、一口だけでも、と追いすがる兵士の手からぞんざいに携行食料を奪ったのは、案の定カルノだった。彼だけは最初から横柄な態度を崩さず、水や食料、果ては毛布やら寝床やら、思いついたものを片端から要求しては悪口雑言を垂れ流している。きつめに窘められれば、その苛立ちの矛先は幼い少女へ向けられる。たまりかね、彼女だけでも別の場所へ移そうという意見が出たが、それは本人が固辞した。どう説得しても、ここにいます、と譲らない。そうなるともう下手に近寄れず、荷馬車の面々はやがて遠巻きに様子を見られるだけになり、出立直前までその状況は続いた。
「帰路とはいえ、あまり速度を落とすわけにもいかない。長く、辛い道程になるかもしれないが、どうにか耐えて欲しい」
悪臭立ち込める荷馬車を覗き込みながら、一切の顔色を変えずにエルヴィンが微笑みかける。案の定、人々から返事は返らない。暫くの間、しんと静まり返るその様子をつぶさに観察していた団長だったが、やがて納得したようにひとりでに頷き、きびすを返した。目張りの布を締めかけた、その時である。
「うぁああああああぁぁああああ、ぁぁああぁぁああああああああ」
奇声、というしかない叫び声だった。咄嗟に見張りの兵士が二人、エルヴィンの前に飛び出してくる。身構える彼らの肩を叩き、目線で促してから、今しがた締めたばかりの布を捲る。砂埃や風雨に耐える分厚い布をよければ、途端奇声は耳を劈くものになった。荷馬車、一番奥、隅に陣取る陰から発せられている。人影が邪魔をしてどんな人物かはよく見えないが、しゃがれた男の声だ。それまで無表情だった人々が、競うようにしてその人物から距離をとろうともがいている。だがやはり、彼らからはうめき声の一つも上がらない。必死の息遣いだけが木霊する車内は饐えた臭気と相俟って俄かには反応しがたい絵図だった。叫び声を上げ続ける男の陰形を見つめ、エルヴィンが口を開きかけた時、ふと、華奢な影が立ち上がった。だ。
「だいじょうぶです」
その台詞は明らかに、立ちすくむ荷馬車外の面々へ向けられていた。彼女はそのまま、怯える人々の波を掻き分け、奇声を上げ続ける影の元へ向かう。人垣が割れ、隙間が出来た。そこには枯れ木のような手で頭を抱える老人がいる。方々に伸びた白髪の強い頭を掻き毟り、我武者羅に首を左右に振っている。はその老人へ手を伸ばし、腕ごと頭をぎゅ、と抱きしめる。
「この人は、ずっとこうなんです。暫くすれば収まります。わたしがちゃんと見ておきます」
だから、大丈夫です。
そういいきり、は幼子にするようにして、老人の頭を優しく撫でさする。血が滲みそうなほど歯を食い縛る老人の奇声は、やがてその言葉どおりに徐々に収まりつつあった。ひゅう、ひゅう、と隙間風のような呼吸音が漏れている。
「おい」
カルノだった。彼は荷馬車後方の隅で足を投げ出し座っている。その彼はエルヴィンを下から睨みあげ、ぞんざいに顎をしゃくった。
「いいから行けよ。お前らがいるからあれが騒ぐんだ。このクソガキが面倒見るつってんだから、つべこべ言ってないでとっとと出発しろや」
「お前…!」
曲がりなりにも兵団団長に投げつけるべき言葉ではない。激昂した団員がたまらずといったようにカルノの胸倉を掴みあげる。彼は皮肉げに笑うだけで特に抵抗もしない。それを押し留めたのは、侮りを受けた団長である。歯噛みする団員に穏やかな笑みを授け、その顔のままカルノに向き直る。
「君がカルノ、とやらだね」
「だったらなんだ」
「なるほど、聞きしに勝る勝ち気ぶりだ。あのご老人は本当に放っておいて大丈夫なんだね?」
「ありゃ、いっつもああだよ。いきなり叫んで、疲れたら勝手に眠りやがる。反応するだけ無駄だよ」
「そうか」
ならいい、そういってエルヴィンが下がる。カルノは再び荷馬車の隅へ乱暴に腰を押し付ける。硬い木板のすわり心地を誰とはなしに口汚く罵っている。では、とエルヴィンが再び口にし、今度こそ荷馬車の目張りは硬く閉じられた。男の奇声は弱く、細くなり、やがて、意識しなければ捕らえられないものになった。
エルヴィンは一瞬顎に手を当て自身のつま先を見つめていたが、やがて瞬きほどの刹那で何事もなかったかのようにきびすを返した。行こうか、と麾下の面々へ気安く声をかける。恐れ多くも団長命令を受けた人々は、やがて声を張り上げながら陣形出発を告げ始める。
「大丈夫でしたか?」
馬へ乗り上げるエルヴィンへ女性兵士から気遣わしげな声が掛かった。彼女は、先ほどエルヴィンの前に躍り出た一人である。不安の中に怒りがちらつく彼女に薄く微笑み、団長は頷く。
「少し驚いただけさ。なんてことはないよ」
「しかし、ものには限度があります。今は救出すべき民間人でしょうが、壁内に無事戻った暁には憲兵団に叩き出すべきです」
「はは、手厳しいな」
快闊に笑う団長に、笑い事ではありません、と他の兵士からも苦情が飛ぶ。すまない、と素直に謝罪する団長は一度大きく肩を回し、これから始まる長い乗馬に身体を備え始めた。他の面々も次々に己の愛馬を操り、馬脚を確かめる。そんな様子を見遣りながら、エルヴィンはちらと後方の荷馬車を振り返った。
「確かにリヴァイの言う通り、面白い二人だ。仲が悪いわけではなさそうだな」
鐙を踏みしめ、馬の横腹を蹴る。高い嘶きが上がり、調査兵団の帰路が始まった。