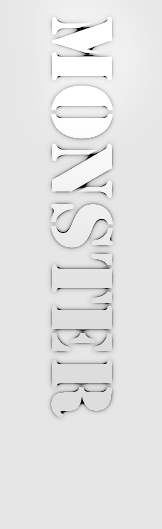MONSTER
7.落日
まもなく日暮れがやってきた。とても四方を壁に囲まれているとは思えないほど、太陽はきちんと地平の彼方へ姿を隠してゆく。橙色が荒くれた土地家屋を満遍なく染め抜く中、衰弱した人々を乗せた荷馬車一向は無事廃村へ辿り着いた。
陽が沈むと巨人との遭遇率は日中のそれと比べ圧倒的に低下する。しかし過去夜間の襲撃がなかったわけではない。夜通し火を焚き、立体機動の性能を生かす背の高い拠り所の近くに見張りが欠かせない。そのため、壁外調査中の野営はこのように廃村をキャンプ地として利用することが殆どである。放棄された風車跡に詰めていた団員が、一行到着の旨を告げる。伝令は瞬く間に調査兵団団長・エルヴィン・スミスまで届いた。彼は今、他の班員数名と共に朽ちつつある厩舎にて馬を労っていたところである。
「岩に人…か。数奇なものだな」
顎に手を当て、エルヴィンがひとりごちた。最初の一報が齎されたとき、彼が居た場所は新しい兵站拠点となる同じような集落跡付近だった。備蓄物資を積んだ荷馬車の到着と同時に最初の一報を聞き、一陣としてリヴァイを差し向けたのが功を奏したと第二の報告で聞き、そのまま取って返して今に至る。随分と馬に無茶をさせた強行軍だったが、いつもきちんと分けられている彼の髪に乱れはない。そのくせ、付き従った人馬共に疲労の色が濃く、頓着なく団長自ら面倒を見る始末である。
「団長、あとはもう私たちでやりますから、先に分隊の様子を見に行かれてください」
飼葉を与えている女性兵士がやんわりと促すも、エルヴィンは顎に手を当てたまま片手で愛馬の鼻面を撫でるばかりで、特に何も言わない。思案に耽っているのか、聞こえていないのか、滅多に崩されない表情はいつもと同じ生真面目そうなままである。反応の無い彼もまた疲れているのだろうと判断した女性兵士が馬に向き直ったとき、やっとぽつり、といったようにエルヴィンが零す。
「私が見に行かなくても、向こうから来るだろう」
「え?」
「時間の問題だと思わないかい?」
視線は動かさないまま独り言のように呟かれるエルヴィンの言葉は、大仰な足音群によって応えられた。顔を向ければ、怒り心頭と言った風のリヴァイを先頭に、見知った人員がこちらへ足早にやってくる。もっとも、他の面々からしてみればリヴァイの表情はいつもと寸分違わない。いつものように下から睨みつける様にして相手を見、目が合えば挨拶代わりの舌打ちである。此処に不機嫌さが混じれば、口を開くといつもの倍ほど罵詈雑言を垂れ流すのだ。
「この馬鹿が…何をのんきに馬の世話なんかやってやがる。お前は一介の兵士か? 自覚がないなら団長なんざやめちまえクソが」
「やあ、おかえり。どうだった例の岩とやらは?」
「…このクソ眼鏡に訊け」
大らかな笑顔によって一刀両断に伏されたリヴァイは、決まりの舌打ち一つでぞんざいにハンジを指し示した。指名されたハンジが苦笑交じりに進み出る。一頻りの労いを終え、それぞれが粗方のあらましを伝え終えた頃には、辺りはすっかりと夜になった。
廃村の方々にごうごうと灯が燈る。八方を交代で兵が見張る為に、自然拠点は村落の形状に拘らず円状に展開され、見張りの番を待つ兵士は皆円の中心に集まり、篝火の傍で簡素な食事を取るもの、仮眠を取るもの、様々である。巨人の脅威も少なくなる夜半を迎えているからか、兵の間では談笑する気力も残っているようだ。漣のような笑い声が時折静かに響いてくる。束の間の穏やかさの中を横切り、分隊長以上は全て損壊の少ない大きな平屋の中へ入った。
既にモブリットとペトラ、ルカが後ろ手に腕を組み、明かりの薄い室内の壁際で待機していた。元は講堂か集会場だったのか、がらんどうとした造りの中に木組みの長テーブルと椅子だけが備えられた、簡素な室内である。壁面は剥き出しの石造りで、朽ちた煉瓦があちこちに屑となって落ちている。灯りは欠けた飾り皿の上に置かれた燃材と、元からここへ備えられていただろう燭台が一つずつ、テーブルの上で頼りなく揺れていた。お互いの顔が近寄って辛うじて判るくらいの薄暗闇の中、無言のまま各々が席につく。壁際の面々は直立したままである。
いきなりに口火を切るものは居ない。暫し、場には静寂が落ちた。平屋内は割れた硝子窓以外は閉じられており、万が一外に異変が起きた場合を想定して戸口横に班員をひとり置いているが、口の堅い寡黙な班員である。影すら感じさせずに、格子越しからは遠くうそうそとした僅かな人声が流れてくるだけである。長いこと放置されていた所為か、室内は胸をつく埃の臭いが強い。リヴァイがふいに隊服の胸ポケットから綺麗に畳まれた手巾を出し、静かに口に当てた。それを見計らったように、エルヴィンが小さな溜息を吐いた。
「俄かには信じられん話だ。マリア陥落後からずっと、彼らはあの岩の中で暮らしていたということか?」
低く、自問するような声音に対し、斜向かいに座ったハンジが肩を竦めた。
「聞き出せた限りじゃそのようだよ。全員衰弱もひどいし、意思も少し混濁してる。今までそういう人間を見たことがないから何とも言えないけど、ま、まともな状態じゃないことは確かだね」
「ふむ…中は調べたのか?」
「ン、まぁ、大体だけど」
エルヴィンの視線はハンジに固定されている。言葉少なに次を問う彼に、ハンジは左手で頬を摩りながら、一拍をあけて口を開く。
「広さは結構あったね。大まかに見積もって平均的な家屋の五、六軒分くらいかな。最初の人数からはだいぶ減ったみたい。隅のほうに、丁寧に遺骨が重ねられてた。食料も隅のほうに纏めて置いてあって、我々の携帯口糧とそう変わりない内容でね、残り少なかったけど。特筆すべきところといえば、酵母があったことかな」
「酵母?」
「そう、あの酵母。それも結構大量。これがあったおかげで彼らは一年近くも岩の中でまんじりとしてられたってわけだろうね」
「ほう」
エルヴィンがテーブルの淵へ片肘を突き、顎を乗せた。分厚い掌が口元を覆う。
「あの酵母は確かシーナの商会連中が独占していたな。市井に流れているものをいくつか見たことはあるが、どれも粗悪品の小さなものだった」
「そうなの? 私は正規品しか見たことないなぁ。その私が見た感じでは、本物と相違はなかったよ」
「そうか、それは困ったな」
ちらともそう聞こえない声音で言い置いて、エルヴィンはふうと一息、溜息とも呼吸ともつかない呼気を吐いた。そこで始めて、ハンジから視線をはずす。次に向かった先は沈黙したままのリヴァイである。
「しかし、衰弱している割には、聞く限りでは秩序ある暮らしぶりだな。劣悪な環境下で備蓄の食糧が残存していた、遺骸を纏めてある、他は?」
「正気を失っていないヤツが二人居る。貧弱な男と小汚ぇガキだ」
エルヴィンから水を向けられ、リヴァイは椅子の背に行儀悪く凭れ掛かる。口元の布をきちんと畳みなおし、仕舞いながら、片足を曲げ椅子の縁へ乗せる。
「男はガキを甚振ってふんぞり返ってやがった。ガキの方は従順そうだが、俺に楯突く気概はあったな。日常的に嬲られてたわけじゃなさそうだ」
「男と、子供か…、親子か?」
「似てねぇ面だったな。どっちもクソまみれでよく見ちゃいねェが。その男、王都商会の人間を自称していたぞ」
鼻で笑うリヴァイの椅子が負荷に耐えかねて耳障りな音を立てる。軋む木組みの音は揺れる荷馬車の歯車が重い荷を運ぶ音と同じだ。
岩の中より救出した人々は、促しても荷馬車を降りようとはしなかった。補給物資を詰め込む大型の函とはいえ、それなりの人数が入れば文字通りすし詰めの状態になる。息すら苦しい状態で、彼らは文句一つ言わず黙して俯き、じっと身を丸くして座り込んでいた。ヘルというあの少女も似たような状態だったが、荷台の後方に陣取ったカルノは違った。彼は拠点に着くなり真っ先に荷台を下り、好き勝手に歩き回っては団員に注意され、相手かまわず噛み付くを繰り返していた。不潔な身なりが気になるのか、冬季ではないが夏季でもない今時分に、雨ざらしの井戸水を頭から被るなり後は地べたで不貞寝を決め込んでいる。王都のごろつきにも勝る悪漢ぶりだと、彼を見張っていた何人かの兵から苦情が出ていた。
大まかにカルノとヘル、二人のあらましを聞き終えたエルヴィンがふむ、と口の中で呟き、指先が口元を撫でる。
「男の話が真実だとすれば、その大岩は少なからず商会に縁のあるもの、ということになるな。そんな情報をわざわざ我々に開示してなんになると思う?」
「さあな、見当もつかん。ただ、普通は吐くにしても他にもっとマシな嘘がある。つまりなにかしら益があるんだろ」
「もしくは目的ね。助かりたい一身で出た台詞って線もありっちゃありだけど、こっちの身分を明かした後であの態度だからねぇ、それも薄いか」
リヴァイ、ハンジが順に述べるのへ、エルヴィンは何度か頷きを返し、口元を覆う指先を退けた。腕ごと降りた机の上から、カツ、と爪が木を弾く音が鳴る。三度、エルヴィンの視線は流れ、今度は壁際で不動を保つ補佐二名と索敵班兵士一名に注がれた。薄暗がりの中、調査兵団団長の視線を受け止めるペトラとモブリットの顔は固い。ルカは、相変わらず読めない無表情で宙を見つめている。
調査兵団が如何な人員不足とはいえ、役職を持たない兵士が団長と接する機会は少ない。入団式の激励で声をかけられるか、せいぜいが伝令や訓練時に二、三言葉を交わすだけである。ましてや、音に聞こえた人物といえど、見目は穏やかで紳士的な風情だ。分かり易い鬼教官のように怒鳴るような声も出さず、滔々と話す口調も彼の風評を裏切るに一役買っている。補佐の二人が視線を向けられただけで息すら慎重に身を引き締めるのは、日頃から来る条件反射の部分が強い。だが、それを差し引いたとしても、向けられた視線によって場には確かに有無を言わさない緊張が強いられた。ピンと張り詰めた木綿の糸へ徐々に火種が近付いてゆく、そんな想像を駆り立てられるほど、決して狭くないはずの室内は息苦しい。その中であって、ルカの表情はぶれずに視線も泳がないのだ。
余程の胆力か鈍感か、全員が測りかねているところへ、エルヴィンが口火を切った。
「その男が岩の中で集団を纏めていたと見て、間違いなさそうかな?」
特定の誰かを指しての問いではない。ややあって、モブリットが応えた。は、と短い返事をよこす。
「少女と人々の怯えから察するに、かなり独裁性が強い人物が仕切っていたようです。他の面々にそのような気力は見受けられません」
「気力か。何人かと口を利いてみたのかい?」
「岩を発つ際、荷馬車へ誘導しながら声をかけてみました。慰労や憐憫、やや挑発とも取れる言葉もかけましたが、どれにも反応せずに黙して俯くだけです。移動時も同じです」
「岩を見つけたのは君だったね。確か、ルカだったかな」
漂うだけだった瞳が動く。姿勢は崩さず、僅かに床を踏み直しながら、索敵班兵士が敬礼を取り直した。
「ルカ・ティランです。班員他三名と南南東を警戒中に件の大岩を発見致しました」
「君はどう思った? その大岩は何のために存在し、かつどのような経緯で数多の人々が幽閉され、朽ちるに任せたまま放置されるに至ったのだろうか」
また沈黙が降りる。静寂は一定ではなく、隙間風が遠く談笑する班員の余韻を薄く運び、やがて儚く消えてゆく。面食らったのか、考えあぐねているのか、ルカの目線はエルヴィンから焦点をはずし、何処とも知れない虚空を見つめて止まっていた。椅子についた面々は微動だにしない彼を伺い、急かすでも、助けるでもなく、ただつぶさにその様子を観察している。容赦ない三対の視線の中、たっぷり一分以上を沈黙に費やした男は、やがて徐に唇を舐めた。
「檻、ではないでしょうか」
端的な言葉に聞き返すでもなく、エルヴィンが目線だけで先を促す。
「己の意思が儘ならぬ劣悪な環境に居住を強いられる行為は監禁、あるいは投獄です。容姿はどうあれ、人目に付き辛い奥まった林道の中、出入り口を塞ぎ、人間を囲う。それは檻ではないでしょうか」
「檻、か」
ふふ、とほぼ吐息の笑みが落ちる。
「なかなか面白い意見だね。では、その岩が檻だと仮定しよう。なぜそこへ彼らは詰め込まれていたのかな?」
「檻の目的は大きく分けて二つです。対象の身柄を拘束し監視するためか、もしくは周囲にとって有害なものを隔離するためか。彼らがどちらに属するかは自分にはわかりかねますが」
「では彼らが有害なものかもしれないと」
ルカが顎を引いたまま頷いた。
「可能性はあります」
斥候を担う若い兵士の返事を聞き、今度こそ団長は穏やかに口角を撓ませて、しっかりとした笑みを浮かべた。
「そうか。なるほど、よくわかったよ。ありがとう」
朗らかに礼を言って、団長の視線は補佐等からはずれ、再び朽ちかけるテーブル上に戻る。ペトラが堪え切れないような吐息を僅かにこぼす気配がした。
「では、彼らの処遇は壁内に戻ってから考えるとしよう。その男がいうとおり、彼が真実商会の人間であればこちらから問い合わせて何ら問題もないだろう。相応の感謝もされるかもしれないな」
「わお、そりゃ期待しちゃうね」
ハンジが肩をすくめてこぼすのに、エルヴィンが苦笑いの顔で頷き返す。
「我々への風当たりはそうそう変わらないだろうがね。では、予定には少し早いが今回の壁外調査は本日を持って終了。明朝より順次帰還を始める。救出した人員は今と同じく荷馬車に載せて運ぼう。あとは、」
エルヴィンが言葉を切り、つい、と淡青い夜闇を映す窓硝子をみる。経年の埃に塗れ、その表面は繊毛のようにけぶっている。
「私は少しその男と話してみたい気もするが…、まあ、それも様子を見るかな。今話したところで噛み付かれるのが関の山のようだ」
「変人同士気が合うかもしれんぞ」
「そうだといいかな。気心が知れれば素直に口を利いてくれる可能性もあがるだろう」
リヴァイの皮肉を難なく切り替えし、一笑いして、エルヴィンは椅子を引き立ち上がった。それを合図に短い会議は終わりを告げる。