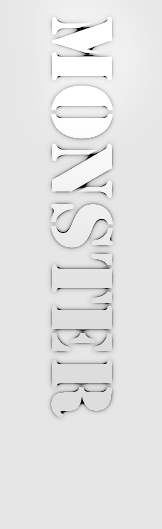MONSTER
4.巌となりて
一口に外周、と言っても、巨岩の外周は平均的な家屋を五棟以上つき合わせた大きさである。仔細に調べるには時間が足りず、大まかな確認だけになるかに見えた。実際、ハンジもそう見積もっており、現地での調査はある程度を持って引き上げる算段だった。散らばった小石を大小かまわず拾い上げ、壊れ物を扱うかのように慎重に仕舞ってゆく。これを持ち帰り、技術班と共にその分析に勤しむ想像を膨らませながらの作業に没頭し、岩表面の観察はややおざなりになっていた。そこへ一通りの検分を終えたリヴァイが現れ、だんだんと鼻息荒くなるハンジの後頭部目掛け、ずっと岩の表面を叩き続けていた柄を同じように振るった。ゴツッ、と鈍い音が響く。
「ぃいっったぁあああっ!!」
「おい、いいか変態、よく聞け」
「なにすんのさ!聞くけど!」
「こいつの中身は空洞だ」
ぞんざいに親指で指し示す先は件の巨岩である。たっぷりと十秒ほど考え込んだハンジは、それからまもなく文字通りに飛び上がった。
「空洞!? え、中身がない? からっぽてこと!?」
「そう言っている」
そっけなく言うなり、きびすを返し岩へ近寄っていく。ハンジの頭や岩を殴りつけたそれは、アンカーの射出とガスの噴出や調節、加え剣の柄も兼ねるいわば立体機動の心臓部だが、リヴァイは頓着なくまるでハンマー代わりに扱っていた。再度、岩壁を柄尻で殴りつける。音を確かめているのか、うっすらと目を細めた。
「斬りつけた時に思ったんだが、これだけの体積にしちゃ打撃音が軽い。元々そういう性質の岩なのかと確かめたが、叩く場所によってやや音が変わりやがる。道具がありゃ割れるだろう。ま、だからなんだって話だが…」
淡々と告げるリヴァイの後ろから、同じように外周を見て回っていたルカが早足で戻ってきた。彼も残りの替えも少ない刀身を抜き身で提げ持っている。一頻り斬りつけてきたようだ。わずかばかり刃先が欠けている。
「リヴァイ兵士長の仰る通りのようです。中に何かが詰まってる可能性もありますが、岩だけで出来てはいないようですよ。裏に妙な罅を見つけました」
「罅?割れてるの?」
「よく分かりません。隙間を斬りつけたら木片のようなものが出てきました」
「は?」
木片?と返す面々へ頷きつつ、彼は左手で握っていたものを差し出した。黒く、握りこぶし大の岩に見えたが、断面が明らかに岩のそれとは違う。ささくれ突き出した針のような繊維群は確かに木片のようだ。
ひとまずモブリットが受け取った。まじまじと見つめ、木ですね、と呟く。
「炭化…してるのでしょうか。いやに軽いですよ」
「石はけっこう普通の重さだよね。箇所によって材質が異なるってこと? だとしたらますます岩じゃなくなるよこれ」
またしてもハンジの顔が嬉々と輝きだすが、他の面々は何ともいえない面持ちでルカの寄越した物と岩とを見比べている。得体の知れない物体に対する薄気味悪さが勝ってきたのだろう。
「オイお前、これの場所は何処だ」
リヴァイがぞんざいに訊くのにも、ルカは眉一つ動かさずに頭を下げた。
「ご案内します」
剣は収めないまま、ルカがきびすを返した。それにリヴァイ、ハンジ次いでペトラとモブリットが続く。他の班員も恐る恐る後を追おうとしたが、ハンジが苦笑しつつその場へ留めた。
リヴァイらが先程歩を進めた左側ではなく、右側を半周以下進んだ先だった。一見すると岩の一部にしか見えない。しかし、地と接する部分から細かい亀裂が上へ走り、中ほどに大きな割れ目がある。この抉れはルカの仕業らしい。彼が走るひび割れを見て何とはなしに斬りつけたのだという。その所為か、罅というには聊か大きな亀裂が広がっていた。
有無を言わさず、電光石火の速さで再度リヴァイが剣を振るった。しなる硬質スチールの刃も今度は折れることなく、より深く広く、亀裂がえぐられる。その破片はモブリットの言葉どおり、まるで炭化したかのような木片だ。ぱらぱらと細かく飛散り飛礫となる。軽量な所為か皮膚に当たっても痛みはない。だが破片は擦れると皮膚や服を問わず黒い汚れを残した。リヴァイが一気に顔を顰めるのを尻目に、今度はハンジが揚々として剣を抜く。しかも両刀である。
「下がって下がって! 私がやるよ」
「分隊長、あんまり性急なのも考え物じゃぁ…なにがあるかわかりませんし」
「もうそろそろエルヴィンも追いつく頃合でしょ。早めに片付けなきゃね。あと私の知的好奇心がうずく!」
「いいからさっさとやれグズ」
リヴァイの激励とも罵倒とも知れない言葉が終わらないうち、ハンジが鼻歌交じりにはしゃぎながら斬り付けた。その残撃は見た目を裏切る衝撃で更に深く割れ目を広げる。二度、三度と手首を切り返しながら続けるにつれ、飛散る破片が増えてゆく。頬を掠め、隊服を汚すその木炭片に早々に辟易したリヴァイはとっくに距離をとって静観を決め込んでいる。もう指一本動かす気はないのだろう、ペトラが遠慮がちに何かを言い募るが、まるで聞かぬ振りだ。
対して、汚れなど歯牙にもかけぬハンジの猛攻が続いた。予想よりも岩ではなく樹の部分が多いようだ。亀裂は広がり、深くなってゆく。
「ハンジさん」
「ん?」
同じく、木片を浴びながら静観していたルカが待ったをかけた。そのままやんわりとハンジを下がらせる。一刀だけ提げ持っていた剣を逆手に構え、狙い済ました箇所に振り下ろす。
それはまるで、はめ込まれた木扉が蹴破られたかのようだった。消し炭のような木片が派手な音を立てて割れ飛び、内側に向かい歪ながらも四角い岩肌が倒れてゆく。たちまち、ただのひび割れは四方一メートル程度の穴となった。奥に向け、一面の暗闇が続く。それは夜に見る鏡のようだ。何も映さず、波打たず、ただとっくりと濃く厚く、決して向こう側を透かさない。
確かに中は空洞のようだ。かろうじて光が射す外との境目の付近には、外側となんら変わりない地面が続いている。砂と、土と、小石。それは地面だ。岩の中に地面がある。
「…いやはや、いよいよ持って奇っ怪だ」
ハンジが唇を舐めながら呟いた。提げ持ったままだった剣を仕舞い、早速穴倉へもぐろうと身を乗り出す。慌ててモブリットが押し留めようとする前に、傍らで穴を覗き込んでいたルカの無表情に変化が現れた。
眉根を寄せ、スン、と鼻をすする。おかしい、と唇が囁いた。
「この臭い…、覚えがある」
「臭い? する? まさかミケじゃあるまいし…」
「おい、お前らどけ」
首を傾げるハンジを、リヴァイが背中から乱暴に押しのける。
「妙だ。気配がするぞ。しかも複数だ」
「はぁ!? この中から!?」
「同感です。それにこの臭い…」
人いきれの臭いだ、と無を取り戻した表情でルカが続ける。ペトラが何かを察したように待機する班員のほうへ走り出した。モブリットも続く。ハンジに向かってだろう、無茶は駄目ですよ、と強く告げながら駆けて行く。
補佐の二人を尻目に、抜剣した兵士同士は構えたまま、視線を交わさずに口をきく。
「何故人間と分かる。巨人かも知れんぞ」
「そうかもしれませんが、自分は単純に知っている臭いです。不潔な人間が長い間同じところに居ると、こんな臭いの固まりになる。独特ですよ。他ではまず嗅がない」
「やけに詳しいなオイ。身に覚えがあるのか?」
「ええ、まあ。…俺も兵士ですから」
「奇遇だな、俺もそうだ。だがお前の言う悪臭の塊になるなんざ、死んでもごめんだ」
つらつらと言葉を交わす間にも、目の前の四角い闇に変化はない。ぬらりと幕が垂れ下がっているかのように、それはちらとも空気の揺れを感じさせない。ルカが頻りと発する臭いというものを、リヴァイはまだ嗅ぎきれていない。だが本人にとってそれは幸運である。人いきれの悪臭なぞ、彼にとっては唾棄すべき罪悪でしかない。
場は一気に緊張に包まれたが、状況は変わらぬまま、やがてモブリットが松明材を手に戻ってくる。次いでペトラが待機した班員を三名ほど連れてきた。道すがら、起きた事の経緯は簡単に説明したのだろう。駆けつけた三名は得体の知れない事態に顔を強張らせながらも、腹の据わった目つきで一様に穴倉を睨つけている。
「とりあえず、一本」
ハンジが呟き、補佐から受け取った松明を手早く点した。日中の元、煌々と燃え上がるそれを、勢いをつけて投げ入れる。
ぱっと、暗闇が弾けた。闇の中、ぬらりと尾を引きながら、赤い炎が転がってゆく。
「!? 兵長、今の…!」
「…どうやらこいつの言う通りらしい」
それは、誰の耳にも明らかな、女性のか細い悲鳴だった。
明らかに巨人の上げる耳障りなそれとは異なる、衰弱し、怯えた、弱者の声である。リヴァイが再度ハンジを促し、頷いたハンジが二度、三度と松明を投げ入れる。燃材はきれいに一箇所で並び、焚き火のように燃え盛る。だが、入り口から確認する限りでは、人の姿は見えない。
リヴァイが一度剣を振った。巨人相手ではないと見てか、双剣はやめ利き腕に一本だけを携えている。
「もういいだろ、入るぞ」
「うん…オーケー」
「先に行きます」
何かあってからでは遅い、そう言ってルカがハンジとリヴァイの前に躍り出た。立場にこだわらず、有事には真っ先に前線へ打って出る兵士長がどう出るかハンジが凝視するも、珍しいことにリヴァイは何も言わなかった。抜き身の剣を握ったまま、視線はとくと暗闇の奥を見つめている。
ルカが穴のふちに手をかけ、身をかがめながら中へ入ってゆく。次いでハンジ、殿をリヴァイが務める。暗闇に足をかけた途端、後続二名の頬が引き攣った。ここまで入るとさすがに分かる。確かに、猛烈な悪臭が漂ってくる。
「ペトラ、火を寄越せ」
「はい」
空いた腕を伸ばしたリヴァイが新たな灯りを手にした後、三人は完全に岩中へ侵入を果たした。全員ある程度までは匍匐前進もやむなしと考えていたが、淵を潜り抜け、さほどもしない内に立ち上がれるようになる。
先程ハンジが投げ入れた灯りは、先頭のルカの足元より三メートルほど向こうで燃え燻っている。燃材の先に滲み込ませてあるのは松脂のほか、獣脂と榧の実などを複雑に混ぜ合わせた、野戦用の燃料である。多少の雨や水などでは消えず、点る炎も強く太い。その松明が、周囲五メートルほどしか照らせていない。それほど、中の空洞は予想を遥かに上回る広さだった。
何を言うでもなし、三人はまず背を合わせ周囲を伺った。あれきり悲鳴は聞こえない。あたりは水を打ったように静まり返っている。しかし、ほぼ密閉に近い空間下であれば、軍人にとって凡夫の気配を探るなど容易なことである。もはや疑いようがない。害意の薄い怯えの塊が一緒くたになって奥の壁際にへばりついている。その数は少なくなく、必死に息を殺してこちらの一挙手一投足に注目している。
最初に三位一体を解いたのはやはりリヴァイだった。周囲の気配が脅威にはなり得ないと判断し終えたのだろう。握った松明をハンジに押し付けるや、彼は地面に転がる灯りへ頓着なく近付いてゆく。コツコツと軍靴の踵が地面を叩く。地表は硬く、当たり前だが草一つ生えていない、そこに小石は転がるが、砂利はない。掃き清められた古街道のように平坦な地面だ。
灯りの元へ辿り着くなり、二本をぞんざいに拾い上げる。まとめて持ち高く掲げると、近いところから順に、黒光りする壁面が橙色の炎に照らされてゆく。
そして、その声は降って来た。