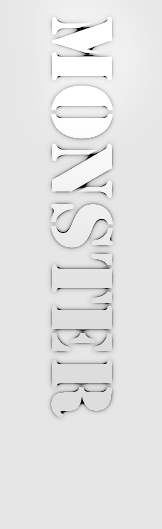MONSTER
3.しゃれこうべの歌
「あ、粗方、片付いたか…?」
班員の一人が荒い息の中、搾り出すように呟いた。顎先から薄く血の混じった汗が滴る。小枝が額を掠めたときに切ったのだろう。意識した途端、それはひりひりと痛みを寄越す。
大岩に群がっていた巨人が一斉にこちらへの攻撃を始め、場は一気に乱戦場と化した。戦闘が開始されて既に二十分以上は経過している。今なお途切れることのない蒸気の中、彼自身仲間とともに巨人三体を仕留めていた。分隊長クラスは実力が桁違いな所為かよく誤解されがちだが、一戦闘下における班員の討伐数にしては昇給ものである。事実、調査兵団という組織自体の方針も、もともと戦闘は避けてしかるべきものと律している。
だがその分隊長殿は、補佐の班員と金髪の先遣隊員を従え、先程見せた躊躇も何のその、我先にと群がる巨人を屠っていった。七体以上どころか、巨岩の円周に沿うように潜んでいた連中が次から次に現れる中、ただ一つともいえる不幸中の幸いは、そのどれもが大した図体ではないことだ。目測でも三から四、多くて六メートルくらいまでであり、動きもやや鈍い。ただ一体居た十メートル程の巨漢は真っ先にルカが攻め落とした。その彼と分隊長達は今、甲高い奇声を上げる残党狩りに徹している。
立ち込める巨人の蒸発煙は本来、煮炊きの蒸気と同じく少しの時間で解け消えるものだ。だが始末した数も多く、加え吹き荒ぶ風もない木立の合間である。視界は霧に包まれたように徐々に悪くなっていた。飛び交う兵士が起こす風圧が立ち込める煙を裂くが、それも僅かなものである。立体機動ならではの高速移動は白い視界に一瞬の影だけを残す。分隊長以下、班員達が退避と攻撃を繰り返す中、一足先に残りのガスが心許無くなった彼は、痩せた樹の上で眼下の動向を見守っていた。
剣戟の音と、ハンジの短く鋭い指示が聞こえる。見え辛いが、掃討は終わりを迎えているようだ。
(当初の予定とは大分異なったが、目的達成には大いに近付いた。あとはこの巨岩を調べてしまえばいい。増援は間に合わなかったが、それも直追いつく。ガスの補充もしなければならない。それにしてもこの大岩は一体何なのか。巨人どもが大群で群がっても何ともない。アンカーも刺さらなかった。かけらでも落ちていればいいが、それすらなければ面倒だ―――)
静まり往く心音と、徐々に落ち着いていく呼吸が耳朶を打つ。止め処ない思考に没頭する彼の前にまたうっすらと影がよぎった。
大きな影だ。
大きい、
「え」
バチン、と破裂音が響いた。羽虫を叩き潰すような、拍手を打つときの皮膚が撓み弾けるあの音。だがそれより何倍も大きい。音は頭上から、四メートル級の首を蹴り飛ばし、反動で飛び上がり、幹を駆け上がったまだその先。
「全員下がれ!」
ルカの声だった。咄嗟に仰け反った班員の鼻先に、血塗られた装備の残骸が降って来た。剣刃、柄と鞘、ひしゃげたボンベ、一番最後に、四肢ごと平らに押しつぶされた班員が落ちてゆく。
「一人やられた。自分が見た十五メートル級です」
あんなところに居たのか、と誰に言うとはなし、ルカが表情の消えた顔で頭上を見上げる。その頬に一滴、血が飛んでいる。
草を掻き分けるように木々を押しのけながら、それは無理やりに巨体を推し進めてくる。今の今まで一切気配をさせず、音を立てないまま、およそ隠れていたかのような、まるで唐突な出現だった。やかましい音を立てて若い痩木がなぎ倒されてゆく。頭髪の薄い、血走った目を持つ苦の表情の巨人だ。血が出るのも構わず、強く歯を食い縛っている。隙間からうめき声を漏らし、くの字に半身を屈めながら、それはいきなり拳を振り上げた。
「!?」
「ックソ!」
迎撃態勢を取った班員たちの予想を裏切り、振り下ろされた先は件の巌だった。腹の底に響き脳天へ駆け上がる、身の竦む大音が轟く。巨人は更に唸り声を上げながら、まるで憎い仇のように繰り返し繰り返し岩を殴り続ける。一切こちらを省みない。固唾を呑む班員の前で、骨が砕け、指が飛び、傷が再生する間も待たずに拳を振るう。一心不乱の猛攻に、当初びくともしなかった大岩にも変化が現れた。ぱらぱらと細かい小石が散り、竦むような音がだんだんと調子を変えてゆく。
「…分隊長」
「分かってる。ありゃ仕留めなきゃまずいね。しかし…」
歯噛みするハンジが柄を握る拳でボンベを叩く。既にガスの残量が危うい。加え、見渡す班員の顔には須らく拭い難い疲労が浮いている。ルカだけは一人変わらぬ態で刃の血を落としているが、彼一人に任せるわけにもいかない。一旦退くべきか。無理を押して仕掛けるべきか。再度逡巡に落ちるその刹那にも、巨人の猛攻は続く。
があん、と高い音が鳴った。大岩の表面に皹が走る。重ねてもう一撃が加えられ、欠片や小石とは言い難い、一抱えもある大岩が転がり落ちてゆく。同時に破片が飛散り、樹上に取り付く班員の身を掠めた。
慌てて交わす班員の中、ハンジのゴーグル縁へ硬貨大の石がぶつかった。顔を顰めながら、衝撃を殺すためそのまま顔を傾ける。上を向いた視界。多数の木々が薙ぎ払われ、生い茂る葉で隠れていた空が見える。うす曇だが雲に切れ目が走り、光が射していた。レンズ越しの所為かやけに目に滲みる。咄嗟に目を瞑った、その時だった。傍らのモブリットが身を固くした事を気配で悟る。ついで聞き慣れたワイヤの摩擦音、班員のどよめき、先程とは異なる巨人の叫び。それは瞬きに近い一瞬の間に起きた。
ハンジが目を開けば、そこには耳を劈くような悲鳴を上げ、両目を抑えた巨人がのた打ち回っていた。顔面から夥しい血が垂れ、岩に降り注ぐ。嗚咽を上げながらもがき額を岩に擦り付ける所為で、更に辺りに血が滴った。その巨人の頭が接する岩の上、すぐ傍に、いまや待ち焦がれたと言うに等しい小柄な人影がある。
「…うるせぇな。いちいち騒ぐなクソ野郎」
唾棄するが如く言い捨て、舞い降りた人影はそのまま再び宙に浮いた。無造作にアンカーを投げつける先はおよそ見当違いと見せかけて、その実慣性を利用し最短距離で巨人の背面へ回りこむ。的確な位置につくや、唐突にワイヤの巻き戻しをやめた。重力に自重を加えて墜落しながら、しなる双剣が巨大な首筋を凪ぐ。見事なまでの種子型に切り落とされた肉が飛ぶや、叫び続けていた本体からぴたりと奇声がやんだ。力なく崩れ落ちる端から蒸気が吹き上がり、三度視界は濃霧に包まれた。
もうもうと上がる煙の中、辺り全てを切り裂くような鋭さで舌打ちが聞こえてくる。馴染み親しんだお決まりの癖を耳にし、呆気に取られていたハンジが盛大な歓声を上げた。
「リヴァァァアアイィィイイッ!! 来てくれると思ってたよぉおおーーー!」
少ないガスを吹かし、ハンジが駆けつけた人物に瞬速で飛びかかる。しかし相手は身軽に交わし、再び血反吐に汚れた巨岩の上に降り立った。そのまま、眼下のハンジを処刑人のように見下ろしている。
「オイコラまぬけ…汚ぇ手で俺に触るんじゃねぇよ」
「ごめんよだって感動したんだもーん! 信じてたけど遅すぎるからまさかのまさかかもとか思ってたしねー!」
「お前らがクソ判り辛いところに居るからだろ。何なんだ此処は」
「まだわかんなーい!」
「…舐めてンのか」
冷え切った顔つきのまま、増援に駆けつけた兵士――リヴァイは、鈍らとなった刃をハンジ目掛けて投げ棄てた。笑いながらあっさり交わしたハンジの傍に、慌ててモブリットが降りてくる。次いでルカ、班員たちが続く。やや間を置いて、今度は後方から騎乗した兵たちが姿を見せ、立ち込めていた蒸気の霧散と共に、場は俄かに活気を取り戻していった。
増援に駆けつけた班は少ないながらガスと刃等の補給物資を持参していた。併せて、同士の亡骸を包む特殊な布の用意もあり、殺された班員は速やかに回収された。圧死の所為で顔も分からなくなってしまった彼は棒状に包まれ、四肢の破損をなるべくわからないようにし、骨になってから遺族の元へ戻される。肉はなくなるが、欠損の少ない骨が戻るのは珍しいことではある。大抵、腕や脚の一部しか回収できないことが多い。
些かの哀悼と当座の補給も無事終わった頃、運の良い事に先ほど逃げた馬も戻ってくる。分隊班員は皆、武器と移動術を取り戻し一息をついた。壁外での物資の枯渇はそのままイコールが死だ。貴重という言葉では言い足りないほどである。その所為か、団長命令を請け駆けつけたリヴァイの表情は何時にも増して冷ややかだった。あらましを聞き終えた彼は血糊を拭き落とした腕を組み、指が苛々と肘を叩いている。
「つまりなんだ。お前はこの薄汚ぇ岩ごときを調べたいが為に、私欲に駆られて荷馬車を放り出し、手前の都合で無断に索敵班員を割き、挙句全員まとめて全滅寸前まで追いやられかけたってことか」
「言い方に棘があるなぁ、現実はもっとオブラートに包まれてるよ。私的に言うとね、素敵に不思議な岩を発見したって聞いたからみんなで見に来たら大ピンチ、みたいな」
「時間の無駄だったな。勝手に死んでろクソ眼鏡」
「冷たっ! せっかく来たんだから調べてこーよぉ、エルヴィンはなんて言ってたの?」
「………」
団長の名を出された途端、リヴァイは眼光鋭いまま押し黙った。ハンジが首を傾げるのへ、おずおずとリヴァイ班補佐の女性兵士・ペトラが切り出す。
「団長もこちらに向かっています。ただ、予定していた村落への補給物資の備蓄が遅れているらしく、兵長には一足先にハンジさんと合流するように言われまして…」
「てことは、団長許可が下りたってことだね。さすが我らが誇るエルヴィン団長殿だ。先見の質が違うねぇ」
「言ってろクズが」
にべもなく吐き捨てるなり、リヴァイは組んでいた腕を解き件の大岩に向き直った。他を省みず、すたすたと歩を進め近付いてゆく。相変わらず切り替えが早い。慌ててペトラが後を追い、何人かの班員へ引き続き周囲の警戒を頼んだ後、ハンジ達も続いた。
改めて、近くで見上げるとわかる。五メートルほど距離を空けているのに、傾げた首に痛みが走るほどである。全容は見渡せないが、遠目で視認した限りでは、形状は斜円錐に近いものだった。表面は黒光りし、時折油膜に似た鈍い虹色が見え隠れする。目立つ凹凸は少なく、一度融けて固まった蝋のように滑らかなくぼみがある程度だ。さほど硬質には見えないが、半端で力尽きたとはいえ、あの巨人の猛攻にも結果的には崩れずに耐え抜いたということになる。
降りかかった巨人の血液が蒸発途中なのか、岩からはうっすらと立ち上る煙がある。棚引くそれを何とはなしに眺めやる一行の前で、唐突にリヴァイが剣を引き抜いた。一閃、甲高い音が響く。
「うわっ!」
右手後方で悲鳴が上がる。腰を抜かした班員の足もとで地に刺さったスチールの刃が揺れていた。
「硬ぇな」
折れた残りの刃を捨てながら、リヴァイが無感動に呟く。あわや刃が刺さりかけた班員を慰めるモブリットを尻目に、ハンジは岩壁にまで近付きつつ顎に手をやりながら肩をすくめた。
「まぁ、スチール刃は元々折れやすいしね。ただ人類最強の一撃も通さないとなると、いよいよもって怪しさ大爆発だ。新種の鉱物かぁ…」
表面に手を添え、リヴァイの刃が通ったであろう位置を撫でるも、そこには滑らかな凹凸しか存在しない。何事かを呟きつつしゃがみ込み、散らばった岩の破片を拾うハンジの隣で、リヴァイが軽く握った拳で岩の表面を叩く。
「既出の可能性もある。レアメタルの詳細は工場都市の連中しか知り得ないしな。素材が同じなら斬れなくても道理だろ」
「そうだとしても、巨人が群がる理由にはならないよ。私が知る限り、人間以外に興味を示したところを見たのは初めてだ」
「だが最終的にはお前らに対象を移したんだろ? ということは奴らにとっちゃ生身の人間以下の価値ってこった」
「んんー、それなんだよねぇ」
拾い上げた小石を掌で転がしつつ、ハンジが立ち上がる。日に透かすように指の間でつまみ、空に掲げるが、透けるでも光るでもない。正真正銘、何の変哲もない、ただ恐ろしく硬いだけの石にしか見えない。
「それだけ!ってわけでもない、でもあれば飛びついちゃう! これって喩えるならなんだと思う?」
「さあ…、そうですね、なんだろう…」
ハンジがつまむ石を眺め上げながら、ペトラも首を傾げている。増援に駆けつけた兵士達は大体が半信半疑の顔つきだ。実際に巨人が群がる様を目にしたハンジ班の兵士やルカが説明しているが、その説明に対しての反応も薄い。奇怪な目撃談を頭から疑ってはいないながら、得体の知れなさを感じてはいるらしい班員達は、岩との距離をあけたまま遠巻きに伺うのみである。
コツ、コツ、とリヴァイの手が岩を叩き続けている。反響を確かめているのか、無言のまま繰り返していたが、やがて手を止めハンジに向き直った。掌を打ちつけ払いながら、顎をしゃくる。
「胡散臭ぇ話だが、此処まで来たなら調べるしかねぇ。時間が惜しい、とっとと動くぞ。まずは外周だ、二手に分かれて妙なところがないか確認しろ」
「了解! やる気になってくれて嬉しいよ」
そうと決まれば早速、とハンジが意気揚々と人数を割いてゆく。最後まで見届ける前に左側へ進みだしたリヴァイの後へペトラが続き、こわごわと岩の表面を撫でながら進んでゆく。
「なくてもいいけど、あれば嬉しい…なんでしょうね、なぞなぞみたいです」
「あの馬鹿が勝手にやってる妄想だ、あまり真剣に構えるなよ」
「はい。……あ、そうか…」
「…なんだ」
小さな語尾はリヴァイへ向けられたものではない。その証拠に、促す彼に中々返答は返らなかった。握った柄で表面を叩きながら進んでいたリヴァイはやがて、痺れを切らしたように振り返った。視線の先、補佐の彼女は苦い顔をして岩を見つめている。
「一つ、思い浮かびました。あってもなくてもいいもの」
「ほう」
「巨人にとっての我々、…食べても吐き出す人間」
ペトラの言葉には何も返さずに、リヴァイはまた前へ向き直った。引き続き岩へ柄を叩きつけながら歩を進めてゆく。