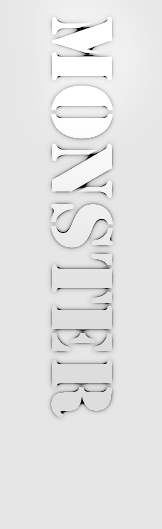MONSTER
1.苔の生すまで
舌は火である。不義の世界である。
舌は、わたしたちの器官の一つとして具えられたものではあるが、全身を汚し、生存の車輪を燃やし、自らは地獄の炎で焼かれる。
あらゆる種類の獣、鳥、這うもの、海の生物は、すべて人類に制せられるし、また制せられてきた。
ところが、舌を制しうる人はひとりもいない。それは制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。
わたしたちはこの舌で父なる主を賛美し、またその同じ舌で、神に模って造られた人間を呪っている。
---ヤコブの手紙 第3章6節より
雨が降ってきたのだろう。
頬ごと押し付けた右耳が、苔生した岩肌に染み入る水の音を聞いた。巌に響く雨滴はしくしくと低く、ごく幽かだが、じきにそこかしこから雫が垂れて来る。しかし小雨は徒に群生する地被の間を流れるだけで、貯水までには至らない。こうして、肌を押し付けたところにだけ、滴りはゆっくりと染み入ってくる。
目を閉じたまま、口をあけ、舌を突き出した。蘚苔の表面は砂埃でざらつき、慣れた土の味がする。構わず上下に舐め動かすと、にわかに染み出した雨滴が舌先を濡らした。そのまま、上顎へ塗り付ける様に嚥下する。貼り付いた喉奥が開く。ひりつく咽喉を慰めるように二度、三度と同じ事を繰り返す。かみ締めた奥歯がざり、と鳴った。
暫くそのまま、苔伝いに身体を這う水気に身を任せていると、ふいに天へ晒した左頬に雨滴が弾けた。飛散った雫がちょうど目淵に落ち、閉じた目の内に滲み入ってくる。
壁面を伝わずに雫が落ちてくるとなると、思うよりも雨脚が強いのかもしれない。漏った雨滴は貴重な水源である。薄目を開け辺りを伺うと、やはりまだ薄暗く、視界は明け前の群青に染まっている。音を立てないように壁から身を起こし、低い位置にある地面を見下ろせば、記憶に違わぬ数の影が静かに寝入っているのが見えた。僅かながら水音に混じり、寝息が岩壁を駆け上がってくる。
陽の射さないうちから彼らを刺激するのは得策ではない。だがこれからいつ乾季に入るとも知れない。幸いな事にここ数日は雨天に恵まれ貯水は文字通り潤ったが、水が尽きかけ痛い目を見た記憶もまだ新しい。背に腹は変えられないだろう。
投げ出したままの手を少し動かせばすぐ、指先に小石が当たる。いくつか手ごろな大きさを見繕い、掌に集めた。小石もひんやりと濡れていた。眼下へ投げ棄てる。一拍を置いて、硬く軽い音が反響する。
その後すぐ、悲鳴が上がった。
鉛色をし、低く垂れていた雲が去った。雨靄に烟る視界が徐々に晴れてゆく。濡れそぼった石畳はあちこちが欠け、割れた地表から名も知れない雑草が伸びている。人の往来が耐えて久しい道だ。馬脚を乱すほどではないが、荒れた街道に馬も少なからず不満を感じているらしい。鼻息荒く蹄を踏み鳴らしている。
現時点において、今回の調査兵団による壁外調査は目立って大きな損害もなく進攻していた。索敵陣形の思惑通り、視界内の巨人を振り切ったあとは大規模な交戦に発展せず、打ち上がる煙弾も方向を示す緑色ばかりが空を切る。近年稀に見るこの順調な道程を好機とみなし、隊はそのまま一気に南下。シガンシナ区近郊の集落跡にて一時散開し、今後の兵站拠点を築くにあたっての探索に入った。補給物資を運ぶ荷馬車の護衛を兼ねながら進む分隊に奇妙な一報が齎されたのは、視界を遮る驟雨を避けてすぐだった。
「巨人が岩に群がってる?」
ゴーグルについた雨滴を拭いながら、分隊を指揮するハンジ・ゾエは今しがた伝えられた情報をそのまま繰り返した。横殴りの雨は兵団の分厚いコートをすり抜け、長めの黒髪からはまだ雫が落ちている。
「何それ、要するに奇行種って事かな?」
「その可能性が濃厚かと思われますが、目視できる限りで七体ほどの巨人がその大岩に齧り付いていました。単なる奇行種にしては何らかの目的意識がある行動のような…」
「うーん、ただの岩好きがそんなにいっぱい居ないよねぇ」
初列・索敵班の兵士は陣形散開後もそのまま斥候を担い、三名前後の少数班にて身軽さを生かしての情報収集と口頭伝達を行っていた。逸る馬を御しながら現れた金髪の若い兵士はルカと名乗り、荷馬車に合わせて速度を落として進むハンジへ並び、息を整えている。
彼の班は四人構成らしく、振り返れば後方に疾走する影が見える。速さのある彼が先に追いついたのだろう。このまま、こちらを追い抜いたその先には、中央陣頭指揮を執る団長がいる。その他精鋭は間に件の斥候を挟みつつ、縦横無尽に探索活動を行っているはずだ。
後方と前方を交互に確認後、なにやら思案に沈むハンジを見て、それまで黙って付き従っていた分隊長補佐・モブリットが恐々と声をあげた。
「分隊長…駄目ですよ? 絶対駄目ですよ?」
「やだなぁ、まだ何も言ってないよ?」
「言わなくてもわかります。っていうか言わないでください。せっかくこんなに軽微な状態でここまできたのに、何考えてるんですか? いえッ、やっぱり聞きたくありません!」
「どっちだよー」
はははと朗らかに笑うハンジの眼は既に笑っていない。残り三名の索敵班員がその顔貌を判別できるまで追いついた頃には、進行する荷馬車を一旦止めるに至っていた。
「分隊長! 駄目ですってば!」
「わーかってるよぉ、もちろんエルヴィンに確認しなきゃね。まぁ多分大丈夫だと思うけど」
「だからそれが駄目なんですって…ああもう最悪だ…」
頭を抱えるモブリットを見て困惑するルカに気にするなと手を振りつつ、ハンジは遅れて追いついた三名に後方班の大まかな位置を確認する。その言動だけでこの後の展開を悟ったモブリットが、今度は無言のまま大仰に天を仰いだ。打ちひしがれる彼を尻目に、ハンジは意気揚々と指示を出してゆく。
「物資の護衛はこのまま後続のみんなに引き継ごう。幸いこの先は風車やら何やら高めの建物が多いから、巨人が大群で押し寄せて来ない限りは立体機動で何とかなるよ。君たちは二手に分かれてそれを伝えてきて欲しいな。あっ、団長に駄目って言われたらすぐ引き返すからさ、その場合も悪いけど知らせてね。で、その岩ってここからどのくらい?」
「はい、さほど離れてはいません」
言葉尻の後半をルカに向けると、彼は主副それぞれの反応の違いに特に面食らう様子は無くそのまま彼方を指を指し、淡々と道程の説明を始める。
曰く、北西に三キロほど進むと緩やかな勾配が始まり、やがて小さな集落跡、その奥に巨木の林道が続く。大岩はその林の中に忽然と姿を現し、高さ二十メートルを越す威容だという。
「巨人がこちらに気づくのを警戒し距離をとったままの確認でしたので、大きさは憶測でしかありませんが…」
「いやいや十分。他はなんか気になった?」
重ねて問うハンジに、後続三人のうち一人が控えめに手を上げた。
「集落から林、その岩まで、荒れてはいましたが舗道が続いていました。林道までは恐らく材木の搬出用でしょうが、道が奥の岩までにも続いているとなると、当時はそこまで何かしら住民の行き来があったようです」
「へぇ、ってことは意味のある岩か。趣向は違うけど巨大樹の森みたいなものかな…、うーんますます気になるねぇ!」
「…分隊長。言っても無駄でしょうけど、それでもやっぱり一応言わせていただきます」
「ん? なんだい?」
律儀に前へ倣って挙手をしつつ、モブリットが虚ろな目のまま続けた。
「今回我々は補給物資の護衛班です。およそ兵站拠点開拓班といってもよいです。次回以降壁外調査をスムーズに行う為に一番重要な班です。それを任されたという事にどうか、誇りを持っていただいてですね、無闇矢鱈にわけの分からない岩に行くことは次回以降にしたほうが絶対に絶対に絶対に懸命です。岩は逃げません。よしんば逃げる岩でも一向に構いません。そんな岩無視です。クソくらえです」
「なにいってんのさモブリット! これはチャンスだよ!?」
抑揚なく切々と懇願する補佐にすら微塵も動揺しないまま、ハンジが笑顔で両手を広げる。
「明らかに不審な岩! そこになぜか群がる巨人たち! しかも多数! 最っ高に滾らない!?」
「滾りません」
「滾らなきゃ!滾るとき滾れば滾らなきゃ!」
「意味が分かりません…」
容赦無い部下の進言にもめげず、からからと笑う班長はそのまま、おもむろに馬首を返した。突然の方向転換につられ振り返った面々の視界に、少し距離が離れていた後続班がこちらに向かってくる様が映る。話し込むうちに追いついたのだろう、どうやら欠員は居ないようだ。併走する馬と供に、相当数の班員が泥を巻き上げ駆けている。
片手で額にひさしを作り、増員を眺めながら、依然変わらぬ陽気な声でハンジが言う。
「じゃ、尚更行かなきゃね。巨人の謎に迫るチャンスを忌避してちゃ、調査兵団失格だよ」